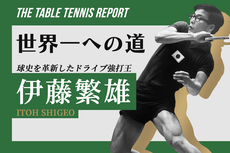無名選手
伊藤は東京選手権大会に出場するため、3月上旬に上京した。広島の大竹高校を卒業したばかりの広田佐枝子も一緒だった。東京駅には専修大学からの迎えが来ているはずだった。二人はホームの雑踏の中で辺りをきょろきょろ見回していたが、専大のマネージャーはすぐにセーラー服姿の広田に気づいたらしい。
「おお、よく来たな。待ってたぞ」と、片手を挙げて近づいてきた。
「広田、長旅で疲れただろう。ご苦労さま。合宿所に着いたらまずはゆっくり休めよ」
マネージャーは、インターハイ準優勝の広田をしきりに気遣った。
「荷物、重いだろ。俺が持ってやるよ。いいから、いいから、遠慮するな」
彼は、歩き出す段になってようやく、所在なさげに傍らに突っ立っている伊藤に目を留めた。そして「あれっ」といような怪訝(けげん)な顔で言った。
「ん、おまえは何だ?」
「三菱レイヨンから来た伊藤です。お世話になります」
「ああ、お前が伊藤か。まあ、ついて来い」
伊藤は重いかばんをひきずりながら、すたすたと前を行くマネージャーと広田の背中をにらみつけた。
「くそ。ばかにするのもいいけげんにしろよ。俺は西日本選手権チャンピオンなんだぞ。今にすごい成績を挙げて、こっちに注目させてやるからな」
伊藤はこのとき、人の波を押し分けながら、上京前からの決意を新たにした。
河野満
伊藤と同期で専大に入学した選手の中に、後に世界チャンピオンとなる河野満がいた。河野が青森商業高校時代にインターハイや全日本ジュニアで活躍していたことは知っていたから、伊藤は「一体どんなやつだろう」と彼に会うのを楽しみにしていた。
「河野です。よろしくお願いします」
そう名乗ったのは、色の白い、東北なまりの青年である。どちらかといえば動作がのんびりしていて、大股(おおまた)でずんずん歩く伊藤とは対照的だった。いかにもとっつきにくい、というのが最初の印象だった。
しかし、伊藤は河野と球を打ち合ってみて「こいつは天才だな」と直感した。表ソフト速攻型で、ボールへの感覚の鋭さが抜群に優れていた。
口数が少なく自分から声をかけてくることはあまりないが、話してみると、卓球への熱意が人一倍高く、自分のプレーについてしっかり考えていることもわかった。
伊藤は、河野に追いつき、そして追い越すことを目標に決めた。
東京選手権大会
伊藤は1カ月前に西日本選手権大会で優勝していた自信から、東京選手権大会にはベスト8入りを狙って臨んだ。シードされての初戦で慶応大学の左ペンホルダー攻撃型、本美選手と当たった。
ところが、である。相手のサービスのタイミングに動きを合わせられず、レシーブにてこずり、あれよあれよという間に失点を重ねてしまったのである。
思いもよらない敗退だった。西日本で名を馳(は)せた自分の方が格上のはずだというプライドが邪魔して、集中力を欠いた結果だった。
伊藤はラケットを引っつかんでベンチに戻りながら、憤懣(ふんまん)やる方ない思いを両腕に込めた。ラケットは「バキッ」という音を立て真っ二つになった。
「誰に対してもベストを尽くす、それが俺のモットーではなかったのか。西日本選手権大会での優勝を鼻にかけて相手をなめるなんて、最低だ。こんなふまじめな試合は二度としまい」
これが、試合で負けた腹いせだとしたら、おおよそ褒められたことではない。用具を大切に扱うことは、卓球選手として当然のマナーである。ましてやラケットを割るなど論外だ。
しかしこのときの伊藤のそれは、まったく異なる意味を持っていた。単に悔し紛れのものではなく、知らず知らずのうちにごう慢になっていた醜い自分と、静かに決別するための行為だったのである。
1日の生活
専大に入学すると、想像以上に厳しい寮生活が待ち受けていた。
1年生は毎朝6時に起床する。それも目覚まし時計を使うなどもってのほかである。同じ部屋で寝ている先輩を起こしてしまうからだ。代わりに毎晩「明日は6時に起きる、絶対6時に起きる」と何回も唱え、自己暗示をかけて寝た。
寝床を片付けて、部屋とトイレを掃除し、先輩のユニフォームがそろっているかを確認する。それが終わると道場に駆け上がって床の雑巾がけをし、7時までには台をピシッとそろえて並べておかなければならない。
7時からは準備体操とトレーニングが始まる。まずランニングである。5~10キロくらいを走るのが常だった。専大の周りは丘陵地帯になっており、クロスカントリーには最適だった。
途中までは全員でペースを合わせて走る。
「ファイト、はぁはぁ、ファイト、はぁはぁ」
「ファイト、ひぃひぃ、がんばれ、ひぃひぃ」
「1年生、声が小さい。もっと気合を入れろ」
1、2年生の掛け声に混じって、上級生の怒号が飛ぶ。
折り返し地点まで来るとフリーになる。先輩よりゴールが遅ければうさぎ跳びをさせられるとあって、みんな必死である。
「ああ河野、俺はもう倒れるかもしれない」
「伊藤、俺もだ。はぁはぁ」
後の世界チャンピオンとて、最初から体力的に優れていたわけではない。伊藤も河野も、むしろ持久力不足に悩まされていたくらいだった。しかし、甘えて立ち止まることは許されない。励まし合って走り切るのみである。
余裕のある野平主将などは、後ろ向きで走って、からかい半分に伊藤に声をかける。
「伊藤、どうした。ちっとも進んでないぞ。根性を入れて、もっと足を動かせ」
「はぁはぁ、がんばります」
足はふらつき、コースまでゆがんで見え、よたよたしているように思えた。
その後は道場に帰って来て腹筋運動、背筋運動、腕立て伏せをかなりの回数やらされた。朝のトレーニングだけでへとへとになってしまう。
しかし、本格的な練習はそれからである。
午前中はフットワークなどの基本練習、午後と夜は課題練習と試合が中心だった。
伊藤は大学に入るまで1日に5分程度しかフットワーク練習をしたことがなく、いきなり30分のノルマを課せられて参った。ノーミスで左右に厳しく回されるボールを、すべてフォアハンドで打ち返す。ノータッチで抜かれようものなら、すかさず先輩にほうきでおしりをぶたれる。
苦しくてたまらず、「早く時間が過ぎてほしい」とそればかり考えていた。ボールを拾いに行くのにもわざと息を弾ませて時間を稼ぎ、汗もゆっくりとぬぐった。
ようやく相手を動かす側に回っても気は抜けない。少しでも横着すると、「微調整をしろ」と怒鳴られる。このときも下手に返すと後ろからぶたれるのは同じである。
「ファイト、ファイト。元気を出していきます」
専大では、練習中の声出しが特に重視されていた。
声を出すと、集中力を上げたり気持ちを積極的にしたりできるだけではない。ボールを打つ瞬間に発声して腹筋に力を入れることで、打球点が安定し、正しいラケットワークができるようになる。また、体全体のリズムをつくる意味もあった。
それも、ただ胴間声(どうまごえ)を張り上げればよい、というのではない。他人を寄せ付けないような気迫に満ちた掛け声が求められていたのである。
専大の道場は決して新しくはなく、カーテンがところどころ破れ、台も旧式のものだったが、床はいつも黒光りしていた。選手たちが毎日磨き上げていたからである。道場内の雰囲気は常に高く保たれ、不用意に音を立てようものなら、ほおが空気にピリッと切られそうなほどだった。
世界のトップ選手を何人も生んだ専大は、このような大学だったのだ。
卓球日誌
伊藤はこのような生活の様子を、事細かに日誌に記していた。その日誌は今でも大切にとってある。うぐいす色のどっしりとした日記帳である。現役時代を通して書き続けたため数冊に及ぶ貴重な記録となっており、その中の1冊の冒頭には、
「一度しかない人生を
一度しかない自分を
本当に生かさなかったら
人間生まれてきた
かいがないじゃないか」
という、山本有三『路傍の石』の中の一節が引かれている。勢いのある、力強い筆致である。
毎日欠かさず付けていたわけではないが、たいていは1日に1ページ、多いときには数ページにわたってぎっしりと書いた。対外試合や部内試合の成績と敗因分析、詳しい図のついた練習計画、そして最後には自分を鼓舞する文句を書き連ねた。
「シゲオ、まだまだ貪欲(どんよく)になってないぞ」
「一日一日、くいを残さぬよう、必死でやるぞ」
「目指すは世界、そのためには練習で泣け」
「さあ、明日もがんばろう。母さん、見守ってください」
日々の出来事を淡々と記すというより、言葉を自分の心に深く刻みつけようとしていたかのようである。
伊藤は、練習に明け暮れる生活の中でも、このように自らを振り返る姿勢を大切にしながら、前へ前へと進んで行ったのだ。
専大卓球部訓
専大卓球部には、「矛盾を矛盾と思うな」という部訓があった。伊藤は最初、この意味を理解できなかったが、専大の生活に慣れていくにしたがって、少しずつ納得できるようになった。
例えばトレーニングで腕立て伏せ300回を命じられるとする。22~23回が自分の限度だと思っていた伊藤には、当然こなすことができない。
しかし「先輩、300回は無理です」などと言おうものなら、すかさず「伊藤は気持ちがたるんでいる。連帯責任として全員に50回追加する」と切り返される。いくら辛くても、やらなくてはならない状況に追い込まれるのだ。
やっとのことで20回までやると、腕が硬直してしまい、もうだめだと考えてしまう。周りを見ると、大声を出して必死でやっている仲間たちも同じで、頭を上下に動かすことしかできなくなっている。
それでも顔を真っ赤にして何とか力を振り絞り、腕をがくがくさせながら、なんとか「...298、299、...ええい、...300」と数え終える。
これを繰り返すうち、伊藤はあることに気づいた。
それまで自分は22~23回が限界だと思っていた。300回などあまりに非常識な数字で、いくら腕力のある人でも不可能だと考えていた。しかし、実際に深く腕を曲げられたのは数十回にすぎなかったにしても、気持ちの上では300回にも耐えられた。自分で限界をつくってしまうとそれを超えることはできないが、無限に向かって必死になればなんとかなる、それが「矛盾を矛盾と思うな」という部訓のいわんとするところではないかと考えたのである。
とにかく専大の取り組み方は普通とは違った。非常識が常識になっているのが専大だったのだ。
ひざを壊すのではないか、肩を痛めるのではないか、筋肉が引き攣(つ)るのではないか。普通の人ならこう考えるところだが、専大の選手は違った。それで故障するくらいなら、自分はそれだけの力しかない、専大で卓球をすることはできないと思うのだ。ましてや、本当に故障したら「喜べ、一流に近づいた証拠だ」とまで言われた。
いくら練習がつらくても、名を挙げるまで故郷には帰らないという決心を胸に上京した伊藤には逃げるところがなかった。耐えて先輩たちに食らいついていくしかなかった。
入学前は卓球の苦しさなど知らなかった。好きさ加減は10なのに、5しかできないことの方が多かったからである。しかし、大学では15以上やらされる。毎日が限界への挑戦で、合宿生活に慣れること、練習についていくことで精いっぱいだった。他のことをやる余裕はなかった。
最初の半年
実業団から大学に入った伊藤のような選手には、初めの半年は対外試合に参加できないという研修期間規定があった。せっかく練習に励んでも、試合で結果を出す機会を与えられないのは悔しいものである。専大にも、いったん社会に出てから入学した先輩が何人かいたが、半年の間には、我慢しきれず努力を怠る例があった。
一方、試合で自信をつけた選手は大きく成長する。伊藤は、河野には4対6くらいの割合で勝ったり負けたりしていたが、新人戦で優勝したあくる日の彼には太刀打ちできず、たった1日で一皮むけたなと驚いたことがあった。
しかし、伊藤はこの半年をマイナスだと考えて気を腐らせたりはしなかった。基本を身につけ今後どういう卓球を目指すのかを見つめる、自分だけに与えられたチャンスだと思い直したのである。
周りで練習しているのは、学生大会ではもちろん、全日本レベルで活躍している選手たちである。一緒に練習したり試合を見たりするだけで、勉強になった。ときには元世界チャンピオンのOBやOGのアドバイスを受けられることもある。
専大の部訓には、「専修を制する者は関東を制す。関東を制する者は日本を制す。日本を制する者は世界を制す」というのもあった。専大はそれまでに川井、富田、野平(明雄)、星野、渡辺、松崎らの世界選手権メダリストを輩出していた。「専修を制する者が世界を制する」と言っても、ただの誇張ではなかった。
それまで専門の指導を受けたことのなかった伊藤である。卓球に関する知識がまだ不十分で、プレーの組み立ても自己流の域を出ていなかった。フォアハンドで払いたいから払う。ドライブを使いたいから無理にでも仕かけるというような自分本意のプレーを押し通そうとして失敗することが多かった。試合の流れの中で相手の嫌がる戦術をどう編み出すか、それを実行に移すための技術をどう実につけるか。考えることはいくらでもあった。
サービスはどの位置からどう出すか、レシーブはどこで構えるのがいいのか、ラケットの振りは十分に速いかどうか、自分の動きをボールにどう合わせるのか、一つひとつチェックしながら理想の型に近づけた。
一生懸命やっているとスランプに陥ることがある。フォアハンドの振り方や足の動かし方、そんな基本的なことがわからなくなるのである。
こういうとき伊藤は、
「伸びない選手にはスランプもない。本気でやった証(あかし)がスランプなんだ。これは喜んでいいことなんだ」と自分に言い聞かせた。
うまくいかないのには必ず理由があるはずである。基本姿勢はいいか、ストライクの位置で打っているか、戻りは素早くしているか。自分の動きの狙いを、焦らず丁寧に確認していった。
研修期間を終えた伊藤が東京選手権大会以来初めて出場できたのは、東日本学生選手権大会の予選だった。
この直前の合宿で、伊藤は奇跡を起こした。1年生ながら部内リーグ戦で1位になったのだ。学生から唯一の世界選手権大会代表となった野平、全日本のダブルスで優勝した有本、全日本学生のダブルスで2回優勝した大野、そのパートナーでこの年に隻腕で全日本学生チャンピオンになる北村、売り出し中の宮之原、そして新人戦で優勝した河野らをすべて破って14戦全勝である。
この1週間の合宿では、のどが3回もつぶれた。それほど気合が入っていたのである。半年間の練習の成果を、ここで存分に発揮したといえるだろう。
入学した時点の伊藤は、技術面でも体力面でも専大で求められるレベルには遠く及ばなかった。そんな中でがむしゃらに努力することで確実に実力をつけ、いつの間にかそのレベル以上のものまで狙えるようになったのである。
東日本学生選手権大会予選の決定戦で対戦したのは、高校時代に国体で負けた梨本(中央大)だった。1ゲーム目はあっさりと敗れたが、2ゲーム目を8-12から逆転勝ちして部内リーグ1位の自信を取り戻した。そして3ゲーム目は圧勝し、本戦出場を決めた。その後の本戦ではランキング決定戦まで進み、鍵本(早稲田大)にゲームオールで敗れた。
全日本学生選手権大会ではランキング決定戦で初顔合わせの長谷川(愛知工業大)にゲームオールで負けた。全日本選手権大会はシングルスとダブルスでは予選落ちしたが、広田と組んだ混合ダブルスで、前年優勝の三木・関組を破って3位になった。しかし、東京選手権大会ではランキング決定戦で敗れた。
人の4年を2年で
2年に進学してすぐの関東学生選手権大会ではダブルスで優勝、春の関東学生リーグ戦でもポイントゲッターの一人として活躍し、全勝した。
しかし、関東学生選手権大会や東日本学生選手権大会のシングルスで思うように成績を残せていないのが、痛いところだった。世界を視野に入れるとなると、シングルスで好成績を挙げることは必須条件である。
伊藤は入学する前に、
「2年遅れて入学した俺は、他の人が4年かかって挙げる成果を、2年で挙げる覚悟で練習しよう」と心に決めていた。その伊藤にとって、2年時の東日本学生選手権大会は一つの節目としての意味を持っていた。
「もしランキングに入れなかったら選手としてこれから大きく伸びる可能性は少ない。選手を辞めてマネージャーになろう」とまで、自分を追い込んでいた。
苦しい家計をやり繰りして自分を東京に送り出してくれた家族に報いるためにも、なんとかして結果を出したかった。
そのためには試合前の暑い夏休みをうまく使って、効果的な練習をしなければならない。どうすればランキングに入れるか。伊藤は練習方法を必死で考えた。
(2001年8月号掲載)