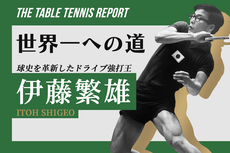上京して
高校を卒業した伊藤は、就職先を東京のニッタク(日本卓球株式会社)に決めた。卓球のことしか念頭になかった伊藤は、その社名を聞いて勤務時間外には思う存分練習ができると思い込んだ。東京の強い選手と試合ができると、そればかり考えて胸を弾ませていたのだ。
卒業式の前日も在校生が式場準備を始めるまで講堂で汗を流し、式を終えるとその日のうちに列車に飛び乗って東京に向かった。新しい練習場を早く見たいと好奇心の塊のようになっていた伊藤には、新幹線のなかった当時の延々14時間の道のりがもどかしくて仕方がなかった。
ニッタクの本社は上野にあった。案内されて仕事場を見て回りながら、まず練習場を探した。1階のそんなに広くない部屋に、卓球台が1つ据えてあった。
よし、ここで思い切りやれるぞ。
伊藤はにんまりした。
ところが、翌日から伊藤を待っていたのは卓球用品の出荷にてんてこ舞いの生活で、とても練習に励む余裕はなかった。朝は早くから出勤しなければならず、夜は9時までの残業が当たり前だった。そのころの日本では卓球が大流行しており、いくら出荷しても需要が満たせないほど用具の注文が殺到していたのだった。高卒で入社した伊藤は初めのうちは製品の梱包作業が中心だったが、あまりの忙しさにボールの選別にも加わるようになった。
平日の練習といえば、昼食を急いで済ませて1時間弱の休憩から40分程度の時間を捻出(ねんしゅつ)するのがやっとだった。着替える時間さえも惜しく思え、午前中はユニフォームを着て作業した。また、練習といっても名ばかりで、同僚たちが和気あいあいとピンポンをしている中で、本気でボールを打つことは憚(はばか)られた。せいぜい素振りをして気を紛らわすくらいである。夜は夜で、練習は寮の消灯時刻の10時までと決められていた。9時に寮に戻り、食事と入浴を終えると、もう何もできなかった。しかも20人の社員に対して台はたった1台しかない。思い描いていたのとあまりに異なる生活に、伊藤は戸惑った。
そんな伊藤が生き返ったような気持ちになれるのは日曜日だった。ニッタクチームの代表として実業団の試合に出場することができたからである。これを楽しみに、練習不足を体力でカバーしようと不忍池の周りを走ってトレーニングをした。それでも練習せずに試合に出るだけでは上達は望めない。それどころかランニングや昼休憩の練習だけでは、実力の低下をいかに最小限に押さえるかというほどの意味しかなさなかった。
卓球への飢餓感
卓球がやりたくてもできない欲求不満の日々を過ごす中で、伊藤は自分がどれだけ卓球に執着しているかを思い知らされた。中学、高校時代には味わうことのなかった、切実なまでの卓球への思い入れと飢餓感だった。卓球がやりたい、好きなだけボールが打てたらどんなにいいだろうか。思いは日増しに募っていった。
会社で作業していると、大学の卓球部員が姿を見せることがあった。高校時代、伊藤が国体の準決勝で対戦した梨本も、
「こんにちは、中央大の梨本です。ボールを受け取りにきました」とやってくる。作業着で仕事に追われる伊藤は、彼らへの羨望(せんぼう)で胸がいっぱいになり、まともに顔を上げることができなかった。大学や職場で順調に卓球を続けられている人には、このやるせなさは理解できないだろうと思った。
このような日々が半年も続くと、次第に諦(あきら)めの気持ちが生まれてきた。いくら努力しても練習は週に3時間がやっとである。強豪選手とたくさん試合ができるという、上京前に想像していたような生活は望むべくもない。卓球のことは潔く忘れようかと思い始めた、ちょうどそのころである。郷里から電話がかかってきた。次兄だった。
転職
「お前、こっちに帰ってこないか。俺の知り合いの勤めている三菱レイヨンが、今度卓球部を強化することにしたらしいぞ。繁雄をチームにほしいと頼まれたんだ」
思いがけないこの言葉に、伊藤はオウム返しに聞き返していた。
「残業はあるの」
初めての職場の忙しさに懲りた伊藤が真っ先に確認したかったのは、給料や仕事内容よりもまず、残業の有無だったのだ。
「いや、残業はないらしいぞ。勤務は午後5時までだ」
それで伊藤の心は決まった。
次兄が声をかけてくれるまでには、実はそれなりの経過があった。
伊藤は筆まめなたちで、郷里の知り合いに何通も手紙を出し、思うように卓球ができない不満を訴えていた。
強い仲間と好きなだけ卓球ができると勇んで上京したのに、当てが外れた。半年間、できる限りの努力をしてきたがうまくいかない。ボールが打てなくては、毎日の生活に張りが出ず、どうしようもない。いっそのこと卓球は諦めようかと思う。
こんな調子で、中学、高校時代の先生、卓球仲間、学友に書き送りつづけた。書くことで少しでも鬱憤(うっぷん)が晴らせればとの思いからだった。悶々(もんもん)とした思いを何かに向かって発散し、誰かに理解してもらわなければ、自分がどうかなってしまいそうだったのだ。
伊藤の熱意が通じたのだろう。郷里の人々の間で、伊藤のことを気にかける人が次第に増えてきた。
「あいつ、相当悩んでるんじゃないか」
「何とかしてやらないとかわいそうだな」
伊藤が卓球を続けたがっているという噂は、めぐりめぐって三菱レイヨンのキャプテンの耳に入った。折しも三菱レイヨン卓球部は強化方針を打ち出したばかりで、山口県の元高校チャンピオンならば是非にと、トントン拍子に話が進んだ。手紙に託した伊藤の一途な思いが実を結んだといえよう。
三菱レイヨン
会社に辞職願を出し、伊藤は東京を発った。次の就職先は広島の三菱レイヨンである。
練習場には卓球台が4つ備えてあり、部員は10人ほどだった。3交代制で勤務するため同時に練習するのは4、5人だったが、カットマンや右ペン裏、左ペン表など戦型は多彩で、広島県の実業団の中で常にベスト4以上に入っていた。
毎日5時に勤務を終えてどんぶり飯1杯をかき込むと、伊藤はすぐ卓球場に向かった。練習時間の開始前から台を拭き、ネットの高さを測り、素振りやサービス練習をしてほかの部員が現われるのを待った。やっと好きなだけ卓球ができると思うと、とてもじっとなどしていられなかったのだ。
実力の近い同僚と何度も試合をする中で、ドライブと強打を巧みに組み合わせた伊藤の卓球の型が生まれてきたのは、この時期である。「独特のサービスを出し、ループドライブや速いドライブを仕掛けてチャンスをつくり、スマッシュで決める。レシーブのときでも、フォアハンドから常に先手を取って強打に結びつける」。当時ではまだ新しい卓球スタイルだった。現在では、ラケットスイングが速ければ速いほど、またフットワークの足数が多ければ多いほどよいというのはほぼ定石だが、そのころはそれほど声高に言われているわけではなかった。伊藤は自らの経験から推してこの2点を重視し、速い素振りと細かい足の動きを入れたトレーニングを毎日行った。
実業団としての伊藤が頭角を現し始めたのは、年明けの全日本軟式広島県予選からである。この大会の決勝で、伊藤はそれまでに2度負けていた原田選手(三菱造船)と対戦した。原田は全日本チャンピオンの木村興治選手に勝ったことがある選手で、伊藤がどうしても勝ちたいと思っていた相手だった。伊藤はこの原田に大接戦の末3-2で勝ち、大きな自信を持った。
全日本軟式の本戦は、盛岡で開かれた。伊藤は、優勝候補といわれた水村選手(大日本印刷)を破って準々決勝に進み、再び原田選手に勝って3位に入賞した。
自信につながったもうひとつの試合は、2年目の広島市長旗争奪卓球大会だった。
この大会には、関東学生リーグ1部で優勝していた日本大学卓球部が、招待されてエントリーしていた。個人戦上位入賞者の候補には当然日大の選手の名前が挙げられていたが、ここで三菱レイヨンの選手が波瀾(はらん)を巻き起こした。ベスト8のうち5名を占め、伊藤が優勝したのである。翌日の団体戦ではさすがに奮起した日大に敗れたが、この大会での快挙は伊藤の実力が全国で通用するレベルにまで達していることを証明してくれた。
専修大への憧れ
このように目標を広島から西日本、全国へと広げつつあった伊藤の野心を、さらにかきたてる知らせが舞い込んできた。
地元の大竹高校の生徒で三菱レイヨンによく練習にきていた広田佐枝子が、インターハイで準優勝し、その実績によって専修大学への推薦入学を決めたというのである。
話を聞いた伊藤は、初めはただうらやましく思うだけだったが、次第にそれだけでは気持ちが収まらなくなってきた。
三菱レイヨンでの練習に不満があったわけではない。それどころか三菱レイヨンに勤めた1年半の間、伊藤は辛いことなどほとんど感じなかった。卓球ができること、ただそれだけが喜びだった。このころの伊藤の卓球日誌には、
「夢ならどうか覚めてくれるな」
「俺はこんなに幸せでいいのか」
という言葉がしきりに出てくる。
しかし、目標が高くなるにつれて、日々の練習に物足りなさを感じるようになったのも事実である。卓球で名前を残したい、自分の限界に挑戦したいという夢は膨らむ一方だった。
専大といえば練習が厳しいことで有名で、世界で活躍する選手を何人も輩出している名門大学である。伊藤はかねてから、大学で卓球ができるなら「絶対に専大で」という憧れをひそかに抱いていた。
専大に行けば、広田はますます強くなるだろうな。専大の厳しい練習を4年間辛抱すれば、人格的にも大きく成長できるに違いない。
俺も専大に行きたい。あの広田が行けるのなら、俺だって無理ではないかもしれない。大竹高校のつてで、俺も「一緒に」推薦してもらえないだろうか。自分の身近な人がスカウトされるなどというチャンスは、もう2度と巡ってこないだろう。
伊藤は早速、大竹高校の金川先生に相談した。
「先生、僕も広田のように専大で卓球をしてみたいんです。専大の監督に僕のことを話していただけないでしょうか」
「伊藤君のやる気はよくわかるから是非とも推薦してやりたいが、硬式の全国大会の実績がないとなあ。とにかく全日本でがんばってみることだよ」
金川先生の言葉を受けて臨んだ、その年の全日本選手権。勝ち進んだ伊藤が対戦したのは、奇(く)しくも専大の強豪・宮之原選手で、試合展開は白熱した。この対戦を専大の四十栄監督と野平時期キャプテンが観ていた。専大ではすでに河野満選手をはじめとする優秀な高校生の推薦入学を決定しており、将来のレギュラー要員の確保はできていた。そのため特に伊藤を望んで採用しなければならないほどの必要性はなかった。
「あれが、うちに入りたがっている伊藤という選手らしいですよ。宮之原を相手にあそこまで善戦するのだから、まあまあ見込みはあるかもしれませんね」
「ううむ。広田佐枝子を採ることだし、伊藤も採って様子を見ようか」
「そうですね」
こうして伊藤は、良いようにも悪いようにもとれる「まあまあ」という言葉とともに専大に滑り込む許可を得た。
家族会議
しかし伊藤には重要な仕事が残っていた。家族を説得することである。山口の実家では父親が病気で臥(ふ)せっていた。伊藤を大学へやるような経済的余裕のないことは、十分過ぎるくらい分かっていた。
しかし今回だけはどうしても引き下がれなかった。ここで妥協したら一生後悔することが分かっている。伊藤は考えあぐねた末に腹を決め、一生で1度の頼み事をするからと、郷里に電話をかけた。そして2年間で貯めた給料の貯金通帳を握りしめ、山口に向かった。
一番奥の畳の間で車座になった家族に、伊藤は改まって正座し初めて大学進学の意志を打ち明けた。
「今日わざわざ集まってもらったのはほかでもないんだ。僕のわがままをどうか聞いてください」
皆は伊藤に同情しながらも、容易に首を縦に振ろうとはしなかった。兄や姉も、早くから就職したり定時制高校に通ったりと、それぞれに苦労していた。
「今の安定した職場を捨てて、成功の保証もない卓球の世界に飛び込むなんてとんでもない。家族に迷惑がかかるでしょう。家が苦しいのを分かっていて、どうしてそんな勝手なことを言うの」
「卓球で自分の限界に挑戦する?何を言ってるの。私も絶対に反対だよ」
姉たちの意見は厳しかった。
兄たちは総じて伊藤の冒険心を認めてはくれたが、経済的に支える力がないからとため息をつくばかりだった。
伊藤は通帳を傍らに、頭を畳にこすりつけんばかりにして懇願した。入学許可さえくれれば金銭的な支援は僅かでもかまわない、入学金や当座の費用は自分で何とかするし、学費や遠征費はアルバイトをして稼ぐからと、とにかく必死で頼み込んだ。
2時間は押し問答を繰り返しただろう。大勢は明らかに伊藤に不利だった。これ以上頼んでもだめかもしれないと伊藤が気落ちしかけたとき、それまでずっと黙っていた母親が口を開いた。
「みんなが反対するのはもっともだよ。でもね、この子がこんなに真剣に頼み事をしたのは初めてだ。繁雄の気持ちはよく分かった。大丈夫、学費の分は私が稼ぐよ。私がもし倒れたら大学も辞めなくてはいけなくなるけど、それでもいいかい」
63歳の母親の、子を思う愛情にあふれた言葉に、皆ははっと胸を衝(つ)かれた。この母親を前にしてなおも反対を唱えるものはなかった。
伊藤はその夜、ふとんの中でむせび泣いた。拭(ぬぐ)っても拭っても涙があふれた。燃えるような激しいものが小刻みに震える体を駆け巡った。
俺には2年のブランクがあるのだから、ほかの人が4年であげる成果を2年であげる覚悟で練習しよう。
卓球よりもおもしろそうなことには絶対に近づくまい。
海外遠征に1度でいいから行ける選手になろう。
名を上げるまでは絶対に家には戻るまい。
一番のライバルは母親だ。どんなに練習がつらくても母のがんばりにだけは負けまい。
初心を忘れたら坊主頭になる。
6つの決心がひとりでに浮かんできた。卓球日誌を引っ張り出してきてこの決意を書きなぐった。そして震える手で握りしめ、いつまでもただただ見つめていた。俺にはやれる、きっとやってやるんだと自分に言い聞かせて。
西日本選手権大会
その年の西日本選手権大会の直前、伊藤を奮起させる記事が新聞に載った。上位入賞者の予想記事である。星野展弥(全日本チャンピオン)、渋谷五郎(同)、原田武、阿部好幸、国重博...。十数人の名が書き連ねてある中に、伊藤繁雄の名はなかった。全日本軟式3位、広島市長旗優勝といった実績がまるで無視されていたのである。
伊藤は闘志をわき立たせた。三菱レイヨンに伊藤ありということを、今こそ思い知らせてやろうと意気込んだ。そして新聞を引っつかみ、三菱レイヨンの同僚に向かって宣言した。
「これを見てくれ。俺の名前がどこにも出ていない。もう頭にきた。今度の西日本選手権では絶対優勝して見せるから、月曜の朝刊を楽しみにしていてくれよ」
初戦から決勝までの試合内容を、伊藤はよく覚えていない。それまで抱いてきた卓球への執着心、野心、闘志などが興奮状態の中で交じり合って爆発したかのようだった。どんな選手に対しても伊藤は無我夢中で攻めつづけた。そして準々決勝の阿部選手、準決勝の渋谷選手、決勝の星野選手を次々に打ち負かし、チャンピオンの栄冠を手にしたのである。翌日の新聞のスポーツ欄に伊藤の名前が大きく躍ったのはいうまでもない。
実業団時代
伊藤の実業団時代を振り返ってみると、2つのことに気づく。卓球に対するがむしゃらな執着心と、周りの人々の温かさである。
後年の伊藤が述懐するように、ニッタク時代に味わった卓球への飢餓感がなかったら、後に世界チャンピオンとして大成するまで努力しつづけることはなかっただろう。やりたくてもやれない辛酸をなめたからこそ、卓球ができる喜びが何十倍にも感じられ、練習に際して常に高い目的意識を維持することができたのだ。自分の生きた証を何かの形で残したいと願う気持ちは誰にでもあるだろうが、伊藤にとってその何かが卓球であることは、もはや疑いようがなかった。
しかし、伊藤が卓球を本格的にやる道に進めたのは、彼自身の努力のみによるのではない。周囲の人々の温かい思いやりなくしては、到底なし得なかったはずだ。伊藤が卓球をやることを認めて送り出してくれたニッタクの同僚しかり、伊藤の手紙に心を動かされて三菱レイヨンに薦めてくれた先輩や友人しかり、末息子の願いを聞き入れ新聞配達や内職で学費を工面してくれた母親もまたしかりである。伊藤はこうした人々への感謝の気持ちを忘れることなく、すべて上達を目指す努力の原動力へと還元していった。
これから大学でその才能を大きく開花させていくことになる伊藤にとって、この2年間の社会人生活がとてつもない重みを持っているのは確かである。
(2001年7月号掲載)