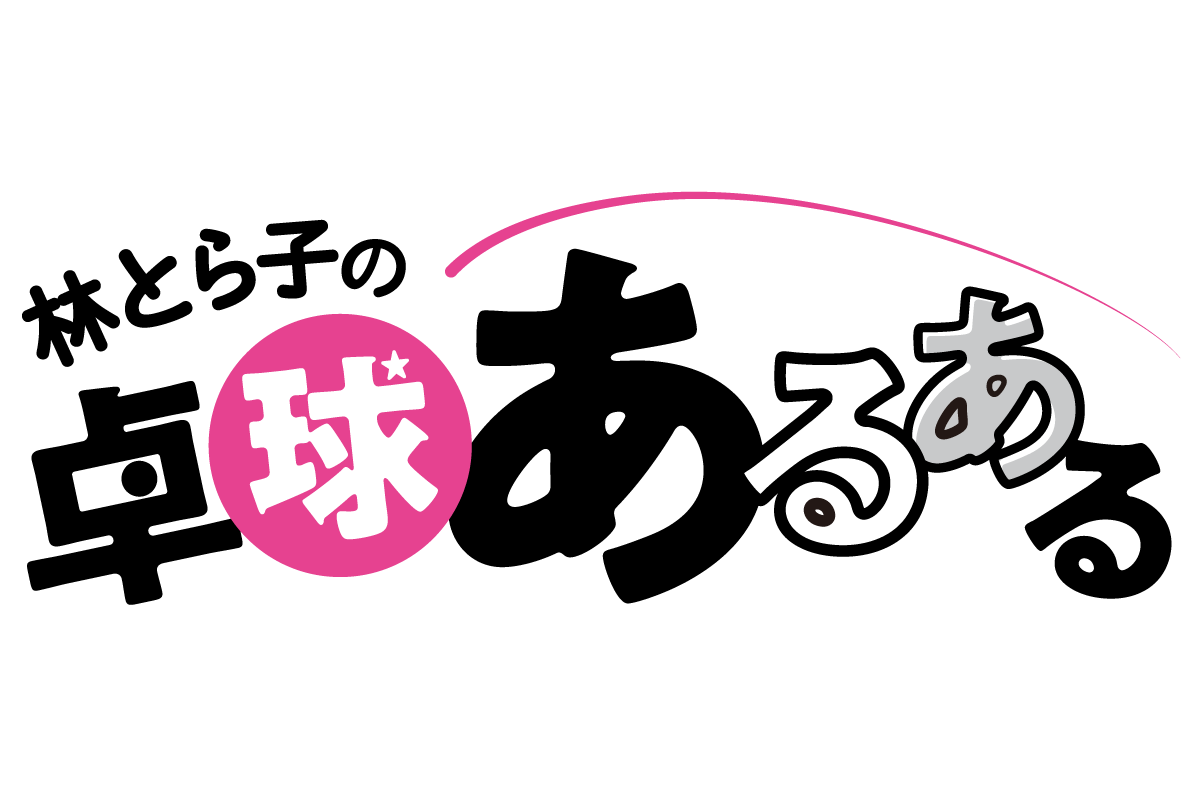五 紅林先生との対談
昭和五十七年十一月二十七日、国際経済研究センター理事長の紅林茂夫先生との
対談が行われ、その記事が「国際経済研究」誌の一、二月号に連載された。
紅林先生のおゆるしをえて掲載させていただくことにした。
「対談」
世界卓球界のトップメーカーバタフライの“タマス”
株式会社タマス 社長 田舛彦介
当センター 理事長 紅林茂夫
アジア競技大会から戻って
紅林 きょうはお忙しいところをありがとうございました。インドのアジア競技大会においでになって、おとといお帰りですか。
田舛 おとといの晩帰ってきました。
紅林 それはお疲れのところ、お帰り早々ご無理をお願いしまして、ありがとうございました。
田舛 いいえ、光栄でございます。
紅林 田舛さんにつきましては私は幸い長年の間、いろいろお話を伺う機会がございまして、知る人ぞ知るというべきすばらしい会社であることを良く存じております。そういう会社をおつくりになったのは社長の人格、人生観、企業観そういったものが普通と違う色々の面を持っておられるからだと考えます。きょうはそういうことも含めまして幅広く御話を願いたいと存じます。今日日本の社会も企業も国際化されつつありますが、日本人のいろいろの欠陥が指摘されてもいます。田舛社長はスポーツを通じて幅広くご活躍ですから外にお出でになって日本人をごらんになって感ずることも多いことと思います。
まず最初に、ちょうどインドからお帰りのところですから、その感想から始めて戴ければと存じます。今回のアジア大会では日本は予定よりかなり成績が悪かったそうですね。
田舛 そうですね。
紅林 なぜそんなに成績が悪かったのかですが、テレビなどかいま見ておりますと、日本が中国の選手の実力を過小評価していたというか、十分わからなかったというようなことを監督が言っていますね。中国というのはよくわからないかもしれませんが、敵を甘く見ていたとすれば問題ですね。一番重要なことは、最近日本はアジアでやるとうぬぼれているところが大いにあるのではないかと思います。
それから、日本の新聞は勝ったところは大きく盛んに書きますが、だめだったところは気をつけて見ないとわからないような小さな記事になっている。こういうことは私はよろしくないと思いますが。
田舛 先生がおっしゃったことに全く同感でございまして、アジア大会-インドのニューデリーで行なわれた大会の話を最初に申し上げますと、私どもは卓球競技のメインスポンサーになったということで招待されてニューデリーに行ってきたわけでありまして、開会式から前半のほうを見て帰ってきたわけです。
現在六分通りの競技が終わった時点で、いま先生がおっしゃったように、種目全体から見れば日本の成績が芳しくない。メダルの数で毎日統計が出ておりますけれども、一位は中国に奪われており、このままでは日本はアジアの第二位ということに甘んじる。初めて第二位に落ちたということになるわけです。
トータル的に申しますと、理由がいろいろございまして、中国の力を十分見抜けなかった。よくわからないという面は若干あるけれども、私どもが長年卓球の面から見てまいって感じることは、非常にハングリーな、十億の国民の大部分がろくろくめしが食えないという状態の中で選ばれてスポーツの選手になるということは非常に名誉であるし、そこでいい成績を上げれば自分の生活の将来の保障と名誉と地位が与えられるという制度がまずいいということ。それから、スポーツを国威宣揚の一つの道具というように国として考えている。ですからスポーツマンにとってやりがいがある状態-これに中国のみならず社会主義国は全部そういう状態になっている。それに対して日本のような場合、自由主義国ではアマチュアリズムというものが、特に日本ではそういうことをわりと厳しく考える国民性があります。
スポーツマン-スポーツ選手の立場でいいますと、最近はやや実業団がスポーツに力を入れるようになっており、そこが救いになっているんですけれども、一部を除いては、プロのスポーツに全力を集中できなくなるという欠陥が自由主義国全体の問題としてある。
それに多くの場合にコーチがプロでないという点が日本の弱点になっているのではないか。ですから、中国の実情をよく知らなかった。インドに行って初めてわかったなんていうんじゃおかしいんですけれども、実態はコーチがプロじゃないですから、世界の強国の内情-どういう選手が生まれつつあるかということを十分に研究しつくされていないと思います。
いまはスポーツの世界においてもプロのたたかいになっておりまして、高いレベルで技術の習練をしなきゃならんし、たたかいですから、大きな大会の場では相手と一対一で取り組んでたたかうということになると、相手を十分に研究しておかないと、いい成績は出ない。
そういうところで日本のスポーツの対世界の訓練というものの程度が進んでいない。中国は進んでいるということではないか。それから、中国がハングリーであって、日本がハングリーでなくなった点では、日本の-これはどのスポーツにおいても-いまの若い人を指導し鍛えていくというのは非常にむずかしい時代になってきたと思います。
二十年ぐらい前は、どのようなスポーツの場合も、そのスポーツに打ち込むことに非常な喜びを感じ、めしを食うのをやめてでもそこへ打ち込んだんですが、いまは若い人に誘惑が多い。これはスポーツマンに限りませんが、集中的に一つのことに若い人が熱中して、深く研究努力をするという点では、いまの日本の世情は誘惑が多過ぎて恵まれていない。
そこら辺がいまの日本のスポーツ界の悩みでもあると思います。
ですから、中国はここ十年間は異常にスポーツに力を入れて、それが国威宣揚の道。それをもって一つの政治活動に組み込まれた活動を中国はやっている。それに対して日本は、特に政府の援助はありませんし、好きな者がやっている。それをよかったときだけ応援するという感じで、負ければみんなソッポを向いてしまうというような、非常に選手にとっては冷たい社会でもあると思います。
スピード、スピン、正確性をこなした名選手
紅林 それは日本の戦後の社会がそうさせているということかと思いますが、いまいわれたように、精神的ハングリーがだんだんなくなってきておりますね。物質的に富めば富むほど、精神的ハングリーがなくなっていくのは人間としての通有性かも知れませんが、悪い通有性は出ないように心掛けることが必要ですね。戦後の教育-家庭・学校の教育-があまりにも精神性を失っていることに問題があるのではないでしょうか。人間を造らないとガンバル精神は出て来ませんね。
田舛 ありますですね。これはスポーツのみならず、いま申したように、あらゆる学術、芸術の世界でもハングリーでなくなったという日本の行き悩みといいますか、壁があると思います。ヨーロッパの人ではっきりそういうことをいう人があって、日本はあれだけ豊かになったのだから、弱くなるのはあたりまえだなんてことをいう人もおりますね。
紅林 アメリカなんか必ずしも弱くはないですからね。
田舛 はい。ですから、家庭教育であれ、学校教育であれ、人間一人ひとりがちょっと甘いところがあるんじゃないか。アメリカ人とかヨーロッパ人は、学校とかチームということよりも、一人ひとりがしっかりしている者が多い。スポーツをやるにせよ、ここで自分の能力の限界を試すのだ、そのためには自分みずからがいろいろ研究し努力をしていくということです。
日本人の場合は、そういう人もありますけれど、多くは先生のいいなりというか、こういわれるからこうやっているというところが多い。
紅林 自分で発明して努力する精神が欠けている。その点、私は社の三十年史をちょうだいしたときに拝見したのですが、また実は夕べ改めてもう一度拝見し直したのです。そして改めて感心しました。卓球には三つの問題があるが誰も三つをコナし得た選手は内外ともにないそうですね。球を打った時のスピード、変化、それからひねりというのですか…
田舛 正確性ですね。スピードとスピンと正確性。
紅林 スピンというのは、糸をつむぐという字ですが回転のことでしょう。
田舛 そうです。ボールの回転です。
紅林 この三つを兼ね備えた選手はいない。誰でもこの三つのうちどれかが得意というに止まる。しかし田舛社長はこの三つを完全にコナされたそうですね。
田舛 そうですね。どこかに特徴がある。
紅林 私は剣道を子供のときから父親にやらされ、大学出るまで剣道一筋でやってきたのですが、剣道でもやっぱり面が得意とか、胴が得意とか、いくらかそれはあります。相手があって変化がはやい点では剣道も卓球も同じですが、相手の変化に対して瞬間的にこちらが変化しなければならない。その時にどう変化するかに一つのパターンが人によってあります。それが得意の手ということになりましょうが、田舛さんは万能で、三つの変化球をすべてこなされた不出世の選手だったということで大変な名人だったのだな、と改めて感心しました。それがすべて天性備わっていたかというと、何事もそうはいかないので、やっぱり努力をされたのだと思います。それだけの三つの動きある球の打ち方をマスターする努力は大変なことで、誰にもできない筈です。だからそういう人はほかにはいない。世界的に見てもいないと三十年史に書いてあります。
独力で始めた運動具店
田舛 ちょっとほめ過ぎです。私は正確性と変化球を追求した選手でした。実は私は戦前は山口県で古いお菓子の製造業の息子の三代目でそれをやっていたんですが、戦争の広島原爆で生き残って、帰ってきた以後、家業を継ぐのがいやで、何か新しいことをやりたいというので運動具屋の道に入ったんですが、当時卓球の選手でもあったわけで、自分のラケットに張るゴムはイギリス製を進駐軍に頼んで、それを張り合わせてというか、ラケットに張って使っていた。それで日本で二番とか三番の成績であったんですが、こんなことではだめだ。自分でラケットとかラバーとか、もっといいものをつくらなければ、将来的に日本はだめだという考えになって、卓球ラケットとラバー製造業に入っていったというわけですけど、自分が選手であったということが、そういう用具の研究開発に役立ったということはいえると思います。
商売を始めるに当たっては、スポーツのある問屋さんから「スポーツの選手が運動具店をやって成功したためしはない。それでもあなたはやりますか」と最初の段階でいわれて、そのことが励みというか、ハードルになりました。それはたまたま私の親父がしっかり手綱を握ってくれていたからですけども、今日まで順調にこれました。
最初の段階では商品開発は自分自身でやったんですけれども、十年間以後は新しい優秀な人を入れて、商品開発とか宣伝販売、製造に新しい能力-知恵を入れてきた。それがうまくリレーされてきたということです。
紅林 しかしいまお話しのように、もともと家業はお菓子屋さんということですから、大転換ですね。お父さんも最初は、田舛社長のおやりになってくことに懐疑を持っておられたようですね。それが一転して認められてからは一家を挙げて東京に出てこられた。そういう決意、決断力、実行力、これはまた並々ならぬことです。だから周囲がみんなびっくりしたということですが、経営者として一家をあげて新しい企業経営に向って背水の陣を敷かれたわけですね。
田舛 まあ、背水の陣という点は全くそうでした。常に全力投球。最初の段階で銀行からの借金も、借りるだけ借りて、後で決算のときにつじつまを合わせるように進んできたわけです。
紅林 しかし、貧乏で困ったというおたくではなくて、裕福であられた。だがお父さんは、やるなら独力でやれ、一切資金援助はしない。こういわれ、それをやり遂げられた。これもまた大したことだと思います。どうしても親に金があれば頼りたいし、親も出してやろうかとも思うでしょう。やっぱり成功者はスタートから違うものだと思いました。
田舛 さっきのスポーツもそうですが、その点は親父が、私が「運動具屋をやりたい」といったときに「よかろう」「じゃ、少し資本を出してくれ」「それはだめだ。資本がなければ商売できないというのなら、やめろ」-そういう非常に、何だかわからんことをいった。それに腹が立ってというか、自分の身ぐるみを脱いで、それを米にかえて、その米を仕入れ先に持っていく。米とか砂糖とか、あるだけのものを仕入れにぶつけていったわけです。
戦後のスタートでは、仕入れ先との“いい関係”というのが必要であったわけですから、自分が裸になって、持ち物すべてを売り払って、何千円かの金でスタートして、グルグル自分のからだで回転をさせていくというぐあいでした。
紅林 しかしお父さんを初代の社長に据えられた。
田舛 そうです。順調に行き始めたから、親父が「会社にして」ということで、したわけです。
ブランド「バタフライ」の由来
紅林 田舛社長のモットー、成功の根底にあるものは、「世の中に対する感謝しかない」と三十年史に書いておられます。私は全くそこに今日の成功があると思います。
それからもう一つは、会社内の社員に対する感謝。こういう感謝の念を常に頭で感謝しているだけではなく実践に移してこられたことが、社運を隆盛に赴かせた根本だと思います。それと関連してタマスさんのところの商品ブランドは蝶ですね。ブランドを、なぜ蝶にされたのか、最初は私よくわからなかったのですが、三十年史を拝見したとき、なるほどと思いました。三十年史に書いてあるところでは、選手を花にたとえ、花に仕える蝶のようにラケットはあるべきだ。そしてそのラケットのメーカーは選手のために誠実に働こうという願いをこめて蝶(バタフライ)というマークをつくられたということですね。しかし、蝶の図はご自分でお描きになったのですね。
田舛 はい、そうです。
紅林 大したものです。このトレードマークの由来を伺いましても、田舛社長の人格、経営方針がはっきりあらわれていると思います。
田舛 ありがとうございます。いまごろになってもよくアメリカ人やヨーロッパ人から何でバタフライなのかということを聞かれます。それでその話をすることになるんですけれども、欧米の人から見ると、日本製品でバタフライだから、マダム・バタフライなのか。でもどうしてそれがスポーツの用具に関係するのかという疑問をまず持たれる。それでその話をいたします。私どもが戦後こういう用具の製造に入って、一つの製品をつくり出して、何をマークにつけようかというときに、まあ世間一般ではライオンだのタイガーだの、世界だの宇宙だの、そういう大きなものをつけたがるときでありましたので、うんと小さいもので、平和的で世界に愛されるアイドルになるようなものを考えよう。しかもそれは昆虫の中から、じゃ、蝶が一番である。われわれメーカーの精神としても蝶はちょうどいい。選手の美しい花を育てるために働くのだ、と最初の段階から、すっきりしたあれをしたということです。そしていま私が申しましたことを英文にしましてね。最初の段階の三十年前に英文と日本文で発表したわけです。
少数精鋭主義で石油危機をのりこえる
紅林 本当にいいトレードマークですね。ところでヨーロッパでトレードマークを悪用された問題がありますね。これはまた後でお伺いすることにいたしまして、石油ショックで経営上の問題が発生した時の対処がまたまことに立派な模範的なものだったと思います。石油危機に際して一人二役-少数精鋭主義が必要だと強調されて、率先断行されたのですが、それが今日の社の基礎を固めるのに役に立った。全くそうだったと思うのですが、石油ショックに対してそのようにいち早く立ち向かったことは、石油ショックが何であるかを十分に理解されたからだと思います。と同時に、みんなが社長の方針によくついてきてくれたから実を結んだのですが、それは要するに社長の人柄に最後は帰することだったと思います。
田舛 石油ショックというのが昭和四十八年から四十九年という時期なんですけれども、ご承知のようにその直前は田中政権時代の高度成長、列島改造という、勢いのいい政策が強行された。で四十七年、四十八年というところは物価がどんどん上がる。われわれのほうでは材料も上がる。何となく世の中は景気に浮かれるような状態がありました。そのとき私どもも身を誤ったわけです。スポーツも各スポーツとも非常に勢いがよかった時代でありますので、思い切った増産と販売促進をやった。それが行き過ぎというか、失敗だった。やはりわれわれ-どんなスポーツもですが-いいときも悪いときもありますが、卓球という世界ですから、急激に卓球をやる人がふえたわけでもないのに、急に販売促進をいろいろな手を尽くしてやった。それがやり過ぎであった。そのころは、受ける側も、材料が上がる、商品も値上がりするわけですから、こちらが持ち込めば、いくらでも流通段階で、買ってくれた。問屋さん、小売屋さんのほうへちょっとした景品つき販売のようなことをやってどんどん売れた。そしてオイルショック。その後、世の中は非常に引き締まってきて、銀行を金を引き締める。金融が引き締まって、問屋さん、小売屋さんは、その段階になると、商品を腹いっぱい持って食べ過ぎていまして、新しい仕入れ意欲がないという時代が一年続きました。
その間をしのぐのが大変であった。その一年間というものをどのような気持で、どのような対策をとったかということが、いまから考えればよかったんですが、われわれの卓球用具-バタフライ卓球用品がトップメーカーであることには間違いないんであって、いま売れないから、これでだめだというんじゃない。一年間ぐらい、流通在庫になっている商品がはけていくまではじっとがまんするしかない。
でこの間は売り上げが前年比何割も落ち込んだ。落ち込んで銀行には借金がたまる。返せないということが続いた。銀行から見ると、どうしたんだ、ということになるわけです。そこを一年間ほど銀行にお願いした。販売はここ一年間はやらない。そして霧が晴れるのを待つという姿勢をわれわれはとります。もちろんメーカーとしての商品開発、努力はやるけれども販売促進というものは一年間やらないことにする。われわれは決して商品の競争で負けているわけではなくて、流通在庫が多過ぎて若干の失敗があった-ということで、まず金融関係にお願いをして、社内的には、適正規模というものを見直さなければいけないということで、十項目の反省のポイントを決めて、それを各職場に掲示して、一人二役-少数精鋭ということからやっていったわけです。
当時人員が、正社員が百四十六名と、ちょっとふくれ上がったところでしたので、それを最終的に二割減ぐらいに抑えないと、われわれの商売の適正規模ということではないということで、三年がかりで、新規採用ストップして、自然減を待って人員を二割ぐらい減そう。それから一年間はトップの五、六人の給料は何割か下げて対処しようということで、社長以下トップの五人は全部同じ給料にしました。一般の社員には及ぼさないで、とにかく辛抱しようと。で工場のほうは一ヵ月レイオフをしました。
そういう社内の引き締めというか、一つ先を見て、こういう方針で、こういうふうにいく。だからみんな辛抱してやってくれ。決して先行きでわれわれが負けているのではない。高度成長に乗り過ぎた点がある-これは多くの企業がそうだったんですけれども、その対応がはやかったんですね。ですから後で金融関係から、非常に適切で、思い切った決断であった、とほめられました。
まあ、大筋を申しまして適正規模-どの商売でもそこをつかむことが一つのコツでもあるし、非常に大事なポイントじゃないかと思います。
紅林 はやくおやりになったのは、先見の明をお持ちになったからですが、それは石油危機を本質的によくつかまれたということです。
田舛 いえいえ、仕方なくやったんですけれども。
「小さい井戸を深く掘る」
紅林 「企業にも人生がある。企業もうぬぼれたとき、落日の運命をたどる」と書いていらっしゃいます。全くそうですね。そしてモットー、信条として「小さい井戸を深く掘ること」とおっしゃっています。これはほんとにいい言葉です。
田舛 ほかに能力がないものですから、そういう言葉もいえるんじゃないかと思うんですけれども、たいがいの企業がオイルショック前後に多角経営を-われわれも卓球だけではだめなんじゃないかという心配を-いまでも持つんですけど-常に持っていました。
紅林 それは確かにそうでした。こっちがだめならあっちだとみんなよく考えたものです。
田舛 あるときは銀行さんからすすめられて、土地を買えとか、ゴルフ場をやったらどうかとかいろいろいわれましたけれども、とにかく自身がないものですから、この道だけならば何とか人に負けないでやっていける。目が見えるという点で、そういう標語を自分からつくって努力をしていったわけですけど、今日それは間違いではなかったと思います。
それと、われわれはもとが卓球の選手であって、卓球を愛するというか、卓球を守らなきゃならん。ほかのスポーツに卓球が負けてはならんという使命感が、私のみならず、社員にあるわけです。社内に世界チャンピオンであった人が現在二人おりますし、指導者であった人はたくさんおりますので卓球愛という点で社内の共通認識ができるわけです。そのためにはみずから頑張って、いい会社にしていかなくちゃならん。そこら辺で社員福利と社会奉仕というものを常に二つ掲げて、会社として努力をするという精神があるわけです。
私にもいいところがあるとすれば、自分が学力とか能力がないものですから、人を大事にする精神が自然にあるんじゃないかと思うんです。卓球というものが、どうかするとスポーツの中でマイナースポーツ的に見られるのがしゃくにさわってというか、何とか卓球を立派なスポーツにつくり上げていくには、われわれメーカーの立場でも努力しなきゃいけない。それは卓球協会が努力される問題ですけれども、メーカーの役割というものも大きいんじゃないかという考え方で、いい会社にならなければいけない、強い会社にならなければいけないということを社内全体のスローガンとしてやってきているわけです。
紅林 「企業は人なり」ということは昔からいわれることですが、これも、言うことは誰でも言いますが、社内で徹底的に人本位、人材本位でやることはむずかしい。だからこそよくなる企業と、だめになる企業に分かれてくるのでしょうが。黒田如水が秀吉に「この世の中で一番多いものは何であるか」と聞かれたときに「それは人でございます」と答えた。次に秀吉が「それではこの世の中で一番少ないものは何であるか」と聞かれたとき如水は「それも人でございます」と答えたと言いますが、秀吉は如水の言うようにやったとは言えません。ワンマンはとかく自分の判断を最善としますから。その点田舛社長は人の教育を実際にやっておられる。
田舛 私ども自身の経験からしても、社員をよくするのも、悪くするのも、社長の仕事じゃないかと思います。
紅林 経営者というものはそうあるべきだと思います。下をリードしていくと同時に、下から慕われる。この社長なら、と思わせることがなければ企業は成り立たない。ところが、ヨーロッパでは労働組合が、マルクス、エンゲルスの考え方そのものに従ってできている。マルクスが生まれたのは一八一八年です。だから私はいつも学生に、マルクスの生まれてきたのはイヤイヤネンである。そう覚えなさい。それから死んだのは一八八三年です。だからイヤヤミネンで死んだのです。物を覚えるにはこういうふうにして覚えるんだ、といっているわけです。そうすれば一生忘れない。
でマルクスが出てきて活躍したのは一八五〇年前後ということになりますが、これはヨーロッパにおいて、資本主義経済が最悪の状態になったときなのです。ですからマルクスの前にすでに空想的社会主義者といわれる、ユートピアを書いたトーマス・モアや実際に自分の理想に従って経営したロバート・オーエンなどが出てくる。あるいはラスキンのように経済は愛情の学問でなければならないとした人も出た時代であった。この世の中こう悪くちゃいかんじゃないかということだったわけです。
古典派経済学のほうでも流石に反省していたわけで、ジョン・スチュアート・ミルは、経済学の中に社会性を取り入れねばならない、と主張した。しかし実際にはなかなか社会がよくならなかった。ですから資本家と労働者の対立が非常に強かった。それでマルクスは剰余価値説を立てて、資本家が労働者を搾取する理論を展開したわけです。労働者は絶対に資本家と対立している。そして、資本家は搾取する、という対立の見方で組合を結成することになる。だから西欧の労働組合は経営者に対して対立抗争の関係としか考えておらず、現在でもそうなのです。
戦後日本でも、組合は当然造るべきだということになって出来たわけですから対立意識は最初はずいぶん強かった。最近、世界同時不況になって、日本だけわりあいうまくいっているじゃないか。それは経営がうまくいっているからだ。経営がうまくいっている中身は、経営者と労働組合との間柄が欧米と違うからなのだ。だから日本的労働慣行は見直さるべきだということになって来ました。欧米では企業は経営者のもので労働者はただ使われているだけだと今でもそう考えているのですが、日本では企業は経営者と労働者のものだと考えられています。このことは例えば不況になったときアメリカでは忽ち雇用を切るが、株主に対する配当は行う。しかし日本では雇用は切らず配当の方を削ります。この差が大切です。
田舛社長は企業の人格というものをお考えになり、企業は人なりとし、経営者、組合員一体になって経営して来られたわけです。ところがそれにもかかわらず組合との間に一時ごたごたがあったということですが、これはどういうことで起こったものなのですか。
組合の結成と企業の団結
田舛 これも私どもの会社の成長過程で油断があったと思うんです。オイルショックの後、いま申しましたように、一つの引き締め政策を社内的にもトップみずからやって、立て直さなきゃならんという時代が数年続いて、新規採用ストップ、そして全般に引き締め政策をとったわけです。そのこと自体どうということはないと思いますが。社内に一人うぬぼれ屋さんがいてというか、もう少し自分の地位を上げてほしい。自分はもっと能力があると思い込む人があり、それが外の労働組合上部といいますか、そこにかけ込んだというか何というか、組合を結成することによって自分がリーダーとなってリーダーシップをとろうという。そういう考えになるということは考えられないことなんですけれども、事実そういうことになりました。
組合そのものがあることは悪いとはいえないわけですから、それはそれで、健全な組合であればけっこうなんですが、非常に戦闘的なスタートが切られた。結局社内の人事にまで入り込むような攻撃的な組合になってきたということで、これは絶対に許せない。われわれは運命共同体という精神がもともとあるんであって、その説明を私がしたんですけれども、なかなか団体交渉がうまくいかない。ということは、交渉が始まると、外から四人ぐらい団体交渉に人が入ってきて、しゃべるのはその四人がしゃべる。うちの社員と私が話ができないという、とても考えられないような事態が起こってしまった。ですから組合としてもまずい形で結成をされ、そしてまずい形で指導がなされた。ちょっと意外な、組合の側から見ても、やり方が失敗であったといっているようです。タマスという会社は、社長が人間性のやわらかい人間だし、幹部がしっかりしていないから、ここで強くパーッといけば、いい組合ができるというふうに判断をした。それでごたついたわけです。
紅林 それは昭和何年頃ですか。
田舛 昭和五十二年五月にできて、最初一年間ごたついたんですけども、直ちに別の組織ができまして-第二組合ではないんですが、社長協議会と称する団体ができて、こんなばかなことをやっていたんじゃ社がだめになるという、社員の中の有志が立ち上がり、それが八割方押さえて、いまだに組合はあるんですけれども、おとない状態になって残っています。
紅林 すると前の残りの組合はまだあるのですね。
田舛 あるのはあるんです。ですけれども非常におとなしくなっている。ただまあ、中心人物はやめていきました。やめていきまして、活動の能力もない、外からは解散させないように守るような行動は当然あります。ですけれども、激しい活動は一切なしというので、ここ数年続いております。ただ、逆説的には、そういうものができたことによって非常によかったんじゃないかと思っています。
オイルショック以後また、昭和五十年から急激に社の業績がよくなって、これで八年連続増収増益です。先月決算でした。ごくわずかですが、増収増益という状態でした。
世間が悪いときに増収増益という、非常にいい状態が続けられているのは、一つは社内にそういう対立したエネルギーがあって、私も緊張するし、幹部も緊張する。社内も、二つありますから、双方とも緊張している。
紅林 結局、そういうことになって本当のよさがわかったということなのでしょうね。
田舛 はい。やっぱり自分達がやったことがまずかったことはわかっておりますし、全社的に何が大事かということをよりよく考えるようになったことです。
紅林 それはよかったですね。
田舛 結果的によかったと思います。ちょっと悩みましたけど。
紅林 それはそうでしょうね。すると現在、組合はあるにはあるが実際は無いに等しい。そして企業としては団結は固くなっている、ということですね。
田舛 そうです。
紅林 ですけど第二組合ができたわけではないから、経営上の話し合いをする社員の相手組織はどういうことになっているのですか。
田舛 二つになっています。春の給与改定の時期、それから、順調なときはボーナスが三回出るわけですけれども、そのつど社員と会社という立場で話し合いをします。私どもは、こっちが会社で、こっちが労働者という気持はなかったんですが、やっぱりそういうものができますと、労働者対資本家という感じになって…。それで、一応団体交渉的なことは、年に何回かやりますが、それはやっぱり二つあるわけです、相手が。
紅林 そういう状態になった会社はよくありますね。
陰の功労者 田舛夫人
田舛 いわゆる第二組合的なものがあるのは多いですよね、かなり。
紅林 創価大学もそうです。共産主義の組合にしようという動きを当然共産党はとりますから、ですからやっぱり二つあるのです。ですけど今いまのお話のように、共産主義的な組合のほうは、全く発言力がなくなってしまった。でもまあ、二つあるのです。
田舛 そうでしょうね。
紅林 ところで中小企業の場合に一番重要なことは、三十年史にもお書きになっていらっしゃいますが、奥様の役割でしょう。というのは、大企業と違って中小企業の経営は家族ぐるみだからです。そして、順調にここまでこられたといわれても、幾つかの山、谷があったでしょうからそのときに奥さまは常に苦労をされ、また全面的に協力をされたということなのですが、ほんとに田舛社長はいい奥様に恵まれましたね。写真を拝見しても大変美人でいらっしゃるし。でもほんとに大変だったでしょう。現在はもうそういう苦労はあまりされないでも済んでいらっしゃるわけでしょうが。
田舛 結婚がわりあいはやく、私が二十二歳の終わりぐらいで昭和十八年のことです。それから兵隊に行って、原爆で死ぬところが生き残った。戻ってきてから新しい商売をやったわけですが、新しい商売というのは、私と家内で始めたようなものです。
運動具屋という商売は、野球の選手や監督が出入りする。テニスの人が出入りする。いろいろなスポーツの監督や選手を相手にして朝早くから夜遅くまで、夜は店をテニスや野球の事務所にしてサービスするということが戦後十年間ありました。ですから戦後十年間は、私も背広一着つくらない。家内も持っているものをむしろ売るぐらいの状態で、終日年中無休で働きました。
紅林 三十年史に「十年間着物を買ってくれといわれなかった」と書いてあります。
田舛 十年一区切りといいますけれども、ここから楽になったという意識はありません。十年ごとというふうになかなかいくものではない。ともあれそういうふうで、たとえばテニスのラケットのガットを張るなんていうのは家内の仕事でして、一時間に四本ぐらい仕上げる。それは大体スピードがいいほうです。
たとえばのことですが、そういうことやら、お茶の接待その他家族や従業員の世話ということで、確かにそういう意味では悪い亭主であったわけですが、私も同じように働くわけですから。だけどまあ、仕事のスタートが順調にできた功労者の一人だと思います。
紅林 功労者ですよ、ほんとに。
田舛 仕事というのは、お客様との信頼関係の積み重ねでいくものであって…。
紅林 松下幸之助も奥さんと二人で、昭和の初年大恐慌のころに長屋を借りて、そこでソケットをつくり始めたというのは有名な話ですが、それに類することですね。
でも二十二歳で結婚されたときには、田舛社長は、お菓子屋さんをやめて、卓球の仕事のほうに入ってらっしゃったのですか。
田舛 二十二歳のころは戦争中でありまして、実は十八年のその時点では戦争も激しくなって、菓子屋という商売は成り立たなくなりまして、有名無実であったわけです。私は外へ働きに行かなければならないので-実は国民勤労訓練所というものが日本に二つできて、東部国民勤労訓練所は小平にでき、西部は奈良にできたわけです。そこで私は訓練を受けたんですが、どういうわけか、指導員に残されて、指導員をやっていた。そのときに結婚したわけです。
紅林 そのときに奥様とめぐり会われた。
田舛 めぐり会ったんじゃなくて、両方の親が同郷でして、家内は東京生まれですが、親が山口県なんです。で見合いをしろということになり東京に…。私は「まだはやい」といったんですが、親父が「とにかく会え」といことで会ったんです。変な話ですが二日目に「どうする」という。「どうするってまだ…」「はやく決めたほうがいい」。戦争もだんだん激しくなってきていますし、「じゃ向こうがいいといえばいいよ」というようなぐあいで。そうした向こうもそういったらしくて、それじゃあ結婚式というわけです(笑)。こういうのは珍しいと思うんです。
紅林 戦時中はそういうこともありましたね。
田舛 それでとにかく、式場とか、そんなものはないから、皇居の前に行って、両方の親が立ち会って…。
紅林 それは何年ですか。
田舛 昭和十八年の三月です。皇居の二重橋の前で誓約式をしたんです。その足ですぐ私は奈良へ帰って、一ヵ月後にやってきたわけです。そのころは、お国のための仕事ということで精いっぱいで一生懸命やりました。
軍隊時代のエピソード
紅林 十八年といえば大変な時期でした。
訓練所でいろいろな提案をされた、と書いてありますけれども…。
田舛 そういう点では多少私にいいところがあった。西部国民勤労訓練所の場合も、それから兵隊に行って二等兵からやっている間においても、いろいろな提案を出しまして、それを上司が受け入れてくれた。
たとえば広島の私が入ったところは、暗号を教える部隊でありまして、暗号教育隊。もっと正確にいうと、広島は船舶司令部というのがありまして、船舶司令部暗号教育隊。要するに船舶隊は海軍みたいにアッツ島からラバウルまで散らばっていまして、その間の暗号連絡をやっていたわけです。私が暗号兵になる。それで教育を受けて、ラバウルかどこかにとばされるところを、卒業というか、二ヵ月の教育を受けた最後の日に、感想文を書けというので、感想文を書いて出した。いまでも覚えていますが、三つほどの問題を指摘して、書いて出したわけです。そうしたらそれを見て指導員に残されたんでしょう。
どういうことをいったかというと、暗号の教育のやり方がよくない、ということ。これは、二百人ぐらい入ってきて、それを六つの班に分けて教育して、二ヵ月後に卒業していくんですが、頭のいい人とよくない人も入ってくる。大体昔の旧制中学以上の学力を持った人が入ってくることになっていまして、ぼんくらはいないんですけれども、物事を覚えるのがはやいのとおそいのとあります。ですから、全体のうち一つの班は、少しおそい者を教育する特別教育班をつくるべきだ。そうしないと、わからない者は途中でついていけなくなって、能力のない兵隊が出て行くことになる。だから特別教育班をつくるべきである。そしてその班は夜おそくなっても教育をするべきである。ということが一つと、それから暗号兵体操をつくれということです。
暗号兵というのは頭ばかり使って、あまりからだは使いませんから、結核になりやすいし、実際になる人が多かった。そういう暗号兵-うつむいて仕事ばかりする人の体操をつくって、やらせるべきである。
紅林 なるほど、それは特別の体操を考えられたわけですか。
田舛 そうなんです。私は体操の研究を少しやっていたので、こんな体操をやっていたんじゃだめだと思っていたわけです。
それから第三点は、内務班の古い兵隊に悪いのがいる。ここを気をつけなさい。内務班のことを将校は知らないだろう、ということです。
いいにくいことですが、そういうことを書いた。そうしたら翌日呼び出されて「おまえは暗号兵体操をつくれるか」「はい」「よし、では、教育要員として残れ」とういことになったわけです。
体操の目的は四つありまして、からだを柔軟にする-骨はかたいほど丈夫なんですが、筋肉はやわらかいほど丈夫なんで、曲げ伸ばしをやる柔軟体操。それから矯正-からだのひずみを直す。こういうふうに、(からだが横にねじれている)なっている人はこう直す(真っすぐ)。こうなる(前かがみ)人はこう矯正(姿勢よく)するという意味の矯正体操。それからからだを器用にする器用体操と、疲労回復の体操と、四つの目的があるわけです。
この四つを組み合わせた一つの体操ができる。職場によっては組み合わせ方をかえるべきなんです。スポーツ選手の体操と、一般の年寄りがやるのと同じじゃいけないわけです。そういうような組み合わせの原則を少し勉強していたものですから、論理的には説明できる。指導員になりましたから、自分でつくりまして、翌日から、指導せい、ということになり、全部隊の将校や兵隊を集めて毎朝指導しました。
紅林 やり方がかなり違うのですか。
田舛 疲労回復体操的なものを中心においてということですから、少しゆっくりした体操です。
紅林 たとえば太極拳なんてゆっくりしていますね。ああいうのがいいのですか。
田舛 そうですね。太極拳は私よく知らないんです。
紅林 締めるべきところはグーッと締める。
田舛 そのようですね。ゆっくりというのも案外力が要るんです。
一つだけ申しますと、背伸びをしますね。グーッと背伸びをして、からだを伸ばして後にそる。そしてあくびをする。普通一般の人間は、これで体操の目的の半分が達成できるわけです。昔の話では、日本人の年寄りは腰が曲がっている人が多かった。これは針仕事とか、特に女の人が多かった。仕事というのはたいがい前かがみなんです。そればっかりやっていて、背伸びを一回もやらないとそうなっちゃうんです。
ところがドイツ人はその点常識が発達していて、背伸びをよくやる習慣が昔からあるそうです。だからドイツ人には曲がったのはいないといわれております。結局体操の大原則で原点は、背伸びから始まっている。背伸びを一日三回やれば、非常にその人のためにいいわけです。
コーデュバイ社との商標係争起こる
紅林 そうですか、それはいいことを伺いました。非常に創意工夫をおやりになることが現在のタマスのある基本的な原因でしょう。
さて、一般の経営者にも参考になることだと思いますので、簡単にコーデュバイ事件についてお話ししていただきたい。
田舛 われわれは輸出ということを考えたのが一九五二年-昭和二十七年です。で実際に輸出が始まりました。卓球の場合、一九五二年の世界選手権がインドのボンベイで行なわれました。そのとき日本が初参加で七種目のうち四種目優勝した。これは、われわれ自身も驚いたんですけど、日本の攻撃的な卓球に、向こうもびっくりした。
紅林 あまり攻撃的なことはやっていなかったのですか。
田舛 卓球というのは守備が基本です。
紅林 ついでですけど、卓球というものはいつごろから人間が始めたものですか。
田舛 近代卓球というのは、セルロイドのボールになってからと考えられています。それは約百年前です。イギリスの貴族社会の遊びとして生まれたということになっています。
紅林 そうですか。百年前にああいうピンポン玉というものを考えたわけですね。
田舛 ええ。セルロイドのボールを誰が発明したかということは、二つの説がありまして、それはアメリカだ、というのと、イギリスだ、というのがあって、ちょっとはっきりしない。私はそれをいま研究中で、将来卓球の博物館をつくろうということで、集めているところです。
紅林 その前は何でやっていたのですか。
田舛 コルクの玉です。今度私がインドへ行った目的の一つは、その資料をさがすことを頼むこともあったんですが、百五十年前にインドで始まったという説があるわけです。それはコルクのボールです。イギリスの海軍か陸軍か知りませんが、インドに駐在していた兵隊が遊んだ。歴史上そういう説があります。その中で、ハンガリーのある人が書いた本には、二千年前に日本で始まった、とあります。だけどそれはお公家さんの羽根突きのことだろうと思うんです。
紅林 だって二千年前といったら、天照大神…(笑)。
田舛 ハンガリーというのは東洋系の人種でもあるので、そういう懐古趣味というか、かわった考え方があるんでしょうね。要するによくわからないわけです。よくわからないから、ずっとさかのぼれば、原点はそこじゃないかという人もあります。
ともあれそういうことで昭和二十七年から事実上輸出-日本が勝ったんで、日本が勝った特殊な用具、スポンジとか、スポンジとゴムをはり合わせたものが活躍したわけですから、そういう日本製品に対する外国の注文がパーッと出てきた。そこでヨーロッパのほうにも翌年ぐらいから-これは必ずしもタマス・カンパニーだけではなくて、ほかの同業者もですが、当社が一番多く注文を受けてヨーロッパでも一九五三年ぐらいから使われ始めたわけです。その時代は、向こうの一流選手からの注文で、自分が使いたいんだということで送っておった。それが一九五五年ぐらいから、業者の注文になってあらわれてきた。
そういう経過があって、オランダのコーデュバイという会社がそこに目をつけたというか、うちとの取引の申し込みがあって取引を始めていた。ところがそれが、ヨーロッパ全体の権利をくれという要求が出てきて、それを断わった。断わったら勝手にブランドを登録して「あなたはもう私以外に売ることはできない。全部権利をくれ」「それはできない」「でもヨーロッパ中の商標権の登録は済んだ。スイスの本部で調べてくれ」という手紙がきた。えらいショックでして、それに全面屈服するか、たたかうか、わが社の大問題です。
それで私も外務省とか通産省に何度も行くし、特に久保専務が毎日のように、どうしたらいいか、お願いに行った。どうしたらいいかっていったって方法がない。どうもらちがあかないので、朝日新聞にいったところが「今日の問題」というコラムでうちのことを取り上げてくれたわけです。そうしたらすぐ翌日、NHKと共同通信と日本経済新聞が取材にきて、当時大きな問題でしたから、全面的に取り上げてくれたんです。
それは四十年です。四十年の春、問題が大きくなって、たまたま四十年の四月に、世界選手権大会がユーゴスラビアのリュブリアナというところでありましたので、とにかく社長が行って、世界各国の選手や役員にアピールすべきである。そういうことで私が、英文の文章を書いて、こういう問題が起きて、こういうふうに困っている。しかしバタフライはわが日本のタマス・カンパニーのものであることは、皆さんご承知のとおりだ。そういうアピール文章を添えて、お土産をつけて各国に配ったわけです。
コーデュバイ社との裁判に踏みきる
田舛 それが終わり、その足ですぐドイツに行きまして、日本大使館に行って通訳を世話してもらい、ドイツの弁護士、弁理士に会って、当方のドイツ代理人に定めてあったドクター・シモンという人と一緒に、裁判をやるべきか、何か和解の方法はないか、話しをしたわけです。ついでに申しますと、最初の会合で弁護士さん、弁理士さん、特に弁護士さんのいう言葉は「裁判をやって勝てるか勝てないかわかりません。あなたの考えをまず聞きたい」といことで、私のほうは「できれば裁判はやりたくない。百万円か二百万円払って相手と、和解する方法があれば、そのほうがいい。コーデュバイに登録したものをおろしてもらいたい。ベネルクス三国だけの代理権を与えるということでおろしてくれないか。百万か二百万払う用意はあるということをいってくれ」といったら「やってみましょう。しかしいやだといったらどうしますか」「そうだったら、バタフライというブランドは捨てて、タマスというブランドにかえてやり直します」といったら、弁護士さんのいった言葉は「田舛さん、あなた個人の財産がどのくらいあるかは知らないが、バタフライのブランドのほうが大きいんじゃないか」というわけです。
紅林 それほどバタフライは世界的に有名だったわけですね。
田舛 そうですね。だから捨てるべきじゃないということをいうわけです。捨てるべきじゃないといっても、裁判で負けたら、こちらが賠償金を一千万円ぐらいとられるということが起こり得る。ですからこちらは非常にそこは危機感があったわけです。だけども「やるか」という気になって「やりましょう。お願いします」とういことになったわけです。それで「勝つ見込みはあるか」といったら「われわれは努力する。しかし絶対に勝てるとはいい切れない。ただ、この際助言しておきたいことがある。この問題があるいはここであなたの勝ちになって決着がついたとしても、この種の問題は将来また必ず起こり得る。だからドイツかどこか西ヨーロッパに現地法人ををつくる必要がある。それから社名はタマス・カンパニーではなく、タマス・バタフライ・カンパニーとういうふうにしたほうがいい。バタフライで争うときに、いまの問題には間に合わないけど、社名であるほうが、たたかう場合に強い」と。
タマス・カンパニーがなぜバタフライというブランドを使っているかという点で、向こうもバタフライはタマスより前に使っているといい始めている。だからどちらが正しいかということを証拠立ててたたかうだけでは弱い。社名を将来のために両方出しておくべきだというわけです。
結果から見ると、その弁護士さんも弁理士さんも実に立派な人でした。簡単に「勝ちます。大丈夫です」とういうことはいいませんし、勝った後も法外な金額を要求するようなこともありませんでした。実に立派な方でした。
私どもは、外国に行って、外国で弁護士や弁理士を雇って向こうとやり合うんですから、大丈夫かなと。日本でやるんならまだ安心感があるんですが。
紅林 どのくらい要求されるか、見当もつかない点もありましょうしね。
田舛 向こうでなあなあでやられると、どういうふうな結果を来たすか、わからない。
十年かけて裁判に勝つ
田舛 ともあれ、西ドイツ市場での争いは、何年かやって勝ったわけですが、勝った理由は、西ドイツは先願優先ではなくて、先使用権というものを盾にとってたたかうことができるわけでして、どちらが先にマーケットに存在したか、その証拠立てはわれわれは十分にできる。それと、向こうが非常に不合理な、不道徳な問題を起こしたという材料がいろいろありまして、裁判所は、向こうの負けということで、はっきりしたわけです。
しかしオランダでのたたかいは、いわゆるベネルクス三国は法律が違いまして、日本も先願優先のようですが、向こうも、とにかく先に届けたほうが勝ち。ですからバタフライというのはだめだということで、オランダ、ルクセンブルク、ベルギーでは、タマスというブランドでいこうと思ったら、タマスもとられていたんです。ですからそこは田舛彦介のタマヒコとうい名前にして売るということにして-ただ、タマスというものを向こうが登録していることは、これはいかにも不道徳である。そういう道徳的な争いとしてやろうということでオランダの弁護士さんが、バタフライはだめだけど、タマスならあるいは勝てるかもしれないということで、これも十年かかりました。
結局十年後に、タマスというブランドはおろすから、三百万くれ、と。三百万というのは、自分がもうけるんじゃなくて、弁護士さんに払う費用である。十年間の費用が三百万かかったというわけです。さあどうする。しょうがない、払うかということで払って、タマスはおろしてもらったわけです。
そしてその次の次の年ぐらいに、バタフライをおろします。おろすかわりに私達と取引をしてくれ。ベネルクス三国だけでけっこうだということで、もとのとおりに、十五年前のとおりにおさまったわけです。
この種の問題は日本の大メーカーには必ずあっちこっちであると思いますが、ちょっと先を見る会社であれば、あるいは会社でなくても個人が、パナマとかニカラグアとか、中南米あたりは盛んにいまそういうことをやっています。片っ端から日本のメーカーのブランドの登録をしておる。行ってみたら、たとえばソニーでも松下でも皆あるんです。持っているわけです、現地の人が。そうしたら使用できませんから、その持っている人に交渉しなければいけない。そうすると、何百万とか、請求される。だけどそれは残念ながら払わなければいけない。
コーデュバイというオランダの会社は、オランダで一番大きな運動具メーカーです。だからオランダでは、法律を悪用するというか、トップのメーカーですが、そういう会社ですら、そんなことをする。
紅林 驚くべき不道徳ですね。考えられません。
田舛 ええ、考えられませんね。
紅林 日本でそういうことをやるのはあまり聞いたことがない。
田舛 ずっと昔日本でも多少はそういうことはあったようですね。ですから日本の外務省は弱いですね。ヨーロッパとたたかうのに非常に及び腰。
紅林 すねに傷を持っているから。
田舛 ええ。非常にぼくはその点で情けなく思いました。外務省とか大使館が必死に動くためには、有力な政治家の、いまなら角栄さんぐらいの名刺を持って行けば馬は走るけれども、まずだめですね。だからどっちを向いて仕事しているのかといいたい。あまりいうと悪いんですが、そのときは本当に情けなく思いました。
紅林 しかしよく頑張られましたね。二年や三年じゃないですから。ほんとに大変なことです。
田舛 十年ですからね。まあ、向こうとしては、こういうふうにやってやれば、タマスごとき小さい会社はびっくりして、恐れおののいて、ひざを屈するだろう。こういう計算だったと思うんです。そうするとバタフライの商品は全部ヨーロッパで自由にできる。それはよく先を見たのかどうか知りませんが、結果は、食いつかれて、なかなか手強い相手であったと。
でもそれが終わりますと、ゲームが終わったように、ヤーヤーでやってきて、一緒に写真をとろうといって、その写真をウインドーに飾っておる。
紅林 そうですか、全く考えられませんね(笑)。いまはそれじゃコーデュバイには出していらっしゃるわけですか。
田舛 ええ。ところが不思議なことに、最近コーデュバイが倒産しました。結果として、わがほうとしてはすべてうまくいったことになるんです。コーデュバイが倒産しても、かわりのものとの取引が順調にいっていますから。
やはり結局、そういうよこしまなことに熱をあげるような運営というものはだめなんだなと思いますね。
国際商品としての卓球用具
田舛 ちょっと話が違うんですが、欧米のスポーツメーカーというのは、ここ数年間軒並み苦しんでいます。欧米のスポーツ熱というか、需要がやや低下傾向にある。それから、日本、アジアに攻め込まれる。まあ、われわれも攻めているほうに入るんですが、アジアとたたかうには労働コストが高いし、私どもからいえば、ヨーロッパの国は怠け者が多い。実はわれわれのところに、会社を買ってくれ、とう申し込みが最近多いんです。卓球関係はもちろん、ヨーロッパ一の卓球台のメーカーあるいはヨーロッパ一のボールのメーカーなどが会社を売りにきています。だけど、去年おととしの問題ですけれども、婉曲にお断わりしております。あんなものを抱え込むと、病根を抱え込むことになる。スキー関係のメーカーとか、テニス関係のメーカーとか、すべてが傾いています。それが日本市場へワーッと押しかけてきて、いま日本のスポーツ業界というのは、先進国の有名ブランドがどんどん入ってくるのと、中華台北、韓国、香港、中国という中進国筋からの安物の売り込みと、両方で、スポーツ用具については貿易赤字なんです。
紅林 ヨーロッパ一のほうはダンピングしてきているわけですか。
田舛 いえ、これはダンピングじゃなくて、日本人がブランド好みなんです。ゴルフならジャックニクラウスのサインが入ったウィルソンとか、スポルディングとか、有名ブランドを好む傾向がありますね。そこら辺でゴルフ、テニス、あるいはスキーというところは、日本のかっこうをつける人は舶来を持ちたいですものね。
紅林 依然としてそういう嗜好がありますか。
田舛 ありますね(笑)。
紅林 バタフライはその心配は全くないわけですね。
田舛 その点では卓球用具が日本の輸出の旗頭になっています。規模は小さいですけれども、卓球用具についてはほとんど輸入なしで、われわれが外国を攻めている。そりゃ輸出するばかりが能ではないけれども、スポーツ業界は、こちらが三輸出をすれば、五か六ぐらいが輸入で、ある意味では負けているわけですから、その中では卓球は非常に健闘しております。
結局しかし、将来的にどうなるかわかりませんけれども、外国市場でこちらが常に攻勢の状態にいないと、逆に今度は日本が攻められて、そのときは非常に苦しくなる。ですからまあ、外国との関係というものは、金をとるばかりではいけないんですから、常に相手国の卓球界を育てるというか、助けるような行動をとりながら輸出をする。
紅林 タマスさんのところでつくっていらっしゃるラケットの製法、それは向こうで盗むこと、あるいは真似することはできないのですか。
田舛 それは不可能ではないと思いますが、商品が複雑で、製法、それから材料のノウハウがありまして、簡単にできないと思います。もちろん安い商品、安物のところでは…。
紅林 それは簡単でしょうけどね。
田舛 われわれのコストがね。日本人の労働賃金がけっこう高くなりまして。
紅林 それはタマスさんのところは大したものです。よかろう、高かろうですから。昔の日本の逆をいっているわけです。付加価値が一番高いものをやっていらっしゃるのだから、なかなか大したことですね。
田舛 若干高いのはしょうがなくて、それだけの価値のあるものを出すということで勝負をしていくということです。
紅林 日本の企業もみんなそのようになれば大したものです。そういう意味で見本的な企業であるといつも私は感服申し上げているわけです。
「小さい井戸を深く掘る」がタマスの経営理念
紅林 来年三月には新社屋もおつくりになられる由でほんとうにおめでとうございました。そうするというと、世界の選手がみんなタマスさんの工場の研究所へやってくることになりますね。だから先行き大変なものです。
田舛 その点は、小さい井戸を深く掘るということでありまして、われわれの業績がますます拡大するということは、実は考えられないと思っています。少なくとも現状を守る。そして卓球を少しでも発展させるお手伝いをするということ。それでわが社がそこに安定があるというふうに考えておりまして、今後つくるトレーニングセンターというか、名前はまだ決めておりませんが、要するに卓球科学研究所的な目的でこれをつくりますけれども、これは日本の若い選手を強くして、日本の国内における卓球のイメージを上げる。それから、ママさんとかベテラン、老人社会にだんだんなっていく。そこへ卓球というものを普及していきたいということと、もう一つは国際技術交流というか、国際親善になるのではないか。各国から二、三名のジュニアの選手を受け入れて、そこで(トレーニングセンター)寝泊まりを一緒にする。こういうことが外国からも非常に歓迎されるわけです。
紅林 それは大変なことですね。日本を知ってもらうということからいっても、これは大変有意義かつ効果的なことです。
田舛 そういうことがわれわれのライフワークの一つというふうに考えて。そこまでやれば、これでだめならしょうがないじゃないかという気が…(笑)。
紅林 いえいえ、そんなことは全くございません。中国や韓国の選手がずいぶん田舛さんに招待されて日本へきているようですね。戦後日本のイメージは非常に悪いし、特に韓国ではずいぶん日本は悪い国だと教育されているように思います。それが日本にきてみると全く違うということで、認識を新たにして帰っていくという新聞記事もいろいろあります。これは、ですから大したものだと思います。やっぱりそれがほんとう国際親善です。そうすれば教科書問題も雲散霧消していくと思います。
田舛 そうですね。非常におもしろいんです。私どもも韓国に初めて行くことになったときに、実のところは、韓国とのあれでは、私個人的に印象の悪い事件がありまして、あまり好きな国ではなかったんですが、七、八年前に初めて、どうしても行かなきゃならんということが起こって、行くときに考えたんですけれども、昔秀吉とか加藤清正とか、槍を持って征伐に行った。やっぱり鉄砲や槍を持って行くような心組みではだめなんじゃないか。印象がよかろうが悪かろうが、向こうも人間なのだから、向こうの人の心をつかむ方法論を考えないといけないんじゃないかと思い、ともあれ、向こうに行って人と会っても、私はこういういい方をしているわけです。「あなた方韓国の人と日本人とは-私はいろいろな国の人と接触するけれども-心情的にも歴史的にも一番近い兄弟の国だと私は思う。あなたが兄貴だ」と。そうしたら「そうじゃありません。文化の流れは確かにわれわれのほうから日本へ流れた。しかしそれを日本人は立派に花を咲かせた。われわれはそれを学ばなければいけない」というんです。ところがこっちが兄貴みたいな顔をすると、絶対突っ張ります。ですから、それをちょっと先にいってやることが必要なんじゃないかと思います。
紅林 事実そうなのです。みんなそういう気持になれば、日韓関係など非常によくなると思います。やっぱり韓国は文化の上で日本の兄貴分です。
田舛 その点私どもはスポーツですから、選手が日本にくる。その世話をしてあげる。あるいはこっちから行く橋渡しをするということなので、選手やコーチと接触するわけです。私は韓国の言葉はわかりませんからなるべく言葉は、いまから覚えるのは大変ですから歌を覚えようと。歌を覚えていたら大変いい。今度はこの歌を覚えなさい、とレコードをいっぱいくれる。とにかく私は言葉はできないし、ほかの能力もないし、歌なら健康法で、というので、実は六十曲覚えた。
紅林 そんなにですか。いやそれはすごいですね。
田舛 パーティがあるんです。何かがあると必ずパーティ。そのとき「田舛さん、歌ってくれ」といわれると「じゃ、何を歌おうか」ということで。
紅林 六十曲といったら大変なものです。
田舛 いまはその半分ぐらい。もう忘れました。この間八月末に第二回ソウル国際オープンという大会がありまして、世界の四十二ヵ国が集まって、全員のパーティがありました。韓国の会長が「田舛さん、歌ってくれ」というわけです。で歌ったところが、向こうのNHK、KBSとかいう公共放送があるんです。それが「今度日本人の韓国歌謡大会にぜひ応募してくれ」と。
紅林 それはそれは…(笑)。
田舛 「とにかくテープを四曲ぐらい吹き込んで送ってくれないか」というわけです。漫画みたいですが、送った。そうしたら今度十二月五日に審査結果の放送があるんです、日本向けの(笑)。
紅林 楽しみですね、それは。それがほんとの日韓文化交流ですね。そういうことがなければ、だめですね。
田舛 実は私は、こんな調子で八ヵ国の歌がうたえるんです。インドネシアの大会ではインドネシアの歌、タイではタイの歌というふうに、アメリカでもユーゴスラビアでもやりました。
紅林 大変けっこうなお話しで、もう少し韓国のことも伺いたいのですが、他日を期すことにして今日は一応ここで終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
(以上)
[卓球レポートアーカイブ]
「卓球は血と魂だ」 第四章 五 紅林先生との対談
2013.11.03
\この記事をシェアする/