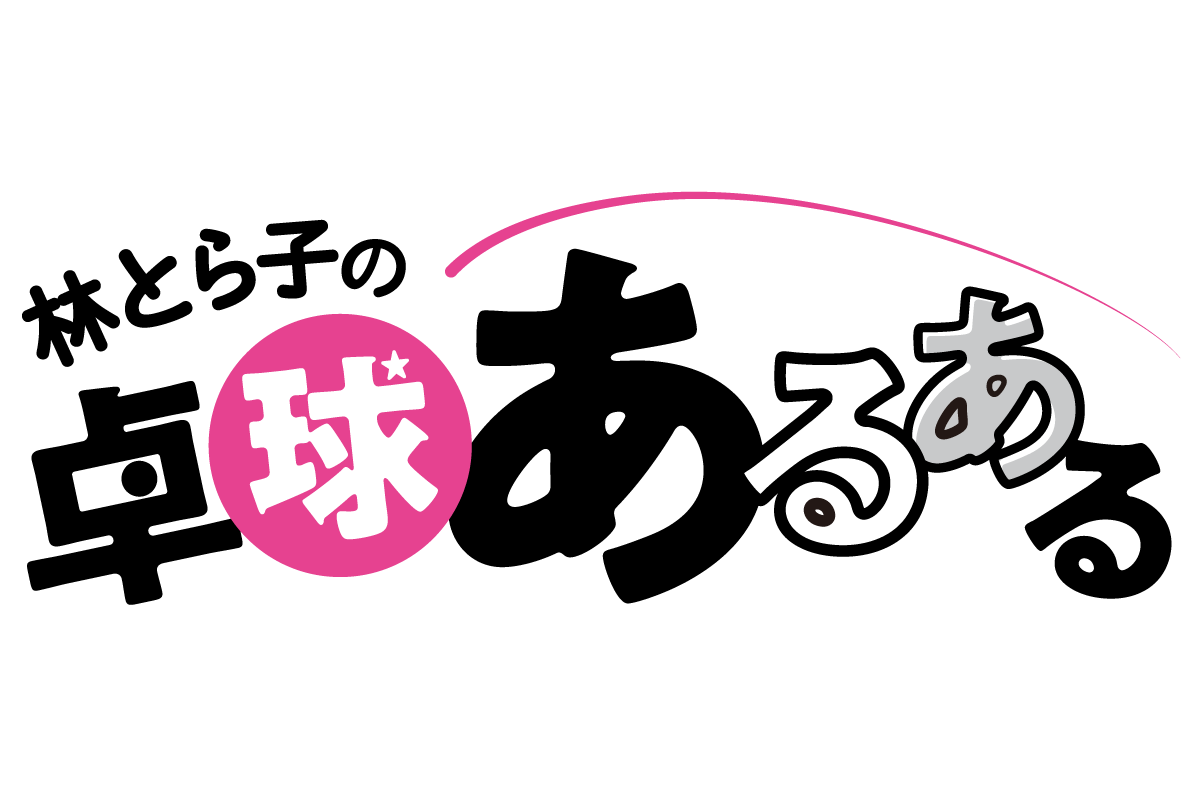誰にも好、不調がある
人間である以上、誰にでもコンディションに好、不調がある。
調子のよいときは、やれる、勝てる、という自信から多少の不安があっても試合前に考えたことが比較的やれるものである。だがコンディションが最悪の場合は、いつものように思い切ってやろうとか、勝敗にこだわらないでやろうとか、無心になってやろうとか考えてもなかなか考え通りできないのがふつうである。またいくら強い気力の持ち主でも気力だけではカバーできないときがある。
コンディションの悪い例の代表的なものに次のようなものがある
・フォームに悩んでいたり、動きが悪いとき
・グリップがしっくりいかないとき、不安定なとき
・直前に変えたラバーが飛びすぎたり、飛ばなかったり
・コンディション作りの失敗
体の故障では
・手首や腰や足首を痛めているとき
・ひどい筋肉痛や風邪やその他の病気
まだまだたくさんあると思うが、いろいろな困難にぶつかる。また自分より強い人と対戦するときに不安や恐さなどの精神面からコンディションを崩す人もいる。しかしいくら最悪のコンディションであっても、健康上の理由以外はスポーツマンである以上困難に打ち勝ち試合に出なければならない。またチームの人数がぎりぎりとか、チームの層が薄い場合の主力選手は少々の健康上の理由ならば試合をしなければならないときもある。
もし気力でもカバーできない不調のときはどうしたら良いだろうか。
己をよく知ることが勝利の道
このような不調のとき、試合で自分の力を発揮することは実にむずかしいものである。
その一番の問題は、人間は技術が向上するにつれ知らず知らずに誇りを持つからだと思う。もちろん誇りを持つことは非常に良いことだと思う。だが調子の良いときはいいが、調子の悪いときはよほど自分自身がしっかりしていないと失敗を起こす危険がある。
たとえばスマッシュの調子がすごく悪いのに何も気をつけないでいつものように低いボールを打って、勝てる相手に自滅したり、不調で自信がないのにその気持ちのままプレイするために相手のことを考える余裕がなく負けたりする。これでは調子のいいときは勝てるが悪いときは負けるという好、不調がそのまま出て、人間としてスポーツをやる価値が低いと思う。どのようなときにも自分のベストが出せるようにいろいろ工夫してやるところにスポーツの本当の意義があり価値があると思う。
それには、孫子の兵法書に『敵を知り、己を知れば百戦危うからず』という言葉があるように、まず自分をよく知ることがもっとも重要である。もし最悪の不調の場合は己を捨てその不調に合わせて"自分のレベルを低くみる"ことが必要。そうすれば心に余裕ができ、精神面にも技術面にもいつもとちがった新しい道が開けてくるものである。
私もいろいろな不調を経験しているので、一番印象に残っている試合を紹介しよう。
悪いグリップから調子が崩れる
'72年9月に、日本、中国や朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)らが加盟の新しくできたアジア卓球連合の第一回アジア選手権大会が中国の北京で行なわれたときだった。私は中国、朝鮮が出場する本当のアジアNo.1を決める大会であるし、日本を代表する選手の責任においてもこれからの若い選手のためにも日本卓球界のためにも団体だけはなんとしても優勝したいと熱望していた。ストックホルムの世界選手権大会に初出場したときと同じぐらい団体戦に勝ちたい気持ちであり、強く燃えていた。
しかし、その気持ちと反対に大会に入ってもグリップに悩みコンディションは今までになく最悪だった。その原因は日本を出発する前に長年愛用していた200gあるラケットを、重すぎて体力の消耗が激しく不利と判断してラケットのまわりを3ミリぐらい削り小さくしたからであった。確かに軽くなったが、反対に空気の抵抗が少なくなったためにインパクトとリズムが狂い使用不能になってしまった。軽率だった。すぐに新しい3本のスペアの中から1本取り出した。だがどれも握るだけで腕全体に力が入り、グリップが手に合わない。そのために振りが鈍くスピードも出ない。動きも悪い。打ったあとのもどりもすべての切りかえしも遅い。すぐ疲れる。日本の女子選手と練習をしてもドライブを簡単に打ち込まれるほど最悪の調子に落ちいってしまった。練習中にグリップを直したり、深夜にまで直したりしたが一向によくならず、できれば大会が中止にならないものかと思ったほど悩みに悩んだ。しかし大会は予定通り始まった。
不調はいつもの精神で通ぜず
だが試合はチーム戦に強い河野選手、田阪選手の活躍で順調に勝ち進み、中国も5対3で破り残るは朝鮮チームで念願の優勝に大きく近づいた。私の予想は中国に勝った勢いで5対2ぐらいか、悪くても5対3だろうと考えていた。
団体戦の最終日、2万人の大観衆の中で男女各1コートを使って試合が行なわれた。日本が勝てば全勝で優勝、日本が負ければ中国が優勝という大一番。A長谷川、B河野、C田阪の日本のオーダーで私の出番は1番、5番、ラストの9番。大試合になるとトップの試合が非常に重要でオーダーから責任を強く感じた。しかし団体戦の鍵を握るといわれる重要なトップで、しかもチームの柱とならなければいけない私が金昌虎選手に攻撃ミスを恐れた消極的なプレイで元気なくストレート負けをしてしまった。そのまずいプレイが原因で河野選手、田阪選手も動揺し同じようにミスを恐れたプレイで負け1対4とリードされ、絶体絶命のピンチに追い込まれてしまった。私がトップで負けた原因で追い込まれ、また2敗目も喫したことから責任を強く感じ、大きな優勝チャンスを目の前にして死んでしまいたいような気持ちであった。
そのときの私の試合は、朝鮮だからといって油断をしたからでは決してない。優勝は意識したが試合前はいつも通り試合に臨む心構えを考え、作戦を立て、そしてシャドウプレイをして体を暖め、いつものように万全な態勢で臨んだつもりだった。そして試合では相手が小さい変化サービスからフォアハンドによる3球目攻撃の作戦とわかりすぐにレシーブの位置を前にした。しかし力の入るグリップが気になってすべてが狂った。ミスを恐れて強く払えない。相手にやすやす攻めさせないように小さくツッツこうとするが、ポカリと高く浮く。打つ前に腕、肩に力が入ってドライブ、スマッシュにミスが多く、入ってもスピードが出ない。また動きも切りかえしも悪くぎこちないロボットのような感じで最悪の調子であった。
そのためこれではいけないとプレイ中に「グリップを気にするんじゃない。腕、肩の力を抜くんだ。ミスを恐れず攻めるんだ。相手にぶつかっていくんだ。勝敗にこだわらず全力を尽くすんだ。気力だ。」と攻撃ミスを恐れない積極的なプレイができるように何度も何度も自分を強く励ました。だがいつものようにどう励ましても自信が持てず、朴信一選手にも、右、左にめった打ちにあって、あっという間に終わってしまった。試合をしながら非常に辛かったことを覚えている。
わが身をすててこそ、新しい道が開ける
私は1対4の絶体絶命のピンチから、ベンチで応援する勇気はとてもなかった。真っ青な顔をしながら背水の陣で死の物狂いで頑張る河野選手、田阪選手の試合を30メートルぐらい離れた出入口のドアの横から応援した。大事な試合で何とバカな人間なんだと自分を激しく卑下しながら、河野、田阪、頑張ってくれと心の中で何度も叫び続けた。勝利を与えてくださいと、壁に頭を何度もぶつけながら神に祈った。卓球生活で初めての経験である。そして祈っているうちに自分の心境に大きな変化が起きた。「自分の現在の力は2流から3流だ。アジアチャンピオンでも日本チャンピオンでもない。もしラストに出る機会を得たら、朝鮮の選手から真の卓球を教えてもらうんだ。負けてもともとの気持ちでやるんだ、それには相手以上の気力と勇気と自信を持って自分の持っているすべてを出すんだ」と心の底から思った。
試合は、河野選手、田阪選手のすばらしい集中力と気力で3点を奪い返し、ついに4対4のタイとなった。相手は2番で河野選手に勝った左のドライブマン金永三選手だった。コートに立った瞬間、不思議に思った。さきほどまでは体育館全体に濃い霧がかかっているように見えたが、コート全体が実にきれいに見える。全身に鉄のヨロイをつけているように重かったからだも非常に軽くなった。相手の顔もはっきり見える。グリップも完全ではないがだいぶ力が抜けていた。本当に不思議なぐらいかわった。
試合も自然に変化が出てきた。ロボットのような動きから速い動きに変り、プレイに粘りと積極性が出てきた。バック側に思い切って回り込めるようになった。台上のレシーブも払えるようになった。ドライブもスマッシュも思い切り打てるようになった。また競り合っても攻撃ミスを恐れない積極的なプレイができるようになった。それに心境の変化から一番大きく変ったのは、みちがえるほど心に余裕が出てきたことだ。あれほど試合前と試合中に励ましても受けつけなかったのに考えたことが行動に移せるようになった。また相手の心が読めるようになって、次々と心、技にわたって新しい道が開けた。そして積極的な攻撃の差、気力の差で打ち勝ち、勝利を勝ち取り念願の団体優勝を飾ることができた。苦しい試合であっただけに、優勝の感激は初出場で初優勝を飾った世界選手権の団体戦と同じぐらい嬉しかった。
負けてもともとに金メダル
しかし、もし前の2試合と同じ気持ちで試合に臨んでいたとしたら、不調の上ラストで緊張からきっと手、足が震えて負けていただろう。
私は表彰式のときつくづく思った。「今までの自分の心構えは、調子が悪くないとき、あるいは相手とあまり力の差がないときや下の選手とするときに臨む心構えであった。だが最悪のコンディションとか、相手が自分よりはるかに強い選手とするときの心構えではなかった」ということを強く反省した。
そして人間はどんなに不調にあっても、心の持ち方によってカバーできることを知った。しかしそれは経験から自分を正確に知るためには真の努力をしていなければつかむことができないことだ。表彰式で立派な金メダルを胸にかけられたとき、この金メダルは優勝したからいただけたのではなく、河野選手、田阪選手のすばらしい活躍、ベンチの応援と「朝鮮のチームに真の卓球を教えてもらうんだ、負けてもともとでやるんだ...」という気持ちに心底なった心に金メダルをいただいたのだ、と強く思った。そして「スポーツは心だ」また、『身をすててこそ浮かむ瀬もあれ』という、ことわざと同じことを身を持って体験できたことは幸せだった。
人間である以上、誰にでもコンディションに好、不調がある。
調子のよいときは、やれる、勝てる、という自信から多少の不安があっても試合前に考えたことが比較的やれるものである。だがコンディションが最悪の場合は、いつものように思い切ってやろうとか、勝敗にこだわらないでやろうとか、無心になってやろうとか考えてもなかなか考え通りできないのがふつうである。またいくら強い気力の持ち主でも気力だけではカバーできないときがある。
コンディションの悪い例の代表的なものに次のようなものがある
・フォームに悩んでいたり、動きが悪いとき
・グリップがしっくりいかないとき、不安定なとき
・直前に変えたラバーが飛びすぎたり、飛ばなかったり
・コンディション作りの失敗
体の故障では
・手首や腰や足首を痛めているとき
・ひどい筋肉痛や風邪やその他の病気
まだまだたくさんあると思うが、いろいろな困難にぶつかる。また自分より強い人と対戦するときに不安や恐さなどの精神面からコンディションを崩す人もいる。しかしいくら最悪のコンディションであっても、健康上の理由以外はスポーツマンである以上困難に打ち勝ち試合に出なければならない。またチームの人数がぎりぎりとか、チームの層が薄い場合の主力選手は少々の健康上の理由ならば試合をしなければならないときもある。
もし気力でもカバーできない不調のときはどうしたら良いだろうか。
己をよく知ることが勝利の道
このような不調のとき、試合で自分の力を発揮することは実にむずかしいものである。
その一番の問題は、人間は技術が向上するにつれ知らず知らずに誇りを持つからだと思う。もちろん誇りを持つことは非常に良いことだと思う。だが調子の良いときはいいが、調子の悪いときはよほど自分自身がしっかりしていないと失敗を起こす危険がある。
たとえばスマッシュの調子がすごく悪いのに何も気をつけないでいつものように低いボールを打って、勝てる相手に自滅したり、不調で自信がないのにその気持ちのままプレイするために相手のことを考える余裕がなく負けたりする。これでは調子のいいときは勝てるが悪いときは負けるという好、不調がそのまま出て、人間としてスポーツをやる価値が低いと思う。どのようなときにも自分のベストが出せるようにいろいろ工夫してやるところにスポーツの本当の意義があり価値があると思う。
それには、孫子の兵法書に『敵を知り、己を知れば百戦危うからず』という言葉があるように、まず自分をよく知ることがもっとも重要である。もし最悪の不調の場合は己を捨てその不調に合わせて"自分のレベルを低くみる"ことが必要。そうすれば心に余裕ができ、精神面にも技術面にもいつもとちがった新しい道が開けてくるものである。
私もいろいろな不調を経験しているので、一番印象に残っている試合を紹介しよう。
悪いグリップから調子が崩れる
'72年9月に、日本、中国や朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)らが加盟の新しくできたアジア卓球連合の第一回アジア選手権大会が中国の北京で行なわれたときだった。私は中国、朝鮮が出場する本当のアジアNo.1を決める大会であるし、日本を代表する選手の責任においてもこれからの若い選手のためにも日本卓球界のためにも団体だけはなんとしても優勝したいと熱望していた。ストックホルムの世界選手権大会に初出場したときと同じぐらい団体戦に勝ちたい気持ちであり、強く燃えていた。
しかし、その気持ちと反対に大会に入ってもグリップに悩みコンディションは今までになく最悪だった。その原因は日本を出発する前に長年愛用していた200gあるラケットを、重すぎて体力の消耗が激しく不利と判断してラケットのまわりを3ミリぐらい削り小さくしたからであった。確かに軽くなったが、反対に空気の抵抗が少なくなったためにインパクトとリズムが狂い使用不能になってしまった。軽率だった。すぐに新しい3本のスペアの中から1本取り出した。だがどれも握るだけで腕全体に力が入り、グリップが手に合わない。そのために振りが鈍くスピードも出ない。動きも悪い。打ったあとのもどりもすべての切りかえしも遅い。すぐ疲れる。日本の女子選手と練習をしてもドライブを簡単に打ち込まれるほど最悪の調子に落ちいってしまった。練習中にグリップを直したり、深夜にまで直したりしたが一向によくならず、できれば大会が中止にならないものかと思ったほど悩みに悩んだ。しかし大会は予定通り始まった。
不調はいつもの精神で通ぜず
だが試合はチーム戦に強い河野選手、田阪選手の活躍で順調に勝ち進み、中国も5対3で破り残るは朝鮮チームで念願の優勝に大きく近づいた。私の予想は中国に勝った勢いで5対2ぐらいか、悪くても5対3だろうと考えていた。
団体戦の最終日、2万人の大観衆の中で男女各1コートを使って試合が行なわれた。日本が勝てば全勝で優勝、日本が負ければ中国が優勝という大一番。A長谷川、B河野、C田阪の日本のオーダーで私の出番は1番、5番、ラストの9番。大試合になるとトップの試合が非常に重要でオーダーから責任を強く感じた。しかし団体戦の鍵を握るといわれる重要なトップで、しかもチームの柱とならなければいけない私が金昌虎選手に攻撃ミスを恐れた消極的なプレイで元気なくストレート負けをしてしまった。そのまずいプレイが原因で河野選手、田阪選手も動揺し同じようにミスを恐れたプレイで負け1対4とリードされ、絶体絶命のピンチに追い込まれてしまった。私がトップで負けた原因で追い込まれ、また2敗目も喫したことから責任を強く感じ、大きな優勝チャンスを目の前にして死んでしまいたいような気持ちであった。
そのときの私の試合は、朝鮮だからといって油断をしたからでは決してない。優勝は意識したが試合前はいつも通り試合に臨む心構えを考え、作戦を立て、そしてシャドウプレイをして体を暖め、いつものように万全な態勢で臨んだつもりだった。そして試合では相手が小さい変化サービスからフォアハンドによる3球目攻撃の作戦とわかりすぐにレシーブの位置を前にした。しかし力の入るグリップが気になってすべてが狂った。ミスを恐れて強く払えない。相手にやすやす攻めさせないように小さくツッツこうとするが、ポカリと高く浮く。打つ前に腕、肩に力が入ってドライブ、スマッシュにミスが多く、入ってもスピードが出ない。また動きも切りかえしも悪くぎこちないロボットのような感じで最悪の調子であった。
そのためこれではいけないとプレイ中に「グリップを気にするんじゃない。腕、肩の力を抜くんだ。ミスを恐れず攻めるんだ。相手にぶつかっていくんだ。勝敗にこだわらず全力を尽くすんだ。気力だ。」と攻撃ミスを恐れない積極的なプレイができるように何度も何度も自分を強く励ました。だがいつものようにどう励ましても自信が持てず、朴信一選手にも、右、左にめった打ちにあって、あっという間に終わってしまった。試合をしながら非常に辛かったことを覚えている。
わが身をすててこそ、新しい道が開ける
私は1対4の絶体絶命のピンチから、ベンチで応援する勇気はとてもなかった。真っ青な顔をしながら背水の陣で死の物狂いで頑張る河野選手、田阪選手の試合を30メートルぐらい離れた出入口のドアの横から応援した。大事な試合で何とバカな人間なんだと自分を激しく卑下しながら、河野、田阪、頑張ってくれと心の中で何度も叫び続けた。勝利を与えてくださいと、壁に頭を何度もぶつけながら神に祈った。卓球生活で初めての経験である。そして祈っているうちに自分の心境に大きな変化が起きた。「自分の現在の力は2流から3流だ。アジアチャンピオンでも日本チャンピオンでもない。もしラストに出る機会を得たら、朝鮮の選手から真の卓球を教えてもらうんだ。負けてもともとの気持ちでやるんだ、それには相手以上の気力と勇気と自信を持って自分の持っているすべてを出すんだ」と心の底から思った。
試合は、河野選手、田阪選手のすばらしい集中力と気力で3点を奪い返し、ついに4対4のタイとなった。相手は2番で河野選手に勝った左のドライブマン金永三選手だった。コートに立った瞬間、不思議に思った。さきほどまでは体育館全体に濃い霧がかかっているように見えたが、コート全体が実にきれいに見える。全身に鉄のヨロイをつけているように重かったからだも非常に軽くなった。相手の顔もはっきり見える。グリップも完全ではないがだいぶ力が抜けていた。本当に不思議なぐらいかわった。
試合も自然に変化が出てきた。ロボットのような動きから速い動きに変り、プレイに粘りと積極性が出てきた。バック側に思い切って回り込めるようになった。台上のレシーブも払えるようになった。ドライブもスマッシュも思い切り打てるようになった。また競り合っても攻撃ミスを恐れない積極的なプレイができるようになった。それに心境の変化から一番大きく変ったのは、みちがえるほど心に余裕が出てきたことだ。あれほど試合前と試合中に励ましても受けつけなかったのに考えたことが行動に移せるようになった。また相手の心が読めるようになって、次々と心、技にわたって新しい道が開けた。そして積極的な攻撃の差、気力の差で打ち勝ち、勝利を勝ち取り念願の団体優勝を飾ることができた。苦しい試合であっただけに、優勝の感激は初出場で初優勝を飾った世界選手権の団体戦と同じぐらい嬉しかった。
負けてもともとに金メダル
しかし、もし前の2試合と同じ気持ちで試合に臨んでいたとしたら、不調の上ラストで緊張からきっと手、足が震えて負けていただろう。
私は表彰式のときつくづく思った。「今までの自分の心構えは、調子が悪くないとき、あるいは相手とあまり力の差がないときや下の選手とするときに臨む心構えであった。だが最悪のコンディションとか、相手が自分よりはるかに強い選手とするときの心構えではなかった」ということを強く反省した。
そして人間はどんなに不調にあっても、心の持ち方によってカバーできることを知った。しかしそれは経験から自分を正確に知るためには真の努力をしていなければつかむことができないことだ。表彰式で立派な金メダルを胸にかけられたとき、この金メダルは優勝したからいただけたのではなく、河野選手、田阪選手のすばらしい活躍、ベンチの応援と「朝鮮のチームに真の卓球を教えてもらうんだ、負けてもともとでやるんだ...」という気持ちに心底なった心に金メダルをいただいたのだ、と強く思った。そして「スポーツは心だ」また、『身をすててこそ浮かむ瀬もあれ』という、ことわざと同じことを身を持って体験できたことは幸せだった。
筆者紹介 長谷川信彦
 1947年3月5日-2005年11月7日
1947年3月5日-2005年11月7日
1965年に史上最年少の18歳9カ月で全日本選手権大会男子シングルス優勝。1967年世界選手権ストックホルム大会では初出場で3冠(男子団体・男子 シングルス・混合ダブルス)に輝いた。男子団体に3回連続優勝。伊藤繁雄、河野満とともに1960~70年代の日本の黄金時代を支えた。
運動能力が決して優れていたわけではなかった長谷川は、そのコンプレックスをバネに想像を絶する猛練習を行って世界一になった「努力の天才」である。
人差し指がバック面の中央付近にくる「1本差し」と呼ばれる独特のグリップから放つ"ジェットドライブ"や、ロビングからのカウンターバックハンドスマッシュなど、絵に描いたようなスーパープレーで観衆を魅了した。
 1947年3月5日-2005年11月7日
1947年3月5日-2005年11月7日1965年に史上最年少の18歳9カ月で全日本選手権大会男子シングルス優勝。1967年世界選手権ストックホルム大会では初出場で3冠(男子団体・男子 シングルス・混合ダブルス)に輝いた。男子団体に3回連続優勝。伊藤繁雄、河野満とともに1960~70年代の日本の黄金時代を支えた。
運動能力が決して優れていたわけではなかった長谷川は、そのコンプレックスをバネに想像を絶する猛練習を行って世界一になった「努力の天才」である。
人差し指がバック面の中央付近にくる「1本差し」と呼ばれる独特のグリップから放つ"ジェットドライブ"や、ロビングからのカウンターバックハンドスマッシュなど、絵に描いたようなスーパープレーで観衆を魅了した。
本稿は卓球レポート1976年3月号に掲載されたものです。