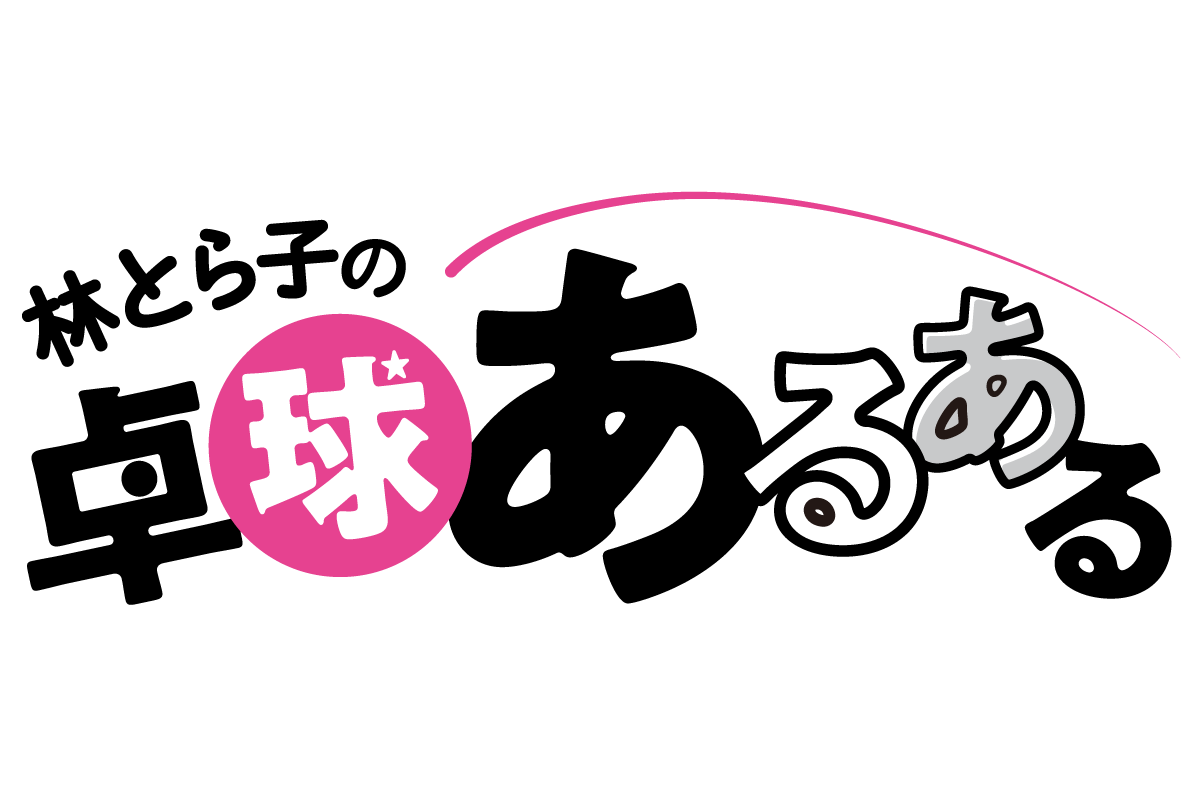「日本は世界一になるための地図を持っている。どれくらいの気迫で、どのくらい練習すれば世界一になれるのか知っている」と国際卓球連盟シャララ会長。
日本からは過去13人のシングルス世界チャンピオンが生まれている。世界一への道を知るため彼らの足跡をたどってみよう。第1回は世界選手権で最も多く金メダルを取り、後に国際卓球連盟会長になった故・荻村伊智朗選手。今回は『卓球レポート』1970年1月号から3回にわたって掲載したインタビューの1回目(選手時代)を紹介する。
―荻村さんには、三つの顔があると思う。プレーヤーとしての顔、卓球コーチとしての顔、それに卓球理論化としての顔。このいずれの分野でも、大きな足跡を残しておられる。プレーヤーとしては、世界選手権に9回連続参加し、男子団体5連勝、シングルス2回優勝を含む12個の金メダル。もちろん、日本の卓球選手としては最高の金メダリストであるし、日本の全アマチュアスポーツを通じでも、世界一の種目・回数が12というのは、最高です。卓球コーチとしては、2年間ほど日本卓球協会のヘッドコーチをつとめられ、その間に山中、深津、長谷川、鍵本選手らを育て、多くの選手に刺激を与えた。海外でも10カ国ほどコーチをされている。また、卓球理論化としては、卓球レポートの読者にはおなじみの『中高校生指導講座』や『世界の選手に見る卓球の戦術・技術』(ともに絶版)など単行本を出されたり、卓球誌にたくさんのユニークな卓球理論を発表されている。
こういった三つの顔がありますので、2回か3回にわけて、掲載させていただきます。今回はまず、"プレーヤーとしての顔"。プレーヤーとしての生いたちについて、うかがいます。金メダル12個の選手というと、雲の上の選手みたいな感じになりますが、その荻村さんも、高校時代はインターハイに一度も出ていないそうですね。高校1年の国体東京予選では1回戦で負けたとか。また、卓球を始めた時期もおそく、高校1年から始められたそうですね。そういった、無名時代の話から...。
1.無名の都立西高時代(昭和23~25年)
終戦の翌々日に陸軍幼年学校に入ることになっていた。その頃の子供は、体を基本的にきたえるという意味では水準が非常に高かったと思う。行軍<こうぐん>(長距離の徒歩)できたえられたし、電車が空襲で焼けたため毎日片道5㎞を歩いて通学していた。小学生時代から足を中心にしてきたえられた時代だと思う。中学1年で終戦を迎え、卓球をやる前は少年野球と体操をやっていた。だから、体力の蓄積はかなりあった。
●高1で入部・1回戦で負け
高校1年の9月に卓球部へ入部したが、入部の決定的な動機は、体育館で卓球部の上級生がロングのラリーを引いていた。あき時間で、誰もいないところでやっていたので「すごくきれいでいいな。よしオレもやろう」と思った。直接のキッカケは、それだ。
卓球部といっても、正規の台が1台もない。板を集めて釘で打ちつけたのが1台あったが、練習できるようなしろものでない。よそへ練習試合を申し込みながら練習していた。入部1週間後に国体都予選に出たが1回戦で負けた。11月頃に中古の台を1台買ってもらうことになって、大八車を引っぱって都立西高(吉祥寺)から渋谷の卓球場まで往復20㎞ぐらいを歩いて運んだ。大八車の上で弁当をたべたのが記憶に残っている。
当時はある卓球選手の事件が新聞にのったりしたこともあって、肩身のせまい思いだった。ラケットをかくして学校へ通うような気分だった。卓球場へ行くのも、不良がいるというので、多少のうしろめたさを感じながら門をくぐった。卓球場では、みんながあんまりうまいので、外で見ていて、とうとう中へ入れないで帰ったこともあった。
●権威者に素質がないといわれる
中田という上級生を非常に尊敬していた。大振りのロングで、ボールを引きつけて打つきれいな卓球。一生けんめいその人のフォームを最初はマネした。教えてくれるというと、どこへでもついていった。
卓球選手としてのぼくの将来性については、最初から評価がわかれていた。非常に素質があるという人と、あんなのたいしたことないという人と。ある"権威者"は二つの点でダメだといった。一つは、お前は体を悪くする。顔色があおいし、体が細い。卓球場はほこりっぽい。必ず肺病になる。だから、卓球はやめろ、といった。もう一つの理由は、得に素質があるとは思えない、野球をやっていた方がいいんじゃないか、ということだった。
しかし、ぼくには理由が納得できなかった。練習道場は清潔にすればいいじゃないか。そのときの"権威者"のことばが残っていたから、2年になってからは毎日卓球部が体育館の拭き掃除をやるようにしたりした。その他、練習場については、衛生上の問題がおきないように気をくばった。素質の方は、あるかどうかわからんことだけど、西高卓球部ではぼくと同じぐらいの勢いで伸びていた実力伯仲のものが2人いて、その連中と一緒に3年のとき東京都のチーム戦で優勝した。富田芳雄さん(現江口)の高千穂とか、松前・安藤の早実、山口才二の世田谷とか、強いチームがあったが、クジ運にも恵まれて部創立3年目にして都で優勝した。すっかり良い気になって、全国学校対抗の代表をねらい、修学旅行を返上して、練習した。だが、代表決定戦で高千穂に負けてしまった。修学旅行なるものは、結局一度も行ったことがない。
●ロングサービスとオールフォア
高校3年生ぐらいまでは、ロングサービスとオールフォアで打つだけの卓球だった。ショートもカットもバックハンドもやらない。打球点も低いし、とても勝てるような卓球ではなかったが、足だけはよくきたえていたので速く、足でかせぐ卓球だった。しかし、ショートのうまい埼玉の福田選手に高2の都市対抗予選で9本と11本で負けた。どうすればよいか?卓球というものが、よくわからなかった。一つの模範とか、いいなと思うものに酔っていて、それを目ざしてやるということで、根本的にわかっていなかった。相変わらず打球点を落としたロングのままで、足だけをより速くするオールフォアの卓球を続けていた。
学校の環境としては、二度家事で焼けたので、電気は一切つけさせないし、合宿もさせない。下校は5時か5時半。学校での練習は1.5時間ぐらい。あとは卓球場へ行って練習したが、金の問題があるので、1~2時間しかできない。3年の頃は八王子へ通って、二本掛けコルク・ショートマンの河田さん(三井生命)と一本差し木面カットの阿木さん(中大出)に3カ月ぐらい、毎週2回ずつ教わったことがある。教わる反面、下級生の指導を盛んにやった。コミュニケーションの手段として、部の日誌を活用した。1年上の田中という人が始めた。それを引きついだが、現在もつづいていると思う。学校から帰ってきて、夜中までかかって日誌を書いたことも随分あった。母は勉強しているとカン違いしたことも随分あるんじゃないかな。
話は前後するが、高校2年の6月に高千穂へ練習試合に行って、富田さんから17~18本とれるようになった。(富田選手は高校1年から東京代表で国体へ出場していた)もうすぐだ、と考えていた。ところが、夏休みに入った直後、武蔵境の卓球場で練習しているときに、床の一部にロウがぬってあってすべって右ひざをしたたか打った。卓球場で練習すれば、電車賃がない。西荻窪―武蔵境―三鷹と歩いて通っていた頃で、そのまま4キロほど歩いて帰った。すべったときに手をつけばよかったが、ラケットをかばって、ひざから転んだ。夜中に全身発熱した。夏休みを45日ぐらい、ほとんど何もしないで家ですごさなければならなかった。完全になおっていなかったが、新学期が始まると、あせって卓球をやった。フォームがかわり、左足のひざの柔軟性がなくなった。故障をおこしたときは、完全になおしてからやらなければならないとつくづく思った。伸びが1年間とまった。強さがほとんど変わらなかった。3年の都市対抗予選で富田さんと当たり、11本と9本しかとれなかった。
●主将になり皆に走るくせをつける
父が3歳のときに死に、母が働いていたし、ぼくも中学頃からアルバイトをいろいろやった。進駐軍のトラックに乗って多摩川の砂利運びとか、おつまみ卸しとか。古い雑誌等を持ち出して、卓球場へ通う金にバケていた。
日曜は学校で8時間ぐらい練習したが、結果的には高校時代は練習量がたりなかった。ただ、工夫とか体力トレーニングはよくやった。毎日1~2時間走った。3年でキャプテンになったときは、みんなに走るクセをつけさせようと、5時間で授業を終わってくる者と一緒に走り、6時間で終わってくる者とまた一緒に走るというようにして走った。
●高3で"力の卓球"にめざめる
高校の終わりの11月か12月に武蔵野卓球場(吉祥寺)ができた。専大OBの天野さんが吉祥クラブを組織しておって、西高のキャプテンは新部長へバトンタッチして、吉祥クラブへ入った。そこで力の卓球に初めてぶつかった。それまでのフォームの卓球、しかも得点を追求するのか美を追求するのか焦点のはっきりしない卓球から、はっきり力による得点追求の卓球へ移っていった。最初、何本打っても、天野さんのボールが伸びてきてラケットの上の方に当たった。一枚ラバーだが、伸びのあるドライブボールだった。天野さんに数カ月おそわった。しかし同じようなドライブをやろうという考えはなかった。
西高の中田さんと断絶があった。ある対抗試合のとき新人同士の対戦でぼくが負けたことがある。自分のスタイルからいって、当時はロングでねばる卓球だった。楽勝なので相手が途中でナメた態度をとった。そのことに対して、中田さんから「おこって試合をすてて、たたき出して負けてしまえ」というベンチコーチがあった。納得できず、それをやらなかった。コーチの方はごきげんななめ。そして、わがチームの同級生新人の方を向いて、これからはお前らががんばるんだ、と言われたのがこたえた。あとで帰り道を歩きながら涙がポロポロと出た。それからは自力でやらなければならないと思った。コーチを尊敬することと頼ることとは別だと悟った。いわば主体性の開眼だろう。その後は、あんまりプレーの方では人の言うとおりにやったということはない。天野さんの指導を受けたときも、そのとおりやろうということはなかったが、"力の卓球"を啓発された。
フットワークにますます磨きがかかったし、河田さんのショートに対してオールフォアでいい勝負ができるようになった。
2.都立大へ進み、スポンジの速い卓球に
都立大(昭和26年)へ入って間もなく、受験勉強の疲れとカゼが原因で、肺炎をおこし、1カ月入院した。なおってから余分に1週間ぐらい病院にいた。それがよくて、かえって体の調子がよく、伸び始めた。その頃からスポンジにかわり、前へ出る卓球になってきた。自分の頭で構築した世界へ入って行くようになって、そこでやってるようになった。寺沢という哲学の先生がいて「哲学的態度とはまず疑うことだ」という意味の話をきいて感銘があり、従来の指導書や技術・練習などに関するしきたり、定説をまず批判精神をもって総ざらいしてみたのもこのころだ。盛んに書きこみをやり、日誌に感想を書いた。
大学の関係もあって、練習量は絶対的に少ない。少ない練習量で効果をあげるためには、プレーの単純化を深くつっこめ、ということで、それから自分の体の特徴を意識しだした。
自分の体の特徴は、特別速いこと+持久力。だから、速くて速くて相手が追いつかないような卓球をしていこうと考えた。トレーニングは近くにボクシング・ジムがあって、シャドーボクシング、ミラーボクシング、なわとび、ロードワークなどをボクサーがやるのを見て、全部自分のトレーニングにとり入れた。
徹底的な先制攻撃で速く攻めて、速く返させて、また速く攻める―肉を切らして骨を切るやり方。さきに自分が消耗しても、消耗戦での持久力、速いラリーに対する敏しょう性では、負けない。だから、できるだけそういう速いプレーにもっていこう、ということでロングサービスを出して、できるだけ速く相手に返させて、それをすぐたたく、という考え方の練習と試合になってきた。
●壁打ち、サービスなど一人練習
都立大では練習する人が少なかったので、台を向こう側に立てかけて、ロングサービスを出し、フォアコーナーへ返ってくるのをスマッシュ―この一人練習をあきずにやっていた。また、垂直の壁を相手に1.7~1.8mの距離から強打。ノーバウンドでラリー100回ぐらい。ネットよりちょっと高いぐらいのところへほとんど真っすぐにボールが飛ぶように打った。最初はなれるために軟球でやり、それから硬球でやった。フットワークと振りの速さの非常に良い練習になった。アジア選手権代表候補の合宿(昭和28年)で補欠に入れられ、そのときこれをやっていたら、角田さん(現日立多賀)に感心されたことがある。今でも、急にやれといわれても、現役で強打100回をやれる人はほとんどいないでしょう。
●速さを生かすためスポンジに転向
なぜスポンジにかえたか。大きな目標としては、必ずスポンジ系の用具での速いラリーの時代がくると確信したこと。それまでの卓球は、いわば箱庭的な精緻(せいち)なものでスケールが小さく、近代スポーツといっても卓球人の自己満足にすぎない面が多いと感じていた。自分の愛好する卓球というスポーツの可能性はもっともっと大きなすばらしいものだ、というかすばらしいもののはずだ、と信じていた。そして、みんながスケールの大きいプレーに自分と同じように惹かれてゆく、とすれば、当然、人間の運動能力を極限にまで要求するスポンジ系の用具の時代にならなければならない。自分が開拓してみよう。どうせやるならば、いちばん速くてむずかしそうなものにしよう、と考えた。
スポンジでも佐藤博治さん(昭和27年世界No.1)の成功したショートでなくトップ打ちにした理由の一つには、藤井則和さん(昭和21~24、26年全日本No.1)を倒すという目標もあった。私を含め、当時の若い志のある選手たちでこの問題をさけて自分の卓球を考えることはできなかったはずだ。特に私の場合はそうだった。藤井さんはトップ打ちに弱かった。坂本さん、戸塚さんに負け、宮原さんに追いこまれている。打倒藤井という目標からもプレーの近代化という点からも、トップ打ちをやるべきだと考えた。
足を悪くして(高2)、碁をだいぶやったときにも、呉清源と木谷の新布石法にすばらしい感銘を受けた。碁は何百年昔から高い水準であるのに、全く新しい考え方が出てくる余地がある、ということは驚異だった。陸上ではザトペックのインターバル走法とか、水泳では古橋の変則ビートとか。卓球は数十年。なんで新しい考え方ができないことがあろうか、と考えた。
スポンジをやること自体に内外の抵抗があったが、自分の特殊条件から考えて、あらゆる意味で、それまでの秩序体系を見直してみるとき、自分も若いときだし、卓球自体を考え、再構成すべいだと決心した。それがスポンジによる速戦即決のロングサービスを使ったトップ打ちであり、またロングマンであるのにツッツキを使うとか、一見矛盾しているようないろいろの新しい試みにつながった。ロングマンがツッツキを使うのは、いまでは当たりまえだが、ロングマンの作戦の一部として採用したのは、これはぼくが最初だと思う。そのこと自体でロングマンという概念がくずれてゆくということもあったろう。本庄さん(京都)の試合を東京選手権で見ていたら、カット性のサービスがくると、必ず軽く打つ。ロングマンは当時、カットサービスがくると、必ず軽くでもはらって打っていたので、本庄さんは例外ではなかったわけだ。カットマンは同じボールに対してカットで返しているが、3球目をたたかれない。それなら、自分のレシーブのときだけ、カットマンとしてツッツく。次の瞬間にはロングマンとして攻撃する―というように頭の切りかえをすればいいという考え方を導入した。スポンジ自体がカット性のボールがさばきにくいことにもつながっていたが。
浅野さんや長谷川清隆さんには、ロング戦だけでなく、カットやツッツキを半分まぜて勝った。これが発展してカットに対しても、ツッツキから勝負した。全日本軟式決勝(昭和27年)で中田鉄士さんには、徹底してツッツキからの反転攻撃で勝った。
ロング戦では角田さん、五百部(いおべ)さん、富田さんとか、速い選手がいたから、速さで対抗しなければならないし、シャドープレー、サービスと3球目、壁打ちを都立大でやって、夜は日暮里で角田、五百部、渡辺、宇佐美さん、カットマンでは山口才二選手ら先輩選手と練習をした。疲れ果てた帰り道で、日暮里駅の長い階段を二度も休まなければ上れなかった。それでも吉祥寺で久保さん(タマス)らが待っていてくれれば、必ず練習をやった。その帰りに12時半ごろにたべる沖縄そばのうまかったことなど、忘れられない。
●カットが打てず"泣く"
全国都市対抗で大阪のペンのカットマン中村秋好さんと対戦。59分40秒の試合でゲームオールの19本で負けた。ツッツキが本職のカットマンに対して、ツッツキでやることは一時的な奇襲になり得ても、練習量からいっても圧勝する確約がないことをこのとき悟った。その晩は矢尾板監督の許しを得て、雲仙の山の中のテントにひとり泊まり、将来を考え明かした。その結果、最後まで勝つか負けるか、わからないツッツキ主戦よりは、ロングでやるべきだと結論したが、ふつうのロングでカット打ちをしようとする以上の考えも工夫もなく、真剣にロングでねばる練習をつづけたが、結果はよくなかった。そればかりか、ツッツキの方まで中途はんぱになっていて、約2カ月後の全日本選手権東京予選で山口一郎選手(明大、ペン裏ラバーの変化カット)に完敗した。全日本選手権に1回出たら、大学2年だし、教養課程は終わるし、あとは勉強して卓球をやめるつもりだった。絶対、全日本に出られると思っていただけに、敗戦のショックは大きかった。敗戦直後にいろいろな人がなぐさめてくれて、スポンジはカット打ちがむずかしすぎるからやめるように忠告してくれたが、それらの言葉には頑なに耐えた。だが、いつも胸を借りていた渡辺さん(大正大)に、「荻村さん、あれだけ一生けんめいやったのにね」と、やさしい声でいわれたら、とたんに泣けちゃってね。卓球を始めてから負けて涙がこぼれたのは、これが二度目で最後だった。これで卓球をやめようと思っていたのが、きっかけを失ったので、やめられなくなった。またやり始めた。もしこのとき全日本に出られていたら、多分、卓球をやめていただろう。
3."笑を忘れた日"以後、急速に伸び
―そのときですか。"笑いを忘れた日"と日誌に書いたのは?
●カット打ちのコツをつかむ
そうそう。それからは形相が変わった。死にもの狂いになって...。カット打ちが課題と悟った。なにしろ、ふつうの打ち方では3本とつづけられなかったのだから。10ミリのスポンジだったからね。雲仙のときはツッツキを捨てて既成のカット打ちを受け入れようと考えたが、こんどの場合は根本的に考え直して、絶対に正確な判断をくだすためにはどうすべきかを考えた。その結果、ショートスイングで球が手もと近くへ来てから肉眼で回転を見てから振ろうという考え方が出てきた。素振りのスイングもそのように変えた。カット打ちでねばる場合、ボールにラケットが当たった瞬間の角度が残像となって目に残っていないといけない。でないと、チェックできない。そういうことが、ちゃんとやれれば、後半になればなるほど打てるという考え方。あそこまでやれば、カットは絶対に打てると思うけどね。ソフトよりはるかにカット打ちのむずかしいスポンジであったから、最初はとにかく3本とつづけて打てなかった。だから、山口選手に負けたときも、いろいろな先輩にスポンジをやめたらどうかといわれた。そのとき思ったことは、誰がやってもこれ以上はできないというところまでやって、それでもなおかつスポンジではカットを打てぬと結論できるならあきらめる。だが、そこまで努力していないので、スポンジで進もうという考え方を変えなかった。そういう経験があったから、田中利明君(日大で1年後輩)が裏ソフトで途中迷ったとき、どうしようかと相談を受けたが「とことんまでやってみたらどうか」という言葉が出てきたと思う。深刻な経験に裏づけられた言葉は重い。人の言葉の重さをはかれる人は素質があるといえようかね。
―"笑いを忘れた日"を境にして、卓球に賭ける気持ちが非常に強くなったわけですね。
●やるからには、人生を賭けて
やるからには人生を賭けてやる。だから、一瞬もムダにしてはいけない...。前からそういう性格だったけど、ますますそういうふうになった。よく「卓球をやって昼飯を賭けよう」という人がある。その方が真剣にやれるからといって。だが、ぼくは絶対賭け勝負をやらなかった。「オレはもっと大きなものを賭けているんだ」という気持ちがあったので。自分の全部を卓球に賭けているという気持ちがあった。それ以上、小さな刺激は必要なかったといえる。私のやろうとしたスポンジの技術・戦術には先輩がいなかったし、私と同じ時間をかけない人には私の考え方の理解できない場合が多いのは、やむを得ないことだった。"百万人といえども、われ往かん"という言葉が好きだった。そうした気概はまったく生意気だが、ロンドン大会でさんざんいじめられても頑張りとおす気概にもなった。
―昭和28年4月に都立大から日大へ転校されたわけですが、あの頃にアジア選手権代表候補合宿が数回あった。荻村さんは全日本選手権に一度も出ていない、軟式選手権をとった程度で、19人の候補選手のワクの中に19番目で入っていた。「たいしたことのない選手だろう」と、最初は思った。ところがあの合宿で見る見るうちに強くなって、数カ月後のアジア選手権では団体戦のメンバーに入り、大活躍。全くスイ星のようなデビューぶりでしたね。
●スイ星のようにデビュー
全日本軟式、硬式、世界、とすべて初出場の優勝でしたね。アジア選手権の合宿は19人中19番目だったが、3回の合宿を終わったら田舛吉二選手(故人)に1敗しただけだった。基本の蓄積があったので、多くの一流選手と触れ合う合宿の刺激の良い面の効率が高く、上達が早かったのだろう。日大へ帰ると、そのたびに強くなったといわれた。あれだけ足の速い選手は、まで出ていないのじゃないかな。世界選手権へ出るまでに、平均1日5㎞走ったとして最低7000㎞ぐらいは走っている。なわとびは両足そろえてつま先でとぶのを1000回1セットとして毎日1~2セットやった。うさぎとびやシャドープレーもやったし...。しょっちゅうではないが、ただ立ったりしゃがんだりを2000回やった。これも実によいトレーニングだった。試合前にシャドープレーをやってから試合に出ると、すごくよかったね。卓球選手のウォーミングアップとしては非常にいい。なわとびのおかげで、ほとんどツマ先で試合をやった。ロンドン大会のとき、ぼくのフットワークを"焼けたトタン屋根の上のネコ"と向こうの新聞に出た。
●短期間でなぜ上達したか
卓球を始めて3年半で全日本軟式、5年で全日本、5年半で世界で1位となったが、足の速さ、敏しょう性、持久力、など体力の蓄積は相当あった。それは生まれつきもあるが、大半はすでに述べたように訓練によるものであった。こういった体力の蓄積があったことと、自分の体力の特徴を生かしたプレーをしたこと、常に創意工夫をしたことが、短期間で上達した原因と思う。渡辺重五さんは関学へ入ってから卓球を始めて、日本一(昭和12)になったそうだ(その前は剣道をやっていた)が、それを聞いてはげましになったね。
4.高い頂点と長い選手生活
●コーチに反対された"51%理論"
ロンドン大会の前のこと。"肉を切らして骨を切る"戦法はロング戦ならいいが、カット打ちはどうか。前々年(昭和27年)にバーグマン、リーチが英国から来日し、日本選手が負けるのを見ている経験からして、持久戦になれば最後は1本勝負になるだろう。そうなると、運を天にまかすだけ。そこで運を天にまかすなら、もっと早い時機に率のよい方法はないのか。そこで考えたのが、"51%理論"。得点率100%の球を51%命中するチャンスがあれば、のがさずスマッシュしていけば勝てる。自分もバーグマンもねばる球は絶対にミスをしない。だから、スマッシュが入れば抜けるという場合に、入る確率が51%ならスマッシュしていこう、という考え方。この考えなら、ネットと同じ高さのボールか、ネットよりも少し低くても全力スマッシュできるのだ。これには一つの前提がある。自分にはプレーボールの瞬間からゲームセットの瞬間まで絶対に精神的動揺がない、ということ。それだけのことを言い切る生活を積んできている、と確信をもっていえること。この"51%理論"はコーチの人たちに受け入れられなかった。だが、ロンドンではそれをやって成功した。トレーニングは最高の速さを常に想定して、球の速さに負けない動きを身につけることと、その速さでの持久力の強化をはかった。
●体力の特徴を生かした要撃法
戦術的にヒントになったものにフェンシングの本に出ていた"要撃法"(ようげきほう)をとり入れた。しかし、自分のものは要撃でなければならぬと考えた。要撃とは、待ちぶせしてたたくこと。ふつうの攻撃システムは全部自分の有利な状況で展開してゆくが、要撃法の場合は相手が十分に返せそうな所へ1発打って、むしろ相手が得意のボールを打った時、それを待ってもう1発たたく。その方が相手のダメージが大きい。そういう考え方だ。この考え方の私のプレーをとり入れたのが、中国のクロス打ち戦法だと思う。その基本となるクロスの強打対強打―相手に低い球をスマッシュさせて、それをたたき返す練習―をよく田中とやった。また、田中か角田さんぐらいしか、そういった練習のやれる人はいなかった。
要撃法のラリー展開の場合、最初の1発を相手がやっと返すだけでなく、相手も思いきり打ってきてもよい。そのために相手の余力が90にさがったとすれば、自分の余力は99。スタミナとか敏しょう性が悪ければ、相手が加速度的に消耗していく。それを計算に入れた戦術だ。最初から自分が入るか入らないかわからない所へねらわなくてもよい。体力的には自分の方が上だということを計算に入れた自分中心の要撃システムである。
これを研究したあと、それから特定の相手のための要撃システムを考えた。対シドとか対アンドレアディスとか。
―プレーヤーとしての荻村さんを見た場合に、全盛期の頂点(強さ)が高かったことのほかに、もう一つ大きな特徴がありますね。それは30代まで活躍したこと。昭和29年のロンドン大会へ21歳で参加して以来、32歳(昭和40年)まで世界選手権でプレーヤーとして活躍された。30歳の日中対抗では李富男と徐寅生を破って日本が公式戦で1960年代に初めて中国を破る殊勲者となった。そして翌年のプラハ大会では王家声(中国)を破り、日本選手としてただ一人男子シングルスのベスト8に進み、張(中国)と2-3の接戦をしている。日本では大学を卒業して2年ぐらいすると、第一線から消えていく選手が多いが、このように30代まで活躍できた原因は...?
●30代まで現役で活躍の秘けつ
一つの原因としては、自分の身体条件の変化、その時代時代の相手になる選手・技術の傾向に合わせてプレーを変えられたこと。具体的にいえば、'54年(昭和29年)8月の旭川国体で右足にけいれんをおこし、足がダメになって速攻ができなくなった時点で、オールラウンドプレーに切りかえたことが一つ。第二は'59年(昭和34年)にスポンジ禁止となったとき、裏ソフトに転向して、田中のプレーを荻村的にやれたこと。ループドライブが流行したがループをある程度使えたことと、なんとか返せたこと。ループが返せなくて急に消えていった選手が多いが...。国際的にはそこで中国が出てきた。カットサービスからの3球目攻撃とか、ある程度得点源になるものをやりながら、ロビングとかカットとかプッシュとか補助技術をふやした。いまの日本で勝つことだけを考えるとすれば、ショート主戦でやるのがよいと思う。ショート+トップ打ちでね。伊藤とか長谷川に勝つには、一番それがいいから。
しかし、身体文化であるスポーツの場合、"人間能力の限界への挑戦"という目標の方が、"時代の選手に勝つことの工夫"という目標よりも、はるかに高い。長つづきは、高い目標への努力の副産物であったし、それ自体は目標としての価値は低い、と思う。"時代の選手に勝つ"という低い次元の目標にとらわれると、もしその時代の選手のレベルが低い場合、低いところで自己満足することがおこる。いま、そんな傾向もあるような気がする。ある程度は運もある。私の場合は恵まれていたともいえる。こんな選手はもう出ないだろう、と思われるすごい選手が世界にいたし。'52年(昭和27年)の日英大会で私の心に偶像が完全になくなったこともよかった。それまで、藤井さんは私にとっても偶像であった。(編集部注:この日英大会で藤井選手はバーグマンに2-3で敗れた)
長くつづけたこと自体にどれほど価値があったかは疑問だが、後輩に刺激を与えた点では価値があったと思う。私たちが伸びてくるまで佐藤、林、藤井さんらが現役でやってくれたことに私自身はすごく感謝の念をおぼえた。
しかし、そのときそこにあるものからしか学べない者もたいしたことはない。若者には、"古人のあとを求めず、古人の求めんとせしものを求む"精神が必要だからだ。本当は頂点の期間がもっとつづいたはずなんだけれども、足のけいれん、つづいて黄だんのためダメになった。それと年齢的なこともあって、裏ソフトになってからは、台からさがる卓球になっていた。人間、ロングマンなら、足が速くなけりゃ、前についていられないよ。
―長くつづいたもう一つの理由は、節制をしたということもありますね。
そうだね。節制をしたが、若いときはよくたべた。焼き鳥を100本ぐらいたべたことがある。
(2000年1月号掲載)
[卓球レポートアーカイブ]
「世界一への道」荻村伊智朗①プレーヤーとしての生い立ち
2017.02.13
\この記事をシェアする/