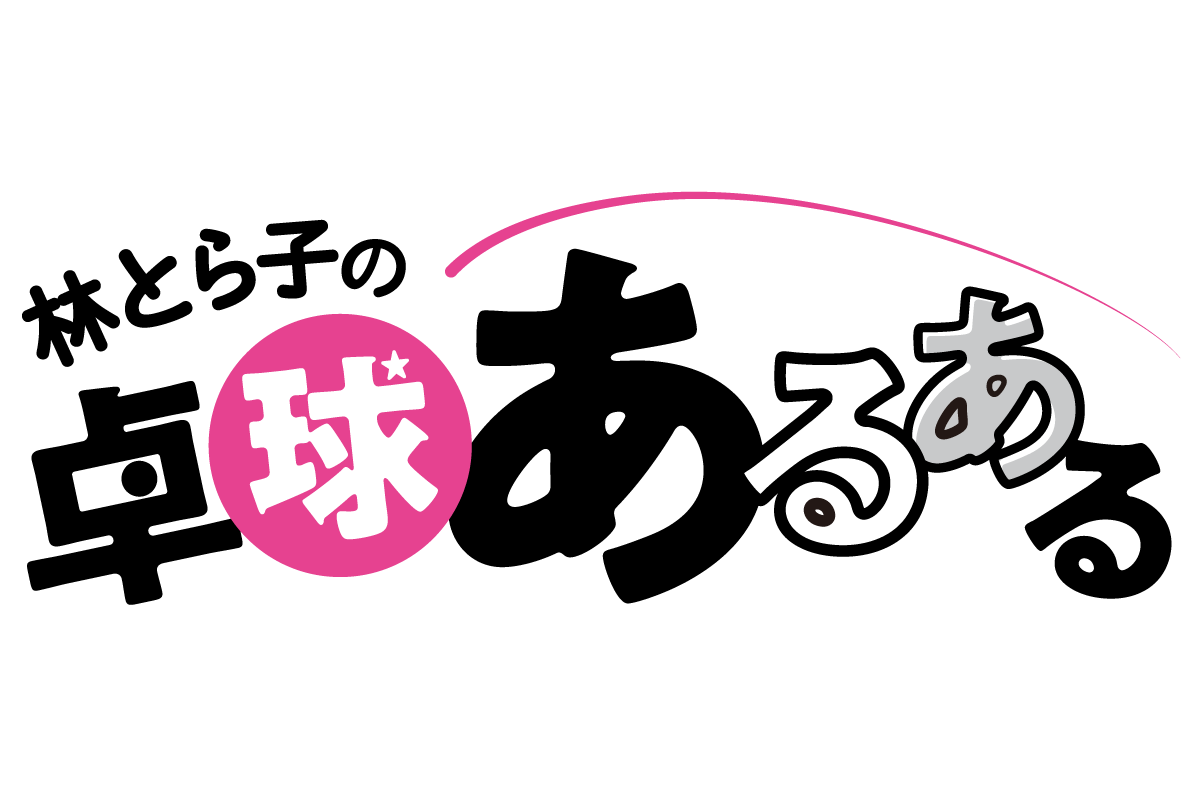普段はおとなしい性格でありながら、内には強い意志の力を秘めていた小野誠治。
初出場の世界選手権大会で、見事世界チャンピオンに輝いた。日本から誕生した12人目の世界チャンピオン・小野誠治。彼に続く日本人世界チャンピオンは、いまだ現れていない...。
彼の放つ横なぐりのスマッシュは、その切れ味の鋭さと破壊力から『カミソリスマッシュ』の異名で呼ばれた。
これは、現在日本から出た最後の世界チャンピオン・小野誠治の物語である。
今からちょうど25年前の1979(昭和54)年。朝鮮民主主義人民共和国で第35回世界選手権ピョンヤン大会が開催された。大会最終日の男子シングルス決勝戦終了後、コートから去る誠治の胸には、世界一になった喜びと支えてくれた人々への感謝の気持ちが込み上げていた。あふれる涙を右手でぬぐい、高島に支えられながら左手を上げ、会場の盛大な拍手を全身に受ける誠治の姿がそこにあった。
1979年5月6日、22歳で彗星(すいせい)のごとく世界の舞台に現れた小野誠治は、卓球王国と言われる中国の4人の選手を次々と倒し、世界の頂点を極めた。
「誠ちゃん、誠ちゃん、早(は)よ起きんかな、迎えに来てもろたで」
今朝も母の声が響いた。
愛媛県西宇和郡三瓶町、海と山に囲まれた小さな町で、誠治は生まれ育った。小学生の誠治は魚釣りが大好きで、休みの日の朝はいつも、友達の三好、松岡と一緒に釣りに出かけていた。朝が苦手だった誠治は、母に起こしてもらうのが常だった。3人でエサのゴカイを取りに行き、いったん帰って朝ごはんを食べ、再び釣りに出かけた。誠治は魚釣りが得意で、エサなしでも器用に釣ることができたほどだった。
誠治の体型は色白でひょろっとしたやせ形だったが、反射神経が良くて肩が強かったので、ソフトボールや野球などの球技も得意であった。中学校に入ったときに野球部に見学に行くと、誠治がピッチャーマウンドから投げたボールが非常に良かったので、野球部に勧誘されたほどである。そんなふうにいろいろなことをして遊んでいた少年時代、誠治はひょんなきっかけから卓球と出合うこととなる。
スリむげノータッチ
誠治が小学2年生のときだった。そのころ珠算を習うことがはやっていて、誠治も叔父が経営している珠算教室に通い始めた。その珠算教室には卓球台が1台あり、早く行ったときには卓球をすることができた。ここで誠治は遊びで卓球をやり始めた。これが誠治と卓球というスポーツが出合ったきっかけであった。
指導者などおらず、みんながやっているのを見よう見まねでやっていた。卓球をやりたい子どもがたくさんいるのに、台が1台しかない。その問題を解決するため、そこでは特別なルールが採用されていた。
10本1ゲームの勝ち抜き戦で、3本連続得点、または1本ノータッチで抜くことができたら勝ちというものであった。3本連続得点できなかったり、ノータッチで抜くボールが1本も出ないまま、どちらかが10点に達してしまった場合、2人とも交代しなければいけない。これを『スリむげノータッチ』ルールと呼んだ。誰が考えたのかわからないが、伝統のルールらしい。『スリむげ』というのは「3本連続で取る」という意味である。
「1本いいボールが入ったら、ずっと台について卓球ができるんだ!よーし、相手が取れないようなボールを打ってノータッチで抜いてやるぞ」
誠治の胸は高鳴った。そして、自分の打ったボールがノータッチで抜けたとき、全身に快感が走った。この快感が後に『カミソリスマッシュ』と呼ばれる誠治の必殺スマッシュを生み出す大きな要因となった。
誠治の家族は卓球とは無縁の生活を送っていた。父は会社員、母は自宅で小さな雑貨屋を営んでいた。姉もまた、まったく卓球とはかかわっていなかった。まさか誠治が卓球の世界チャンピオンになるなど、誰も夢にも思っていなかったのである。
三瓶東中学校へ入学
中学生になった誠治は、野球部と卓球部のどちらに入ろうか迷った。誠治は野球も大好きだったのだ。しかし、スマッシュが入ったときの爽快(そうかい)感に(ひ)惹かれ、誠治は卓球部入部を決めた。親友の三好、松岡も一緒に卓球部へ入部することになった。
練習場所は講堂か教室で、卓球台は2台、部員は1~3年生を合わせて20名くらいだった。1年生の誠治たちはボール拾いをし、打たせてもらえる時間は少しだった。入部したばかりで誰もが球をたくさん打ちたい時期であるが、誠治たち1年生はボール拾いの毎日で、じっと辛抱して先輩の練習を見ていた。しかし、誠治たちにはそれが普通で、厳しいともなんとも思わなかった。むしろ、そうして先輩たちの練習をしっかり見ることが「見取り練習」となった。
こうして、知らず知らずのうちに、誠治には辛抱強さと人の練習から良いところを学ぶ能力が身についていった。
熱意
顧問の岡本はとても熱心で、いかなるときも練習に顔を出してくれた。誠治はその熱心さに打たれ、「自分もがんばらなければいけない」と感じたのであった。もし、熱心な先生でなければ、誠治は一生懸命さに欠ける選手になっていたかもしれない。
卓球は雨が降ろうが雷が鳴ろうが天気に関係なく練習ができるので、部活動が休みになることはめったにない。誠治も普通の中学生だったので、きつくて練習を休みたいと思うときもあった。しかし、誠治は先生が選手に接するときの熱意に心を打たれ、練習をサボることなど1度もなかった。
練習内容
学校での練習はほとんどが基本練習だった。まずはフォアラリーをノーミスで往復100回。これは、15分以内に往復100回できるかという練習だった。そして、先生の決めた課題練習。課題練習といってもやはり基本練習で、フォアとバックのラリーをクロスとストレートで続ける。その他はフォアとバックの切り替え、ツッツキ、3歩動のフットワークなどだった。
また、練習メニューには素振りも欠かさず組み込まれていた。狭い廊下でフォアハンドの素振りを300回行う。これは、合計300回になるように、1人10回もしくは20回ずつ、順番に数を数えていった。卓球では、基本をしっかり練習してイージーミスをなくすことが重要である、ということを考えての練習メニューだった。
1日3時間くらいの練習に加え、トレーニングも行った。近くの山まで競争したり、腹筋、腕立て伏せなどをしたりした。家に帰ってからも、砂を詰めたコーラ瓶で手首を鍛えたり、部屋の畳の上でボールの回転の研究をしたりしていた。
誠治は練習が好きでたまらなかった。卓球の専門誌を読んで、左利きの特長を生かせるように、左にシュートして流れ落ちるドライブを考え出し、練習していた。このように技術的なことも自分で考えるようになっていたのだ。
こうして力をつけていった誠治は、1年生後半のころから2年生の生徒と互角の試合ができるようになった。同級生の松岡、三好と一緒に卓球の練習にも熱が入り、2年生のときには地区大会で優勝し、県大会へ出場した。
三瓶町では毎年、正月の2日に「内宮杯」という町内大会が開かれ、中学生が大人と試合をする機会があった。誠治は大人と試合をする機会があった。誠治は大人たちの中に混じってもまれる中で、サウスポーから繰り出される変化ドライブを身につけ、試合でよく使うようになった。指先が器用で手首がしなやかな誠治は、サービスの回転にも工夫を凝らした。そして、ドライブとサービスにおいては、県下に通用するレベルの技術を持つようになっていった。
敗戦のショック
愛媛県の中でめきめきと力をつけていった誠治は、1971(昭和46)年の中学最後の夏、松岡と組んで県大会の団体戦に出場(このころの団体戦は2人団体だった)。2人は見事優勝し、全国大会への切符を手に入れた。
そして、県大会個人戦。誠治かもう1人の選手が優勝候補だと言われていた。誠治はその選手とベスト8決定戦で当たることになった。1ゲーム目を取り、2ゲーム目を奪われ、ゲームオールでベンチに戻った誠治に、顧問の岡本はこうアドバイスした。
「負けてもいいから、思いきって試合をしなさい」
このアドバイスには誠治をリラックスさせようという意図があった。しかし、誠治はその言葉を真に受け、「負けてもいいのかぁ」という気持ちを持ってしまった。本当は勝ちたくて仕方がないのだけれど、楽な方へと気持ちが逃げてしまったのだ。そして試合は終わった...。
勝ちたい、勝てるものだと思っていただけに、負けたショックはとても大きかった。負けず嫌いの誠治は、自分に腹が立って仕方なかった。すっかり自信をなくして落ち込んだ誠治は、家に帰ってくるなり部屋に閉じこもり、1人でしょげていた。すると、両親はこう言った。
「そんなんやったら、卓球やめてしまえ、試合に負けてショック受けて落ち込むんやったらやめてしまえ」
この言葉を聞き、誠治の中で何かが吹っ切れた。
「ああ、そうか。結果も大事だが、もっと大事なのは一生懸命やることだ。おやじやおふくろは結果がほしいわけじゃない。自分の一生懸命な姿を見ていたかったのだ」高校生になっても、大学生になっても、社会人になっても、誠治は家で卓球のことを話したことはほとんどなかった。また、両親から「卓球、がんばっているか」というふうに聞かれたこともなかった。両親はただ、「体は大丈夫か、しっかりたべているか」といったことを聞くだけだった。
「自分にプレッシャーを与えないようにしてくれているんだ」
後に誠治はこの親心を本当にありがたいと思うようになった。息子が試合しているのに気にならないわけがない。しかし、余計なプレッシャーを与えまいと、一言も聞かないのだ。「おやじやおふくろを悲しませたらいかんなぁー」と、誠治は深く心に刻んだ。
全中出場
全国中学校大会は東京の中野区立体育館で行われた。団体だけに出場した誠治たち三瓶東中は、2回戦で金光学園(岡山)に敗れた。しかし、全中出場という経験により、強くなりたいという気持ちが誠治の中でさらに大きくなっていった。
誠治は「強い者が勝つ」のではなく、「勝った者が強い」という受け止め方をしていたので、自分の負けを何かのせいにはしなかった。「次は自分が上回るようにがんばろう」と前向きに考えていた。
大会の2日目には元世界チャンピオン長谷川信彦の指導があり、さらに刺激を受けることとなった。
3学期になり、進路を決めるときがやってきた。愛媛県で名の知られていた誠治は、いくつかの高校から声がかかった。しかし、すでに誠治の心は決まっていた。地元に三瓶高校とう県でベスト4に入る学校があった。三瓶高校の卓球部はOBの内宮という人物の指導を受けており、その内宮は中学校にもたびたび指導に訪れていた。内宮という指導者の下で励むべく、誠治は三瓶高校に進学することを決めていたのだった。
三瓶高校入学
1972(昭和47)年4月、誠治は三瓶高校に入学した。高校での練習は中学校以上に厳しく、休みがほとんどなかったが、誠治にはまったく苦痛ではなかった。それほどに卓球が好きになっていたのだ。
顧問の山本はとても理解があり、遅くまで練習をさせてくれた。学校は高体連以外の試合の出場を認めないなど、部活動に対して厳しかった。しかし、山本は学校側がメジャーな野球部だけ特別扱いしようものなら、「どの競技だって同じや!」と職員会で主張してくれるような先生だった。
また、OBの内宮が熱心に指導をしてくれた。内宮は三瓶の卓球の発展に貢献した人物で、「内宮杯」の名前も彼の名前を冠したものである。内宮は夕方になって勤務が終わると高校に顔を出し、土日も指導に来てくれた。このように、田舎では珍しい恵まれた環境の中で、誠治は思いっきり卓球に取り組むことができた。
練習内容は主に体操、基本練習、フットワーク、課題練習、ゲームで、土日は多球練習だった。練習時間は午後3時半から6時くらいで、うち30分間がトレーニングであった。また、試合であがらないために、度胸づけとして歌を歌わされることもあった。「30秒以内に歌わないと曲が増える」「童謡は禁止」など、おもしろいルールがあった。これには、練習に休憩を入れるという効果もあった。
卓球部は遅くまで練習していたので、苦情が来ることもあった。そんな中で部員たちは、「勝って文句を言わせないようにしよう」と、逆にやる気を出していた。
「県で優勝するぞ!」
これが誠治たちの大きな目標であり、その実現のために必死で練習をしていた。このころはもちろん世界など頭にはなく、県大会優勝を目指す、ごくごく普通の卓球部員であった。
全日本ジュニア愛媛県予選会
そんな誠治に大きな転機が訪れる。1973(昭和48)年、高校2年生のときの、全日本選手権大会ジュニアの部でのベスト8入りである。
しかし、その道のりは予選から険しいものだった。全日本選手権大会ジュニアの部の県予選会は、ちょうど三瓶高校の運動会と重なっており、「学校行事を優先する」というのが三瓶高校の方針だった。誠治はとても残念だったが、心の中では「全日本選手権大会ジュニアの部に出場してもどうせ勝てないだろう、もう仕方がない」というあきらめの気持ちもわいていた。
ある日、誠治は父にポツリと言った。
「予選会が運動会と重なっていて、試合に出られないんだよ」
すると、普段は卓球に関して静かに見守るという態度でいた父が、思わぬ行動に出てくれた。「卓球部は試合を優先してほしい」と、学校に嘆願に行ってくれたのだった。長い話し合いの末に、とうとう学校側は承諾した。ただし、それには条件があった。顧問の山本は運動会のため引率できないので、保護者同伴で愛媛県予選会に出場するというのがその条件である。
試合には父が仕事を休んで同伴してくれることになった。父が自分のためにこんなに一生懸命力を尽してくれたことが、誠治には本当にうれしかった。そして、父の期待にこたえるかのように、誠治は愛媛県予選会で見事優勝し、全国大会に出場できることになったのである。
全日本選手権大会ジュニアの部ベスト8
「全国大会に行ける」
そう意気込みすぎたのか、誠治は試合の前に不注意にも風邪をひいて寝込んでしまった。なんとか出発2日前に熱は下がったのだが、練習もまったくできておらず、風邪も完治していなかったので、試合に行けるかどうかもわからない状況だった。しかし、誠治は思った。
「いろいろな人のおかげでこうして試合に出られるようになったのだから、自分は行かなくてはいけない」
顧問の山本は授業があったので、またもや父が仕事を休んで保護者として同伴してくれることになった。
大会の前日は会場で練習ができたので、当然ほとんどの選手が会場で汗を流していた。しかし、このとき誠治は正直、試合に勝てるなどとは思っていなかったし、まだ風邪気味だったので、練習はせずに父と2人で東京タワーに登った。
試合の当日、会場の駒沢体育館に入った。誠治は不思議にも1回戦、2回戦と僅差(きんさ)で勝ち抜いた。ベンチコーチに入っていた父は卓球のことはほとんどわかっていなかったが、誠治はなんだか心強く感じていた。
3回戦の相手は、優勝候補の筆頭、熊谷商高の松井だった。1~2回戦を勝ち続けたことで誠治の調子は上がっていた。ラケットを振れば何でも入るような状態で、ここでも思いもよらない勝利を収めた。無名の誠治が優勝候補に勝ったことで、会場にいささか動揺が走った。熊谷商高の応援席からは「相手はさんぺい(三瓶)のやつだって」というような声が聞こえ(正しくは「みかめ」)、相手の監督はすぐにその場を立ち去ってしまった。
このとき、父は素直に自分の息子の勇姿がうれしかった。こうして誠治は松井に勝ち、ベスト16に入った。
次の相手はカット主戦型だった。しかし、誠治はカット打ちが下手だった。なぜなら、三瓶高校には、いやそれどころか三瓶町には、カット主戦型が存在しなかったからである。当然、誠治にはカット打ちをする機会がなかった。しかし、ツッツキをうまく混ぜたのが効いて、信じられないことにゲームオールでまたもや勝ってしまった。なんとベスト8に入ったのだ。
迎えた準々決勝では、1ゲーム目を先取してベンチに戻った。しかし、「2ゲーム目を取ったら表彰台に登れるなぁ」と言っていたら2~3ゲーム目を連取され、あっさりと負けてしまった。
こうして、誠治の高校2年の、全日本選手権大会ジュニアの部は幕を閉じた。
全日本選手権大会ジュニアの部ベスト8という成績は、誠治にとって大きな自信になった。そして、熊谷商高の松井に勝ったことで、大学でも卓球をがんばりたいという気持ちになった。
もし予選に出場できていなかったら、このような成績を残すことはできなかった。大学にも行かず、就職していただろう。誠治は父に深く感謝した。父の行動力によって、誠治は卓球という人生のレールに乗ることができたのだから。
経験という財産
全国大会でベスト8に入ることができた誠治は、高校生の訪中遠征の際、日本代表の一員に選ばれた。北京の首都体育館という約1万8千人入る体育館で、誠治は中国選抜の高校生と試合をすることになった。会場があまりにも広く、観客数も多かったので、誠治は緊張で頭が真っ白になった。試合は簡単に負け、握手をしたことしか覚えていないほどだった。
しかし、この経験が後の誠治の卓球に大きく影響を与えることになる。誠治はこれ以後、試合で気持ちが引き締まるような良い意味での緊張はしても、何も考えられなくなったり、体が動かなくなったりというようなことはなくなったのだ。経験はとても大きな財産である。
のちの世界選手権大会でもこの経験が生かされることになろうとは、このときは知る由もなかった。
(2004年7月号掲載)