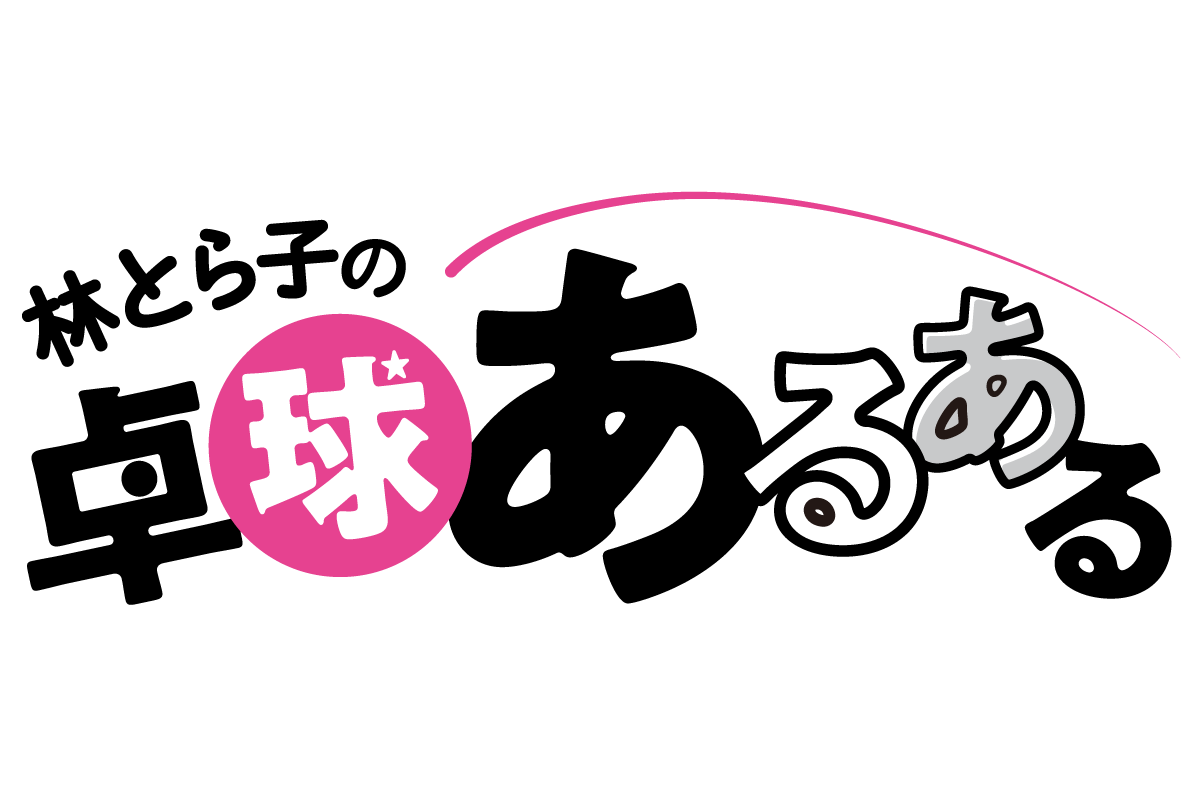「丸いラケットを見るのも嫌」というほどカット主戦型との対戦を苦手とした深津尚子。そのカットを克服するため、当時の女子選手としては革新的だったドライブに挑戦。時代の先端を切り、ループドライブを一級の武器にまで高めた。20歳の若さで世界チャンピオンに輝いた深津尚子は、60年代をひたむきに駆け抜けたきら星だった
料亭の女将
香川県高松市にある老舗料亭「二蝶」。この有名料亭の女将が今回の主役、第28回世界選手権大会女子シングルス優勝の深津(現姓・徳永)尚子だ。
「二蝶」は創業59年余り。宇高連絡船が四国と本州を結んでいたころからの老舗である。「高松に料亭二蝶あり」といわれるほどの高級料亭だ。
玄関を入るとすぐにトロフィーやメダルや賞状、そして卓球の写真が飾られている。写真の中で、1番大きなトロフィーを持っているのは、若き日の女将、1965年世界チャンピオンの深津尚子だ。
あこがれの風景
昭和19(1944)年12月23日、深津は愛知県岡崎市の紡績業を営む家庭に生まれた。7人きょうだいの末っ子で、多くの女子工場従業員にも囲まれ、にぎやかな環境で育った。長兄とは23歳も年が離れており、その娘や息子(深津にとっては甥や姪)と年が近かったせいもあり、遊び相手はたくさんいた。しかし、そうしたにぎやかな環境の中で、深津はどちらかというとおとなしい子どもであった。
小学校時代、下校時に中学校の体育館をのぞくのが、深津の日課だった。深津の通う奥殿小学校は、香山中学校に隣接している。体育館には6台ほどの卓球台が並び(当時、これほどの卓球台が並んでいる体育館は珍しかった)、卓球部の練習が行われていた。この風景が、深津と卓球との出合いだった。
香山中学校は3学年合わせて5クラスほどの、小さな中学校だった。しかし、その小さな中学校の卓球部は、県大会で準優勝という成績を挙げていた。学校では、もちろん卓球部が1番人気だった。
先輩たちの美しいフォーム、楽しげなラリーに、深津はあこがれた。そして、ラケットを握ったこともないのに、小学6年生のころから「中学生になったら卓球部に入ろう」と心に決めたのだった。
城殿先生
中学校に入学すると、深津はすぐに卓球部に入部した。今まで先輩の卓球を体育館の外から見ていることしかできなかったが、やっと自分もボールを打つことができる。授業が終わると、毎日一目散に体育館に駆けていった。
中学校の卓球部で、深津は素晴らしい指導者と巡り会う。卓球部の顧問、城殿輝雄だ。城殿は、深津にとって最初の指導者だった。以後、高校、大学、日本代表監督など、数々の指導者と出会うことになるが、それらの出会いについて深津は「とても幸運だった」と語る。
城殿は戦時中に学生時代を送ったため、卓球の経験はなかった。しかし、「子どもたちに自信を持ってほしい」「子どもたちを力づけてやりたい」という一心で、独学で卓球を学び、毎日一生懸命指導に当たった。
深津はとても素直な生徒だった。城殿が指導したことをすぐに覚えてしまい、1週間ほどで先輩とラリーが続くようになった。その素直さのためなのか、他の生徒が何回も反復してやっと覚えるようなことを、すぐに理解して行動に移してしまう。次々と技術を習得していく深津を見て、城殿は「不思議で仕方がなかった」という。しかし、城殿は同時に「こいつはモノになるぞ」と感じていた。
しかし、深津には体力がなかった。ランニングをしても、後ろから数えた方が早かった。腕立て伏せは1回もできない。しかし城殿は厳しいフットワーク練習や、筋力トレーニングの類(たぐい)は一切させなかった。
「将来の世界チャンピオンを育てるという気があったのなら、必要だったかもしれないが...」
城殿は、教え子がそれほどの選手に育つとは思っていなかったのである。
城殿の願いは、とにかく生徒を試合に勝たせてやることだった。試合に勝つことで、自信を持たせてやりたかったのだ。そこで、試合で勝つためにてっとり早い方法として、サービスとレシーブ、3球目攻撃をしっかり練習させた。また、サービスに回転をかけやすいようにと、部員全員にペンホルダーラケットを使わせ、裏ソフトラバーを張らせていた。さらに、スナップを利かせやすいように工夫したグリップを教えていた。
こうした城殿の教えは、深津に最も適した戦型を授けることになる。
初めての大会
深津たち卓球部員は、城殿の下で卓球に打ち込んだ。城殿の周りには、卓球が楽しくて仕方がないという生徒たちが集まった。城殿は生徒をがんばらせる名人だった。例えば、試合会場で、他校の選手が素晴らしいラリーで練習をしているのを目にし、香山中学校の生徒たちがすくみあがる。そのようなとき、城殿は「大丈夫。試合をすれば必ず勝てる」と明るく励ますのだった。すると、安心して試合に臨むことができるせいか、結果はいつも城殿の言った通りになった。
1年生のとき、深津は西三河大会(団体戦)決勝で起用された。対戦相手は岡崎市の東海中学校で、後にインターハイで優勝し、専修大学で活躍する太田雅子がエースだった。卓球を始めてからたった3カ月目のことで、深津の力は団体戦メンバーに選ばれるほどではなかった。起用されたのは、「深津は将来伸びるから、負けても何かを得てくれるだろう」という城殿の配慮からだった。しかし、理由はそれだけではなかった。実は、裏の事情もあった。
城殿が試合前にオーダーを考えていると、偶然相手監督の生徒への指示が聞こえてしまった。
「太田、お前は2番で行け」
香山中学校に、太田に勝てる選手はいない。そこで、「どうせ負けるなら深津にやらせてあげよう」ということになったのだ。
結局、深津は太田に対して5点(当時は1ゲーム21点制)取るのが精いっぱいだった。あまりの実力の差に、試合中は「早く終わらないかな」という思いさえ浮かんだ。他の選手が勝ったおかげで香山中学校は優勝を飾ることになるのだが、深津にとっては卓球人生最初で最後の完敗となった。
散々なデビュー戦だった深津だが、2年生になったときには、岡崎市の男子が束になってもかなわないほどの力をつけていた。また、深津に限らず、香山中学校は城殿の下で全員が力をつけた。そして、西三河大会、三河大会、県大会と、すべての大会で優勝した(当時は県大会が最高で、全国大会はなかった)。
深津が3年生のときも香山中学校は完全優勝。さらに後輩たちもがんばり、深津が卒業した翌年も優勝。城殿率いる香山中学校卓球部は、深津が2年生のときから3年間、団体戦の公式戦で86連勝を達成している。
この道より我を生かす道なし
地元の実業団チームなど、城殿は深津たちを普段練習できないようなところへも連れて行った。新しい技術を習得するだけでなく、団結しようとする部員たちに大きな刺激を与えた。
また、「三遠大会」という試合もあった。三遠の「三」は三河(愛知)のこと、「遠」は遠州(静岡)のことで、愛知県と静岡県の中学生が出場できる大会だった。県内の大会しかなかった中学校時代に、外の世界も見ることができたのである。2人1組(2シングルス1ダブルス)の団体戦で、トーナメント方式で争われる。各校が何チームもエントリーし、総勢200チームを超えることもあった。
しかし、静岡と愛知の中学校を集めただけでは、深津に敵はいなかった。
城殿は語る。
「もしこの時代に『全中(全国中学校大会)』があったら、深津は優勝していたかもしれない」
全国にはどんな選手がいるのだろう。自分はどれだけ通用するのだろう。深津は自然と上を目指すようになった。
深津の強い意識は、意外なところから発見できる。ラケットである。
『この道より我を生かす道なし』
ラケットの裏に書いた一文は、武者小路実篤の「この道より我を生かす道なし、この道を歩く」から取ったもので、1つの道を極めることの素晴らしさを説いた名言だ。「教科書に載っていて印象に残ったから」と深津。卓球に人生をかけようとする気迫の魂が、この言葉に惹(ひ)きつけられたのかもしれない。
進学
全国大会に出るには、卓球の強い高校に進学せねばならない。そう考えていた深津に、うれしい誘いが来た。豊橋市にある桜丘高校からの勧誘だ。特待生扱いで、授業料を免除してくれるとまでいう。桜丘高校は当時から卓球が盛んで、後には松下浩二・雄二の兄弟など、一流選手を輩出する学校である。深津にとっては願ってもないありがたい話だった。
顧問の城殿は、この申し出を受けるように後押ししてくれた。しかし、深津の学級担任は反対した。学級担任は、学業成績優秀な岡崎高校を勧めたのである。
深津は学業の成績も非常に良かった。体力がないせいで体育の成績が悪くなるところを、筆記試験で点数を稼いで体育の成績表に「5」がついたといわれるほどだった。
「本気で卓球をやるなら桜丘だ」
「いいお嫁さんになるのも道だよ」
学校内で意見は二分した。しかし、最終的に家族は「自分が本当に進みたい道を選びなさい」と、簡単に認めてくれた。
桜丘高校の推薦入学試験を受けると、素晴らしい成績でクリア。「あの子、本当にうちに来てくれるんですか」と、桜丘高校の関係者が城殿に確認しにきたほどだった。こうして、晴れて卓球の名門校への進学が決まったのである。
しばらくすると、桜丘高校から荷物が届けられた。制服のプレゼントだった。「この優秀な生徒を手放すものか」と送ったのだろう。さらに、入学式では、深津が新入生代表として宣誓をすることになった。
桜丘高校
桜丘高校の練習。それは深津にとって「むちゃくちゃ厳しい」ものだった。中学校のころの比ではなかった。
授業後から遅くまでしっかり練習がある。部員全員が寮生活で、合宿や遠征が多かったのも、体力に不安のある深津にとっては厳しいことだった。
練習はすべて与えられたものだった。自分で考えてメニューを組むことはなく、決められた練習をただ必死にこなした。しかし今、深津はこう語る。
「もし自主性に任されていたら、自分はあの半分もがんばれなかっただろう」
深津は、卓球界の名門・桜丘高校卓球部で、「自分の限界」と引いたラインの倍も練習したのだ。深津はこうも語る。
「すべてのスポーツにいえるが、いくら効率のいい練習をしても、絶対量がなければ勝負の世界では話にならない」
こうして、中学までの「楽しむ卓球」から、「勝つための卓球」に切り替わり、さらにはその能力が世界へと向けられることになる。
松井先生
桜丘高校卓球部顧問の松井彊(つとむ)は、毎日つきっきりで部の面倒を見ていた。
深津が1年生として卓球部に入部したとき、松井は就任5年目。しかし、5年前まで、自身に卓球経験はなかった。
戦時中、北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)で暮らしていた松井は、北朝鮮の国技であるサッカーに力を注いでいた。父が小学校の校長だったため、運動場が庭のようなものだった。その後、終戦前に帰国すると、大学に入学して柔道を始めた。そして、4年間でめきめきと力をつけ、全日本学生柔道選手権大会に出場するほどに成長した。
当時は就職難の時代だったが、松井は柔道の師範の紹介で桜丘高校に就職。そして、教頭から予期せぬ依頼を受けた。
「うちは女子校(現在は男女共学)で、サッカー部も柔道部もない。新入生が卓球部の顧問を探しているから、やってくれよ」
新任早々の松井は断ることができず、生徒の熱意にも押され、とりあえず引き受けてみることにした。これが、伝統ある桜丘高校卓球部の誕生の瞬間だった。
そして、初めての試合出場。団体戦の地区予選は、初戦で第1シードの国府高校に完敗した。このとき、生徒以上に松井が悔しがった。
「やるからにはとことんやってやる」
しかし、何から手をつければ良いかもわからない。松井はその足で本屋へ行き、卓球の本を買った。
「日本で1番強い選手は誰なんだ」
そして、荻村伊智朗の名を知った。同い年であることも、松井の興味をあおった。松井はすぐに、荻村あてに長々と手紙を書いた。
「自分に卓球を教えてください」
「1週間預かってください」
すると、荻村から返事が来た。何と荻村は「いらっしゃい」と、快く引き受けたのだ。松井は10日間、荻村の練習、指導について回った。そして、技術に限らず、多くのものを吸収した。
その後、松井は卓球部に全精力を注いだ。練習環境を整え、コーチを呼び寄せ、自分に出来る限りを尽した。
そして2年後、桜丘高校卓球部はインターハイ出場を遂げた。1年生のときに初戦でボロ負けした生徒が、3年生の夏に成し遂げた快挙である。
当時の他校の監督は、松井をこう評す。
「松井先生は怖い。できないことをできないと知らず、生徒にやらせてしまうのだから」
顧問、コーチから見た深津
松井は、コーチとして高橋勝男を愛工大名電高校から譲り受け、いよいよ本腰を入れて選手育成に取り組んでいた。
初めのころ、松井と高橋の2人は、深津に対して疑問を持っていた。
「卓球は特殊なセンスが必要なのではないか?深津の長所はどこなんだ?」
深津は非力で、運動能力が優れているともいえない。その上、おとなしい性格で、勝負強いようにも思えなかった。
しかし、練習を始めれば、非常にまじめに取り組んだ。松井は、深津の内に秘めた闘志を感じた。
高橋は、深津に独特なショートを教えた。ラケットの先端を下げ、ラケットを縦に使ってボールを押さえつける技術だった。深津は中学校時代と同様、あっという間に身につけてしまった。そして、試合になると「ラケットを立てれば守備範囲が狭くなる」というデメリットも十分考慮した上での戦術を立てることができた。高橋は、深津の頭の良さに驚いた。
技も頭もエース。謙虚。
深津のそうした美点は、指導者たちにも影響を与えた。松井は、深津に「一目置く」ことにした。
「深津にいい加減なことは言えない」
深津は部員にも慕われた。卓球部全員が深津を軸に、量のみならず、質の高い練習に励んでいった。
全国大会出場
昭和35(1960)年の夏、深津は1年生の中でただ1人、インターハイのレギュラーに入れてもらうことになった。大城昌子、玉本征子(後に、専修大学、中央大学へ進学)という強力な先輩を擁する団体戦は、前評判通りの全国制覇を成し遂げることになる。
4シングルス1ダブルス形式の試合で、深津は全試合に4番で登録されていた。しかし、出番は1度もなかった。桜丘高校は決勝まですべて3-0、全戦ストレート勝ちの圧倒的な力を見せつけての優勝だったのだ。
松井が顧問になってから5年目、つまり創部5年目での全国制覇である。
この年の秋、深津は1年生ながら国体代表となり、少年女子の部で愛知の初優勝に貢献した。
深津の高校1年生時代は、自分でも「恵まれすぎている」ともらすほどだった。しかし、そんな深津は翌年、卓球人生で初めての挫折を味わう。
初めての挫折
高校2年生の夏、深津は極度の不振に陥った。インターハイの団体戦、深津はエースであるにもかかわらず、調子が上がらずに4番に下げられた。周りのがんばりで決勝までこまを進めたものの、決勝は山中道子(この年のインターハイ3冠)を擁する京都の華頂女子高校にストレート負け。連覇はならなかった。
団体戦は不本意な成績に終わり、残すは個人戦。しかし、不振に加え、技術的な問題も発生していた。
カット打ちができなかったのだ。
(2005年6月号掲載)