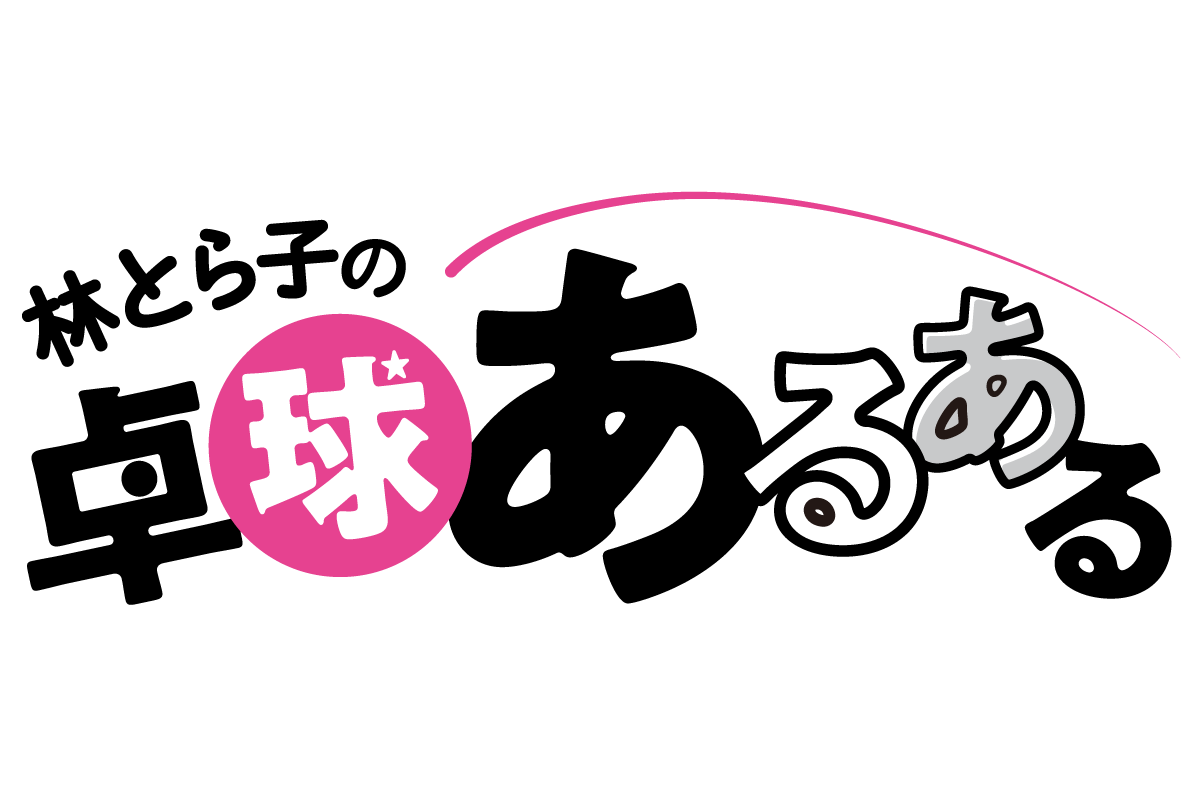第一章 わが卓球の創造 -選手、役員時代-
四 マラソン優勝と兵隊時代
昭和十六年の九月のある朝、私は新聞を見て強烈なショックを受けた。十月末から十一月三日にかけて、毎年開催されている明治神宮体育大会(今日の国体)から、野球、卓球など五種目が除外される、というニュースだ。早速関係方面でしらべてみて驚いた。卓球と庭球は柔弱なスポーツ、野球は敵国アメリカのスポーツ、ホッケーや重量挙げは国民的ではない、というわけだ。
私は厚生省の中川事務官と日本卓球協会の沼正治主事に手紙で猛烈にかみついた。再三の質問に沼さんから長いお手紙を頂いた。
「全国から沢山の問合せが来ているが、貴君にだけは返事を書かないわけにいかないので」という前おきがあった。
要するに、軍部がスポーツに口を出してきた、ことであるが、それを直接に表現できない手紙なのである。
二十一才になったばかりの若い私は、“卓球体育報国推進隊”というグループをつくり、自分たち卓球活動が国家的ではない、という軍部に対するゼスチュアも示しながら、「私の卓球道」という著書を発行、この中で体育報国の信念を述べた。そしてもう一つは、県下のマラソン(二十キロ、長距離断郊競走)への出場であった。
私は身体は小さいし、頑健ではないが、柔弱なスポーツと云われては黙っているわけにはいかないのである。当時私は卓球のため、毎日のように二、三千メートルくらいは走っていたし、長距離には少しは自信があった。しかし五千メートル以上走った経験はなかったので、陸上の専門家にまじって二万メートルを走ることは作戦など立てようがなかった。なるべく早目にトップに立ち、あとはがんばり抜く、という作戦だった。
約六十名の走者でスタート、約四キロぐらいのところで私はトップに立った。その時、わき腹が痛み出し、キリでさされるように激しい痛みになってきた。これでやめようか、と思ったが、「優勝か死か」という覚悟で出場したんだからやめられない。苦しいのをガマンして走っていたら、二キロぐらいで痛みがとれてきた。しかしトップの私のあと二メートルの差でぴったり一人ついてきており、決して離れない選手がいた。その人はあとで聞いたところ、全国四位になったことのある下関市の選手だった。
あと一キロという時にも離れていない。私は何とか離そうともがいてみたが、マラソンというものは中間の走路でがんばってみても、スピードが出ないものだ。十五キロ前後で急な坂を上り、下り坂を過ぎ、いよいよ最後の一キロは私の郷里柳井の町へ入るわけで、最後は町の中をメチャ・クチャにがんばってみた。そしてゴールに入る前にあとを振り返ってみたところ、五十メートルくらい離れていた。
翌日の新聞は「卓球の田舛が勝つ」という見出しだった。私にとってはまさに男子の本懐というところだった。自転車で伴走してくれた卓球の後輩たちも泣いて喜んでくれた。ただし、ゴールに入って自分の足を見たところ、はいていたマラソン足袋の底は抜けており、両足とも指のつけ根が切れて血が流れていた。
このマラソンには翌年も、奈良市の勤務先から夜行列車で帰郷し出場した。再優勝したのである。
兵隊の方はどうか。すでに一年前、国民の義務である徴兵検査をすませていた。最後の検査官は「第二乙種合格!お前はもっと体を鍛えなければならん。何か運動をやっておるか」と質問した。私は「やっております。卓球です」と答えた。検査官(陸軍中佐殿)は「なに!卓球?そんなもん、運動じゃない!」というわけだった。
その翌年三月、教育召集(三カ月)で山口の連隊に入った。入隊日の夜、同じ班のある上等兵が私を呼びとめた。「卓球をやっていた田舛はお前か。軍隊はシャバとは違うぞ」と凄んだ。どうも日本の陸軍は卓球をバカにしていた。海軍の方は少しちがった、と思う。
山口県徳山市に海軍燃料廠があった(現在の出光興産の場所)。」そこの卓球部長の石井中佐は大変私を可愛がってくれていた。また日本の三大軍港の一つ、呉市の海軍工廠内にはなんと二千台の卓球台があった、という。海軍は軍艦の中に卓球台をおいて、軍人のスポーツの一つとしていたわけだから、卓球への理解が深かったのである。
第二回目の召集は十九年二月であり、二カ月間の暗号教育を受け、外地へ飛ばされるところ、教育方法を批判した私の感想文提出で、逆に教育要員として残留を命ぜられた。これは同隊の教育担当将校に十川方之少尉という立派な人がいた。彼が私を見込んで残して下さった、わけだ。
暗号教育隊で私は教育係助手をつとめた(別稿、紅林茂夫先生との対談を参照)。そしてその後は人事係助手をつとめていた。
長は井島曹長という秋田の農家の人。次に田舛兵長で私の部下は旭一等兵(高知県の中学校長)、丸山真男二等兵(当時、東大の助教授、現名誉教授、日本の政治学の権威)。この二人は私が選んで人事にとったのであるが、この四人の階級は逆になるべきもの、と思った。日本が戦争に敗れる象徴的な構図であった。
[卓球レポートアーカイブ]
「卓球は血と魂だ」 第一章 四 マラソン優勝と兵隊時代
2013.05.09
\この記事をシェアする/