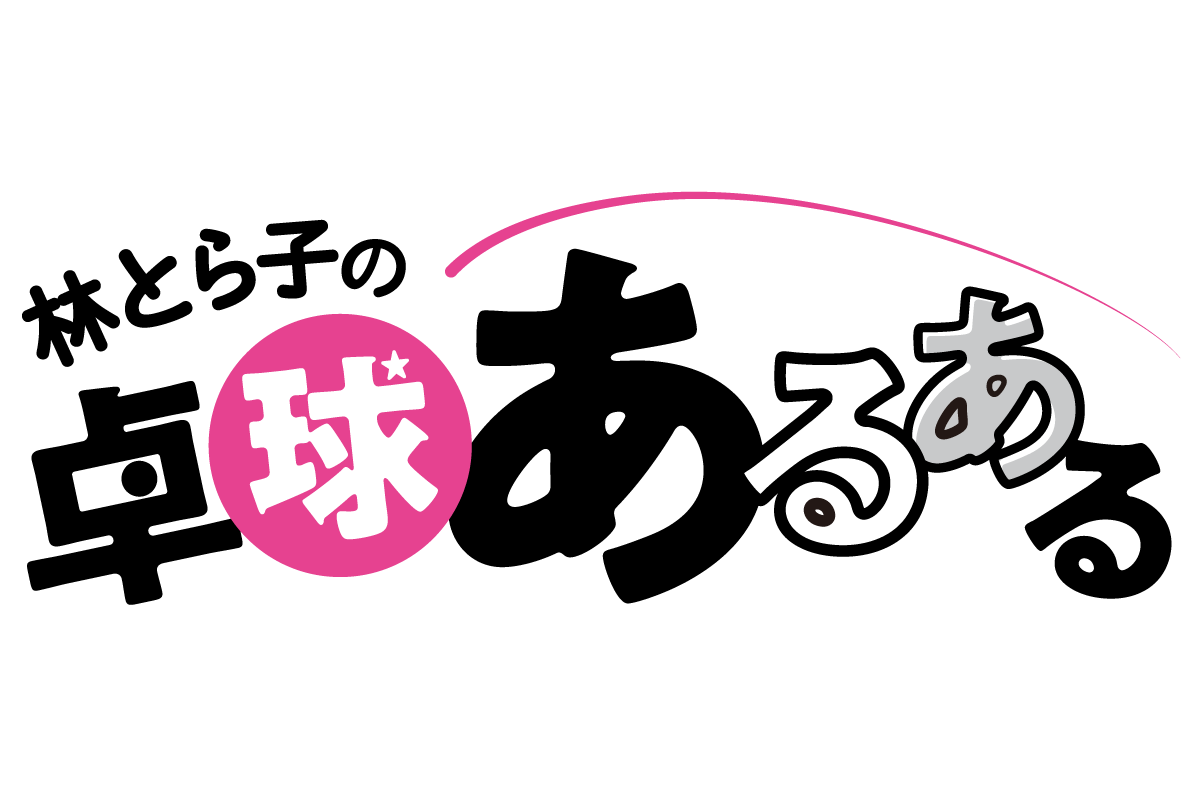数々ある思い出の大会の中でも、6度目の史上最多優勝記録を樹立した年の全日本選手権大会は、私にとってなつかしい大会だ。中でも、決勝での井上(井上スポーツ)戦、準決勝での古川(荻村商事)戦、準々決勝での阿部勝幸(協和発酵)戦、その前の杉本敬太郎(三重県庁)戦や藤原孝志(日本楽器)戦は特に印象深い。
会場は、底冷えのする東京の駒沢屋内球技場。男子シングルスは、12月6~7日の2日間にわたって行なわれた。この大会の試合を語るには、大会前のコンディションの状態を話さなければ正確には伝えられない。そこで、大会前のコンディションの状態から話してみたい。
今でも忘れられないが、この年は私が卓球をやりはじめてから一番の不調にみまわれた年で、暗いトンネルが長く続いているような状態の苦しい年だった。
なぜ、そのような大不調にみまわれたか。
ことのはじまりは、'72年の9月に中国の首都北京で行なわれた第1回アジア選手権大会に参加するために、中国へ旅立つ前日に起こった。私はこのときに「去年の9月に北京で行なわれたアジア・アフリカ友好大会で日本は中国を5対3で破って優勝したが、2度続けて勝たなければ本当に勝ったとはいえない。その意味で中国に絶対に負けられない。しかし、それには体力がなければ勝てない。体力トレーニングと練習を十分にやったとはいうものの、現在使用しているラケット(195g)では重たすぎて途中で疲れてしまい勝てないだろう。危険だが思い切ってラケットの回りを削って軽くした方が良いのではないか」と考え、出発直前にそれまで愛用していたラケットの回りを3~4ミリ削った。それまでにも私はこのように思い切った決断をして成功していた。
だが、中国で初練習をした結果は無惨だった。ラケットは確かに軽くなったが想像したのとは大きく違った。ラケットを振るときの空気抵抗や打撃芯、ラケットの重心の位置などが大きく変わったために、インパクトの位置や打球感が大きく変わってしまい、まったく使いものにならなくなってしまった。すぐにスペアラケットに変えたが、グリップの少しの違いから打球する前に手首や腕、肩に力が入るようになった。その後、スペアラケットのグリップをいろいろ工夫したが、やはりちょっとの違いでしっくりいかなかった。
このときのアジア選手権大会は、それまでの多量の練習とトレーニングに裏付けられた気力でなんとかカバーして、団体とシングルスと混合複の3種目に優勝した。しかし大会後、グリップがすごく気になりはじめて、それに気をとらわれて1日の生活のリズムを大きく狂わした。技術的にも打球する前に余計な力が入るため以前のプレイができなくなり、その年の全日本、翌年のサラエボでの世界選手権、'73年全日本の前哨戦である全日本社会人などに次々と敗れ、最低の成績になりそうであった。
そしてこのとき、私の年齢は全日本出場9回目を迎えて26才となっていた。この年齢からも、もう長谷川の卓球はダメだとか限界だとか国際試合に使えないとか冷たく言われはじめていた。勝負の世界は勝たなければいくら努力しても評価されない厳しい世界である。健在であることを示すためには、何しろ勝つしかなった。が、悲しいことに全日本1ヵ月前を迎えてもグリップがしっくりいかず、もがけばもがくほど沈む底なし沼に入ったようだった。全日本の1ヵ月ぐらい前は眠れない日々が続き棄権したい気持ちだった。
だがこんな不調のどん底のとき、幸運にもすばらしい言葉に出会った。「困難に出会ったとき逃げると危険が2倍になる。しかし、俄然立ち向かえば危険が半分に減る」...イギリスの首相だったチャーチルの名言である。私はこの言葉を読んだときハッとした。よし、危険が半分に減るんならやってみよう。
その日から猛練習を開始して大会に備えた。だが少しは上向いたものの、大会前日になっても調子はよくなかった。私は「背水の陣」だと思い、はじめから苦戦を覚悟して作戦と心構えをしっかり立てて臨んだ。
試合がはじまった。1日目の2回戦、3回戦は作戦どおり得意のロング戦に持ち込めた。そうなるとコントロールの差がでて危なげなく4回戦へと勝ち進んだ。
しかし、このあとから対戦するクセのある選手達を考えると楽観は許されなかった。
4回戦の相手は、表ソフト攻撃型の藤原選手('71年東日本学生3冠王)。私はこの選手には負けるかもしれない、と思った。1つのヤマ場だった。じつは、この年に行なわれた世界選手権代表強化合宿のときに、何度も試合をしたことがある。このとき、彼のショートとショートから回り込んでのスマッシュを実に正確でしかも威力があり、私が負け越していた。それだけに試合前に藤原選手の回り込みスマッシュを防ぐ作戦と、最後まで自信を持ち集中してやることを決心した。勝てばランキングに入れる試合であった。また、この試合で自分のだいたいの力がつかめると思い必死だった。
試合がはじまった。私は、藤原選手の回り込みスマッシュを浴びないで彼のショートをつぶしたかった。そのためには、積極的にサービスからの3球目攻撃、レシーブからの4球目攻撃をして相手を守勢に立たせなければならない。そこで作戦通りに変化のあるショートサービスとスピードのあるカット性ロングサービス、ドライブ性ロングサービスを藤原選手の心理を読んで使い、サービスで先手をとってから3球目ドライブを藤原選手のミドルとバックへ集めた。待ちをはずすために3本に1本くらいの割合でフォア側へも思い切り攻めた。このとき、注意したことがある。単調なからだの使い方だと、コースを読まれて逆にねらい打ちされてしまう。藤原選手は守りが大変うまく、いきなりバック側からフォア側をつくと逆に大きくフォア側へゆさぶられ、不利な態勢になる。そこでレシーブのときに、ボールのところまですばやく動きボールをよく引きつけた。そして、いかにも両サイドへ打つような態勢からバック側へ強く攻めた。藤原選手は、こちらの思った通りに足の動きが止まり、ショートで両サイドへ回してきた。私は、このショートに対して再びドライブでバックコーナーをついた。3球目と同じ考えで逆モーション気味のドライブで思い切り攻めたので、藤原選手はコートから離れざるを得なくなった。そして、藤原選手が甘いショートで返球してきたのを三度ドライブでバックへ攻めた。フォアドライブで回り込めなかったのは、バックハンドで強襲した。これで藤原選手の態勢はやや棒立ちとなった。そして、藤原選手が両サイドにつないでくるのを回り込めなくしておいてバック側へ攻めた。回り込もうとしたときは、スッとフォアへ攻めた。そして相手のミスを誘った。
もちろん、ラリー戦になったとき常に同じ作戦では相手にコースを読まれてしまうために、相手の心理を読んで相手がバック側を警戒してフォア側に少しでもスキが見えたときはフォアへ思い切りドライブ攻撃をした。それゆえに、藤原選手は常にフォアをも注意しなければならずバックへの攻めが非常によく効いた。
それと、しのぎのときの作戦も成功した。
私は、先手を取ったときの作戦と、先手を取られた場合のしのぎの作戦も考えて試合に臨んだ。藤原選手のうまい攻撃に何度かコートから下げさせられたとき、試合前の作戦どおり主に後陣からボールをよく引きつけていつものようなロビングではなくスナップをよく利かしたドライブで返した。ロビングボールはときどきしか使わなかった。それは、ロビングで返した場合、藤原選手はストップがうまかったからだ。しかし、ドライブで返せば強い回転がかかっているのでそれほど短くは止められないし、気持ちに焦りが出てスマッシュミスしやすい。また、反撃チャンスが多くなるからである。
このような考えから、後陣にさがったときは、できるだけ強い回転をかけたドライブで返した。エンドラインいっぱいのところを狙って何本も粘った。気迫がボールにこもったせいかコートについてから伸びるのだろう。ノータッチで抜かれることはほとんどなく、守りに追いやられたときに互角であった。
この攻めとしのぎの作戦で藤原選手のペースを大きく乱し、13本、16本、15本でストレート勝ちした。第1の難関を突破し私は大きな自信を得た。
(つづく)
会場は、底冷えのする東京の駒沢屋内球技場。男子シングルスは、12月6~7日の2日間にわたって行なわれた。この大会の試合を語るには、大会前のコンディションの状態を話さなければ正確には伝えられない。そこで、大会前のコンディションの状態から話してみたい。
今でも忘れられないが、この年は私が卓球をやりはじめてから一番の不調にみまわれた年で、暗いトンネルが長く続いているような状態の苦しい年だった。
なぜ、そのような大不調にみまわれたか。
ことのはじまりは、'72年の9月に中国の首都北京で行なわれた第1回アジア選手権大会に参加するために、中国へ旅立つ前日に起こった。私はこのときに「去年の9月に北京で行なわれたアジア・アフリカ友好大会で日本は中国を5対3で破って優勝したが、2度続けて勝たなければ本当に勝ったとはいえない。その意味で中国に絶対に負けられない。しかし、それには体力がなければ勝てない。体力トレーニングと練習を十分にやったとはいうものの、現在使用しているラケット(195g)では重たすぎて途中で疲れてしまい勝てないだろう。危険だが思い切ってラケットの回りを削って軽くした方が良いのではないか」と考え、出発直前にそれまで愛用していたラケットの回りを3~4ミリ削った。それまでにも私はこのように思い切った決断をして成功していた。
だが、中国で初練習をした結果は無惨だった。ラケットは確かに軽くなったが想像したのとは大きく違った。ラケットを振るときの空気抵抗や打撃芯、ラケットの重心の位置などが大きく変わったために、インパクトの位置や打球感が大きく変わってしまい、まったく使いものにならなくなってしまった。すぐにスペアラケットに変えたが、グリップの少しの違いから打球する前に手首や腕、肩に力が入るようになった。その後、スペアラケットのグリップをいろいろ工夫したが、やはりちょっとの違いでしっくりいかなかった。
このときのアジア選手権大会は、それまでの多量の練習とトレーニングに裏付けられた気力でなんとかカバーして、団体とシングルスと混合複の3種目に優勝した。しかし大会後、グリップがすごく気になりはじめて、それに気をとらわれて1日の生活のリズムを大きく狂わした。技術的にも打球する前に余計な力が入るため以前のプレイができなくなり、その年の全日本、翌年のサラエボでの世界選手権、'73年全日本の前哨戦である全日本社会人などに次々と敗れ、最低の成績になりそうであった。
そしてこのとき、私の年齢は全日本出場9回目を迎えて26才となっていた。この年齢からも、もう長谷川の卓球はダメだとか限界だとか国際試合に使えないとか冷たく言われはじめていた。勝負の世界は勝たなければいくら努力しても評価されない厳しい世界である。健在であることを示すためには、何しろ勝つしかなった。が、悲しいことに全日本1ヵ月前を迎えてもグリップがしっくりいかず、もがけばもがくほど沈む底なし沼に入ったようだった。全日本の1ヵ月ぐらい前は眠れない日々が続き棄権したい気持ちだった。
だがこんな不調のどん底のとき、幸運にもすばらしい言葉に出会った。「困難に出会ったとき逃げると危険が2倍になる。しかし、俄然立ち向かえば危険が半分に減る」...イギリスの首相だったチャーチルの名言である。私はこの言葉を読んだときハッとした。よし、危険が半分に減るんならやってみよう。
その日から猛練習を開始して大会に備えた。だが少しは上向いたものの、大会前日になっても調子はよくなかった。私は「背水の陣」だと思い、はじめから苦戦を覚悟して作戦と心構えをしっかり立てて臨んだ。
試合がはじまった。1日目の2回戦、3回戦は作戦どおり得意のロング戦に持ち込めた。そうなるとコントロールの差がでて危なげなく4回戦へと勝ち進んだ。
しかし、このあとから対戦するクセのある選手達を考えると楽観は許されなかった。
4回戦の相手は、表ソフト攻撃型の藤原選手('71年東日本学生3冠王)。私はこの選手には負けるかもしれない、と思った。1つのヤマ場だった。じつは、この年に行なわれた世界選手権代表強化合宿のときに、何度も試合をしたことがある。このとき、彼のショートとショートから回り込んでのスマッシュを実に正確でしかも威力があり、私が負け越していた。それだけに試合前に藤原選手の回り込みスマッシュを防ぐ作戦と、最後まで自信を持ち集中してやることを決心した。勝てばランキングに入れる試合であった。また、この試合で自分のだいたいの力がつかめると思い必死だった。
試合がはじまった。私は、藤原選手の回り込みスマッシュを浴びないで彼のショートをつぶしたかった。そのためには、積極的にサービスからの3球目攻撃、レシーブからの4球目攻撃をして相手を守勢に立たせなければならない。そこで作戦通りに変化のあるショートサービスとスピードのあるカット性ロングサービス、ドライブ性ロングサービスを藤原選手の心理を読んで使い、サービスで先手をとってから3球目ドライブを藤原選手のミドルとバックへ集めた。待ちをはずすために3本に1本くらいの割合でフォア側へも思い切り攻めた。このとき、注意したことがある。単調なからだの使い方だと、コースを読まれて逆にねらい打ちされてしまう。藤原選手は守りが大変うまく、いきなりバック側からフォア側をつくと逆に大きくフォア側へゆさぶられ、不利な態勢になる。そこでレシーブのときに、ボールのところまですばやく動きボールをよく引きつけた。そして、いかにも両サイドへ打つような態勢からバック側へ強く攻めた。藤原選手は、こちらの思った通りに足の動きが止まり、ショートで両サイドへ回してきた。私は、このショートに対して再びドライブでバックコーナーをついた。3球目と同じ考えで逆モーション気味のドライブで思い切り攻めたので、藤原選手はコートから離れざるを得なくなった。そして、藤原選手が甘いショートで返球してきたのを三度ドライブでバックへ攻めた。フォアドライブで回り込めなかったのは、バックハンドで強襲した。これで藤原選手の態勢はやや棒立ちとなった。そして、藤原選手が両サイドにつないでくるのを回り込めなくしておいてバック側へ攻めた。回り込もうとしたときは、スッとフォアへ攻めた。そして相手のミスを誘った。
もちろん、ラリー戦になったとき常に同じ作戦では相手にコースを読まれてしまうために、相手の心理を読んで相手がバック側を警戒してフォア側に少しでもスキが見えたときはフォアへ思い切りドライブ攻撃をした。それゆえに、藤原選手は常にフォアをも注意しなければならずバックへの攻めが非常によく効いた。
それと、しのぎのときの作戦も成功した。
私は、先手を取ったときの作戦と、先手を取られた場合のしのぎの作戦も考えて試合に臨んだ。藤原選手のうまい攻撃に何度かコートから下げさせられたとき、試合前の作戦どおり主に後陣からボールをよく引きつけていつものようなロビングではなくスナップをよく利かしたドライブで返した。ロビングボールはときどきしか使わなかった。それは、ロビングで返した場合、藤原選手はストップがうまかったからだ。しかし、ドライブで返せば強い回転がかかっているのでそれほど短くは止められないし、気持ちに焦りが出てスマッシュミスしやすい。また、反撃チャンスが多くなるからである。
このような考えから、後陣にさがったときは、できるだけ強い回転をかけたドライブで返した。エンドラインいっぱいのところを狙って何本も粘った。気迫がボールにこもったせいかコートについてから伸びるのだろう。ノータッチで抜かれることはほとんどなく、守りに追いやられたときに互角であった。
この攻めとしのぎの作戦で藤原選手のペースを大きく乱し、13本、16本、15本でストレート勝ちした。第1の難関を突破し私は大きな自信を得た。
(つづく)
筆者紹介 長谷川信彦
 1947年3月5日-2005年11月7日
1947年3月5日-2005年11月7日
1965年に史上最年少の18歳9カ月で全日本選手権大会男子シングルス優勝。1967年世界選手権ストックホルム大会では初出場で3冠(男子団体・男子 シングルス・混合ダブルス)に輝いた。男子団体に3回連続優勝。伊藤繁雄、河野満とともに1960~70年代の日本の黄金時代を支えた。
運動能力が決して優れていたわけではなかった長谷川は、そのコンプレックスをバネに想像を絶する猛練習を行って世界一になった「努力の天才」である。
人差し指がバック面の中央付近にくる「1本差し」と呼ばれる独特のグリップから放つ"ジェットドライブ"や、ロビングからのカウンターバックハンドスマッシュなど、絵に描いたようなスーパープレーで観衆を魅了した。
 1947年3月5日-2005年11月7日
1947年3月5日-2005年11月7日1965年に史上最年少の18歳9カ月で全日本選手権大会男子シングルス優勝。1967年世界選手権ストックホルム大会では初出場で3冠(男子団体・男子 シングルス・混合ダブルス)に輝いた。男子団体に3回連続優勝。伊藤繁雄、河野満とともに1960~70年代の日本の黄金時代を支えた。
運動能力が決して優れていたわけではなかった長谷川は、そのコンプレックスをバネに想像を絶する猛練習を行って世界一になった「努力の天才」である。
人差し指がバック面の中央付近にくる「1本差し」と呼ばれる独特のグリップから放つ"ジェットドライブ"や、ロビングからのカウンターバックハンドスマッシュなど、絵に描いたようなスーパープレーで観衆を魅了した。
本稿は卓球レポート1979年2月号に掲載されたものです。