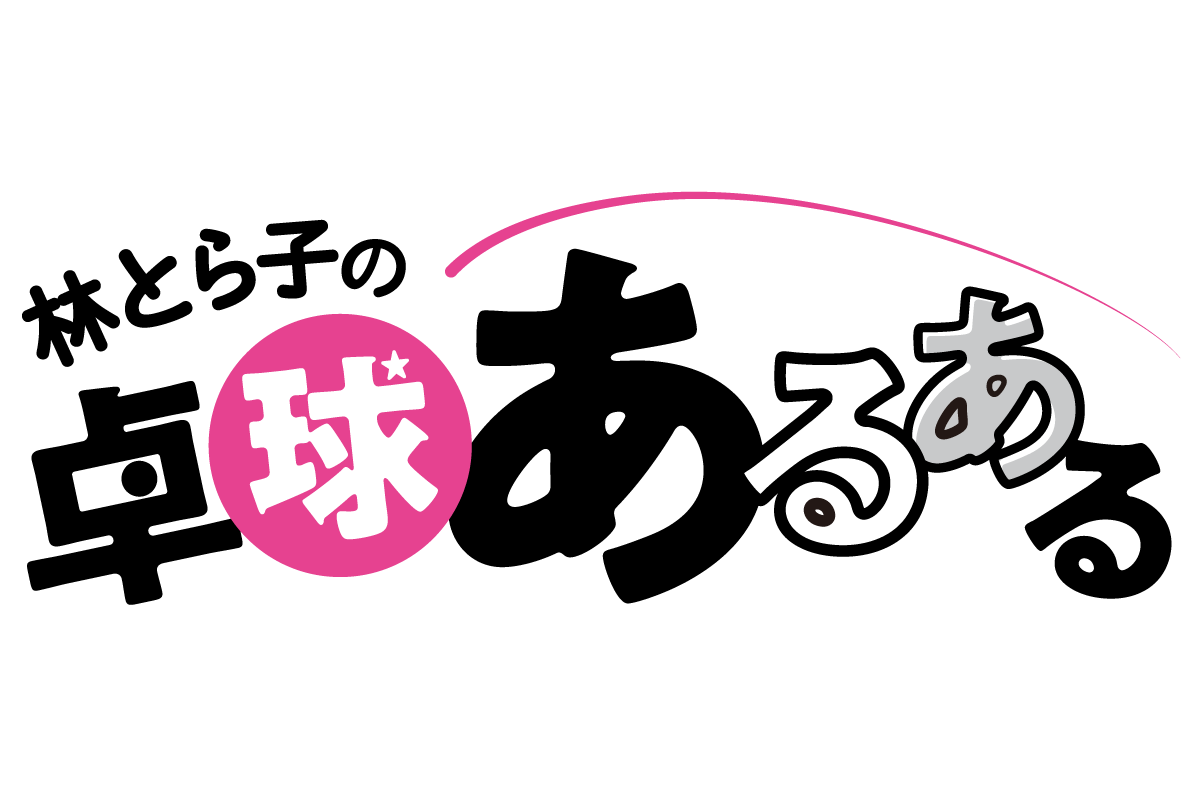試合は、精神面のコントロールが大切
初めてラケットを握る人が、卓球で強くなるためには、まず技術をマスターすることである。特にサービス、レシーブの重要性が高い。そして自分の特長に合ったプレースタイルを選び、正しく基本技術を高めていく。
次に作戦(試合運び)をマスターすることである。自分が同じサービスを出すとまず同じ場所に返ってくる。それを打つと得だから打つ。入らなそうならつなぐ。そういった初心者に近いレベルでもそれなりの作戦がある。相手がカット型ならこうやる、ドライブ型ならこうやる、と知っていると非常に勝ちやすい。さらにレベルが上がると、試合中に相手と自分の技量を比較し、どんな作戦を軸に、どのように戦っていくかを冷静に判断しなければ勝てなくなってくる。初心者、中級者のうちから、作戦の立て方のうまい、へたは勝敗に大きく影響してくる。
さらに上のレベルになってくると体力が必要になってくる。打ったボールが速いか遅いか。正しい動き方をしてもその動くスピードが速いか遅いか。その体力的レベルで強さが変わってくる。また、試合が続いた時に技術面、精神面のレベルが下がらないためには体力が必要である。しかしながら「卓球は体力が勝負」と感じるのはそうとう上のレベルになってからであり、多くの人はそこまでいかないうちに卓球生活を終える。と同時に、そのレベルになってから体力の強化を考えても、すでに遅すぎるケースが多い。
卓球の強さを表す要素には以上挙げた技術面、作戦面、体力面のほかに精神面がある。
初心者のレベルでは体力面の重要性はうすい。しかし、精神面の強さは初心者からオリンピック級の選手まですべての選手に必要である。緊張して打てなくなるのは初心者に限らない。技術面、作戦面では完璧に近い選手が、国際試合で急にリズムを崩し、あっけない負け方をすることがままある。
そう考えていくと、卓球を始めた選手が早く強くなろうと思ったら、技術(技)、作戦(智)、精神力(心)、体力(体)...の順で強化が必要だが、最高レベルの選手同士の試合で勝敗を分ける順としては、心・体・智・技であろう。レベルが高くなればなるほど、精神力、体力の重要性が増してくるのである。
試合で精神面をコントロールできるようになれば、勝率がグンとアップすることは間違いない。
勝ちたい、勝ちたいはマイナスに働く
長谷川語録の四番目に筆者が書いた言葉は「勝敗にこだわらずに戦う」であった。
卓球に限らず、勝敗を決める競技においては、勝つ意欲が絶対に必要だが、強すぎると「過ぎたるは及ばざるがごとし」で逆にマイナスに働く。
幾つか例を挙げると―
①「勝ちたい。勝ちたい」ばかりで頭の中がいっぱいになり、肝心の「どうやったら勝てるか」に頭が回らない。ミドルに打てば決まるボールをフォアへ打ったり、サービス・レシーブが単調になる
②「勝ちたい」気持ちがプレッシャーになり体が固くなる。力が入ってスイングが遅くなるため、ネットミスがでたり、球威がなくなる
③勝負するのが怖くなり、大事に大事に入れておこうとする。当然打つべきチャンスボールをつないでしまったりする。
このように勝敗を気にしだすと、体が固くなり凡ミスがでる。やることも単調になり、打っても決まらなくなる。打っても決まらないうえに打ちミスがでるので打たなくなる。当然打つべきボールを打てないので普段と違うプレーになる。調子がますますでない...。といった悪循環になってしまう。
不調になる最初の原因は、勝敗を意識しすぎ「勝ちたい。勝ちたい」で頭の中がいっぱいになってしまうところにある。
練習試合を本試合と同じ緊張感で
勝とうと思うと打てなくなる原因のひとつに、普段の練習の時に、練習だからといって無理に打ちすぎているケースがある。
バックハンドで強打する。低いボールをスマッシュで狙う...。このように新しい技術にチャレンジし、積極的に練習していくことはよいことである。
しかし、それならそれで「これは今、新しい技術課題として取り組んでいるんだ。こういったボールなら何パーセントぐらい入るんだ。試合になったら自分が有利になるように使うんだ。それ以外は上手につなぐんだ」と自覚して練習していかなくてはならない。
練習の時は1本打ちやコースを決めての練習ばかりし、試合になってコースが読めなくなると急に入らなくなるので試合では使えない、とか、練習試合の時は入る確率を考えずに気楽にやっていて、本試合で「勝ちたい」と思うと入る確率が低いため使えないといったことではまずい。
普段の練習から、どういったボールはだいたいどのぐらい入るか、を正しく認識しておき、試合で「勝ちたい」と思った時に普段の練習試合とプレー内容が変わらないようにしておくことも大切である。
そのためには練習試合の時、本試合以上に「勝ちたい」「勝つためにはどうしたらよいか」と考え、本試合以上の緊張感で試合する。どういったボールを打ったら得なのか、損なのかを分析し、「自分が有利になる技術しか使わない」と本試合と同じ状況下で練習試合すべきである。
確率を考えずに打ってはいけない
もちろん、時には、現在は確率が低くても、将来のためにこういった技術を使っていく、という場合もある。
そういった場合は「将来の本試合で有利にするために、練習していくんだ」と自覚し、思いきって使ってみる。練習試合のみならず、多少確率は低くても本試合で使ってみる場合もありうる。もともとこういった心理状況は「将来のために使うんだ。この試合には負けてもしかたない」と考える時であり、勝敗を意識することでプレー内容が変わるという状態ではない。
ただし、いくら無理なボールを新しい技術で積極的に攻撃するといっても、世界チャンピオンでも打たないようなボールを打ってはいけない。自分が打ったほうが楽だから、という自分勝手な理由で確率を考えずに打ってはいけない。世界チャンピオンでも「難しいボールはつなぎ、チャンスボールを狙う」鉄則を守っている。ワルドナーなどがその逆をやっている時は、相手の読みの逆をつき、確率からいって難球を打ったほうが得、という一段上のレベルでの作戦なのである。
「勝ちたい」と思った時に打てなくなるボールを無理に打つクセをつけてはいけない。それよりトッププレーヤーのビデオ等を参考に、難しいボールがきて打てない時にはどうやって自分の有利なプレーにもっていっているか、を研究してほしい。
試合では好調の時もあれば不調の時もある。調子が落ち、入るべきボールが入らない、という時、強引に攻めずに第二、第三の作戦で、もう一本つないでチャンスボールをつくって打つとか、相手にやらせてショートなどで逆をついて得点するといったシステムがあるとよい。そうすれば調子が悪くてもがんばれるし、そうこうしているうちに調子も上がってくる。
心技体智をすべて出して戦う
勝敗を意識せずに戦うことは大切である。勝敗を意識せず、練習どおりのプレーをすればおのずからよい結果が生まれる。
実は、筆者は大学1年から、「勝敗を意識しないで戦う」とノートに書いて試合のたびに目を通していたのだが、後になってすこし加筆した。
それは大学3年で初出場したストックホルム世界選手権男子団体決勝戦の前日、夜のミーティングで男子監督だった木村興治さんが「明日の朝鮮との試合は、勝敗にこだわらず、今まで積み重ねてきた心技体智をすべて出して戦ってほしい」旨の話をされた。この言葉は翌日の試合で非常に筆者を助けてくれた。
「日本のために絶対に勝たなくてはならない」と力んでいた筆者は「そうだ、今まで積み重ねてきた心技体智をすべて相手にぶつければいいんだ」と思い救われた。初出場の硬さがとれ、2勝して日本の優勝に貢献することができた。
私はそれ以来、ノートの言葉を、木村さんから教えていただいた「勝敗にこだわらず、今まで積み重ねてきた心技体智をすべて出して戦う」に変えた。
勝敗にこだわらず無心で戦うことはなかなか難しい。勝敗を争うスポーツで、全く勝つ意志がないのではよいプレーなどできない。といって、あまり勝ちを強く意識するとこれまたよいプレーができない。そういったジレンマがあるからである。
そこで自分の意志で「勝敗にはこだわりすぎるな。自分のベストのプレーをすればいいんだ。無心で戦う」と自己暗示をかけ、ベストの精神状態にして試合場に向かうわけである。
このように、いざという時、自分の意志で自分の精神状態をコントロールするには、普段から緊張した状況で練習する、ノートに心を整理する言葉を書き試合前に読む、自分で心に決めた計画は必ず実行し意志力を鍛える...といった日々の努力が必要になってくる。
初めてラケットを握る人が、卓球で強くなるためには、まず技術をマスターすることである。特にサービス、レシーブの重要性が高い。そして自分の特長に合ったプレースタイルを選び、正しく基本技術を高めていく。
次に作戦(試合運び)をマスターすることである。自分が同じサービスを出すとまず同じ場所に返ってくる。それを打つと得だから打つ。入らなそうならつなぐ。そういった初心者に近いレベルでもそれなりの作戦がある。相手がカット型ならこうやる、ドライブ型ならこうやる、と知っていると非常に勝ちやすい。さらにレベルが上がると、試合中に相手と自分の技量を比較し、どんな作戦を軸に、どのように戦っていくかを冷静に判断しなければ勝てなくなってくる。初心者、中級者のうちから、作戦の立て方のうまい、へたは勝敗に大きく影響してくる。
さらに上のレベルになってくると体力が必要になってくる。打ったボールが速いか遅いか。正しい動き方をしてもその動くスピードが速いか遅いか。その体力的レベルで強さが変わってくる。また、試合が続いた時に技術面、精神面のレベルが下がらないためには体力が必要である。しかしながら「卓球は体力が勝負」と感じるのはそうとう上のレベルになってからであり、多くの人はそこまでいかないうちに卓球生活を終える。と同時に、そのレベルになってから体力の強化を考えても、すでに遅すぎるケースが多い。
卓球の強さを表す要素には以上挙げた技術面、作戦面、体力面のほかに精神面がある。
初心者のレベルでは体力面の重要性はうすい。しかし、精神面の強さは初心者からオリンピック級の選手まですべての選手に必要である。緊張して打てなくなるのは初心者に限らない。技術面、作戦面では完璧に近い選手が、国際試合で急にリズムを崩し、あっけない負け方をすることがままある。
そう考えていくと、卓球を始めた選手が早く強くなろうと思ったら、技術(技)、作戦(智)、精神力(心)、体力(体)...の順で強化が必要だが、最高レベルの選手同士の試合で勝敗を分ける順としては、心・体・智・技であろう。レベルが高くなればなるほど、精神力、体力の重要性が増してくるのである。
試合で精神面をコントロールできるようになれば、勝率がグンとアップすることは間違いない。
勝ちたい、勝ちたいはマイナスに働く
長谷川語録の四番目に筆者が書いた言葉は「勝敗にこだわらずに戦う」であった。
卓球に限らず、勝敗を決める競技においては、勝つ意欲が絶対に必要だが、強すぎると「過ぎたるは及ばざるがごとし」で逆にマイナスに働く。
幾つか例を挙げると―
①「勝ちたい。勝ちたい」ばかりで頭の中がいっぱいになり、肝心の「どうやったら勝てるか」に頭が回らない。ミドルに打てば決まるボールをフォアへ打ったり、サービス・レシーブが単調になる
②「勝ちたい」気持ちがプレッシャーになり体が固くなる。力が入ってスイングが遅くなるため、ネットミスがでたり、球威がなくなる
③勝負するのが怖くなり、大事に大事に入れておこうとする。当然打つべきチャンスボールをつないでしまったりする。
このように勝敗を気にしだすと、体が固くなり凡ミスがでる。やることも単調になり、打っても決まらなくなる。打っても決まらないうえに打ちミスがでるので打たなくなる。当然打つべきボールを打てないので普段と違うプレーになる。調子がますますでない...。といった悪循環になってしまう。
不調になる最初の原因は、勝敗を意識しすぎ「勝ちたい。勝ちたい」で頭の中がいっぱいになってしまうところにある。
練習試合を本試合と同じ緊張感で
勝とうと思うと打てなくなる原因のひとつに、普段の練習の時に、練習だからといって無理に打ちすぎているケースがある。
バックハンドで強打する。低いボールをスマッシュで狙う...。このように新しい技術にチャレンジし、積極的に練習していくことはよいことである。
しかし、それならそれで「これは今、新しい技術課題として取り組んでいるんだ。こういったボールなら何パーセントぐらい入るんだ。試合になったら自分が有利になるように使うんだ。それ以外は上手につなぐんだ」と自覚して練習していかなくてはならない。
練習の時は1本打ちやコースを決めての練習ばかりし、試合になってコースが読めなくなると急に入らなくなるので試合では使えない、とか、練習試合の時は入る確率を考えずに気楽にやっていて、本試合で「勝ちたい」と思うと入る確率が低いため使えないといったことではまずい。
普段の練習から、どういったボールはだいたいどのぐらい入るか、を正しく認識しておき、試合で「勝ちたい」と思った時に普段の練習試合とプレー内容が変わらないようにしておくことも大切である。
そのためには練習試合の時、本試合以上に「勝ちたい」「勝つためにはどうしたらよいか」と考え、本試合以上の緊張感で試合する。どういったボールを打ったら得なのか、損なのかを分析し、「自分が有利になる技術しか使わない」と本試合と同じ状況下で練習試合すべきである。
確率を考えずに打ってはいけない
もちろん、時には、現在は確率が低くても、将来のためにこういった技術を使っていく、という場合もある。
そういった場合は「将来の本試合で有利にするために、練習していくんだ」と自覚し、思いきって使ってみる。練習試合のみならず、多少確率は低くても本試合で使ってみる場合もありうる。もともとこういった心理状況は「将来のために使うんだ。この試合には負けてもしかたない」と考える時であり、勝敗を意識することでプレー内容が変わるという状態ではない。
ただし、いくら無理なボールを新しい技術で積極的に攻撃するといっても、世界チャンピオンでも打たないようなボールを打ってはいけない。自分が打ったほうが楽だから、という自分勝手な理由で確率を考えずに打ってはいけない。世界チャンピオンでも「難しいボールはつなぎ、チャンスボールを狙う」鉄則を守っている。ワルドナーなどがその逆をやっている時は、相手の読みの逆をつき、確率からいって難球を打ったほうが得、という一段上のレベルでの作戦なのである。
「勝ちたい」と思った時に打てなくなるボールを無理に打つクセをつけてはいけない。それよりトッププレーヤーのビデオ等を参考に、難しいボールがきて打てない時にはどうやって自分の有利なプレーにもっていっているか、を研究してほしい。
試合では好調の時もあれば不調の時もある。調子が落ち、入るべきボールが入らない、という時、強引に攻めずに第二、第三の作戦で、もう一本つないでチャンスボールをつくって打つとか、相手にやらせてショートなどで逆をついて得点するといったシステムがあるとよい。そうすれば調子が悪くてもがんばれるし、そうこうしているうちに調子も上がってくる。
心技体智をすべて出して戦う
勝敗を意識せずに戦うことは大切である。勝敗を意識せず、練習どおりのプレーをすればおのずからよい結果が生まれる。
実は、筆者は大学1年から、「勝敗を意識しないで戦う」とノートに書いて試合のたびに目を通していたのだが、後になってすこし加筆した。
それは大学3年で初出場したストックホルム世界選手権男子団体決勝戦の前日、夜のミーティングで男子監督だった木村興治さんが「明日の朝鮮との試合は、勝敗にこだわらず、今まで積み重ねてきた心技体智をすべて出して戦ってほしい」旨の話をされた。この言葉は翌日の試合で非常に筆者を助けてくれた。
「日本のために絶対に勝たなくてはならない」と力んでいた筆者は「そうだ、今まで積み重ねてきた心技体智をすべて相手にぶつければいいんだ」と思い救われた。初出場の硬さがとれ、2勝して日本の優勝に貢献することができた。
私はそれ以来、ノートの言葉を、木村さんから教えていただいた「勝敗にこだわらず、今まで積み重ねてきた心技体智をすべて出して戦う」に変えた。
勝敗にこだわらず無心で戦うことはなかなか難しい。勝敗を争うスポーツで、全く勝つ意志がないのではよいプレーなどできない。といって、あまり勝ちを強く意識するとこれまたよいプレーができない。そういったジレンマがあるからである。
そこで自分の意志で「勝敗にはこだわりすぎるな。自分のベストのプレーをすればいいんだ。無心で戦う」と自己暗示をかけ、ベストの精神状態にして試合場に向かうわけである。
このように、いざという時、自分の意志で自分の精神状態をコントロールするには、普段から緊張した状況で練習する、ノートに心を整理する言葉を書き試合前に読む、自分で心に決めた計画は必ず実行し意志力を鍛える...といった日々の努力が必要になってくる。
筆者紹介 長谷川信彦
 1947年3月5日-2005年11月7日
1947年3月5日-2005年11月7日
1965年に史上最年少の18歳9カ月で全日本選手権大会男子シングルス優勝。1967年世界選手権ストックホルム大会では初出場で3冠(男子団体・男子 シングルス・混合ダブルス)に輝いた。男子団体に3回連続優勝。伊藤繁雄、河野満とともに1960~70年代の日本の黄金時代を支えた。
運動能力が決して優れていたわけではなかった長谷川は、そのコンプレックスをバネに想像を絶する猛練習を行って世界一になった「努力の天才」である。
人差し指がバック面の中央付近にくる「1本差し」と呼ばれる独特のグリップから放つ"ジェットドライブ"や、ロビングからのカウンターバックハンドスマッシュなど、絵に描いたようなスーパープレーで観衆を魅了した。
 1947年3月5日-2005年11月7日
1947年3月5日-2005年11月7日1965年に史上最年少の18歳9カ月で全日本選手権大会男子シングルス優勝。1967年世界選手権ストックホルム大会では初出場で3冠(男子団体・男子 シングルス・混合ダブルス)に輝いた。男子団体に3回連続優勝。伊藤繁雄、河野満とともに1960~70年代の日本の黄金時代を支えた。
運動能力が決して優れていたわけではなかった長谷川は、そのコンプレックスをバネに想像を絶する猛練習を行って世界一になった「努力の天才」である。
人差し指がバック面の中央付近にくる「1本差し」と呼ばれる独特のグリップから放つ"ジェットドライブ"や、ロビングからのカウンターバックハンドスマッシュなど、絵に描いたようなスーパープレーで観衆を魅了した。
本稿は卓球レポート1990年6月号に掲載されたものです。