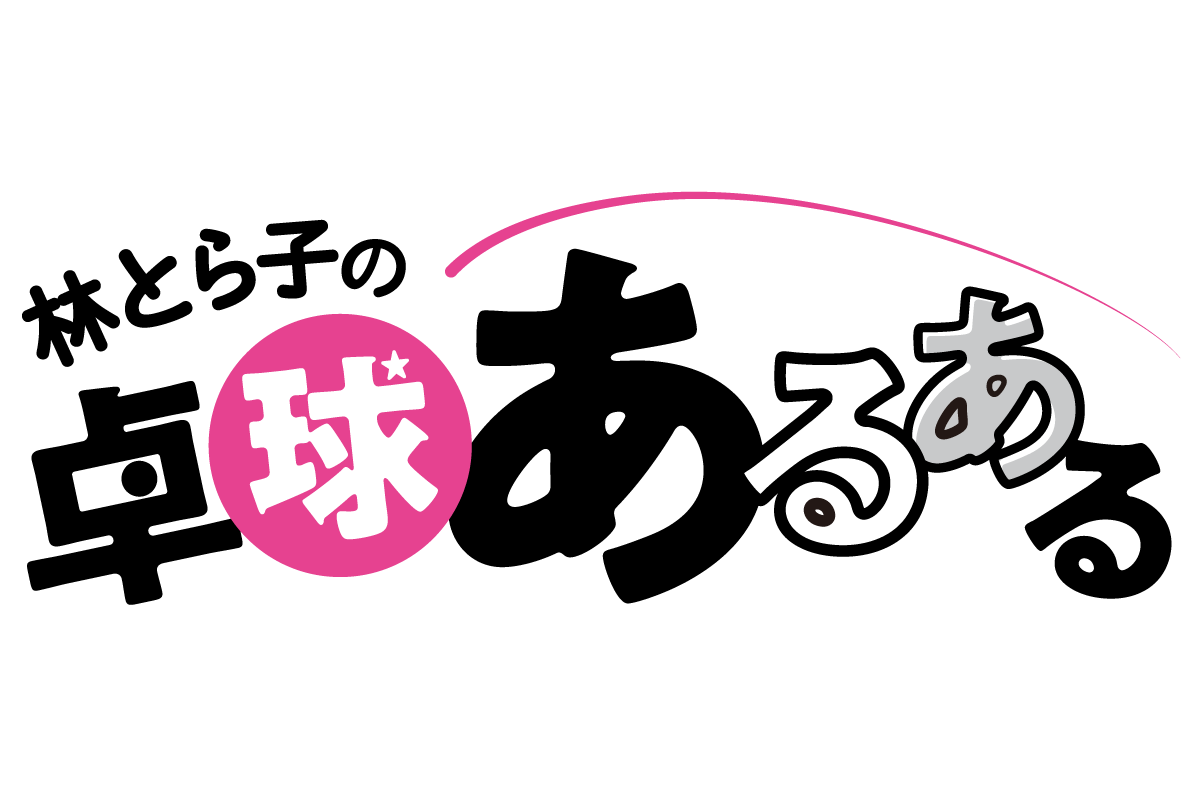勝つ時は失点を1本でも少なく
当然勝つべき試合を落とす。勝てるチャンスのある試合をものにできない。プレーヤーとして、悔しいことである。
1ゲーム目、14-6とリード。もう勝った、と思い無理なボールをスマッシュする。甘いサービスを出してしまう。相手に攻めさせて台から下がってしまう...。
こういうプレーは、たとえ21-15で楽に勝ったとしても、全く感心できない。勝負の厳しさを知らないプレーである。
ポイントを多くとった相手は「これはやれるんじゃないか」と自信を回復する。油断したこちらは、プレーが雑になり、2ゲーム目も甘いプレーになりやすい。調子が出てきた相手。甘いプレーが尾を引く自分。こうなると、たとえ実力差があっても試合の行方は分からない。負けてしまえば、どうしようもない試合ということになるし、たとえ勝っても体力を消耗し、大会を勝ち進むためには全くのマイナスである。
安全なプレーに片寄ってはいけない
長谷川語録に筆者が書いた必勝訓の中に「勝つ時は1本でも少なく、負ける時は1本でも多くとる」がある。
「勝つ時は(失点を)1本でも少なく」というのは、冒頭の例でも分かるように、おおむね自分よりレベルが下と思われる選手との対戦でのことである。自分より強い選手に対しては、大量リードすることも、油断することもまずありえない。
では、大会の1~2回戦で、自分と同レベル、もしくは少しレベルが下の選手と対戦した時のことを考えてみよう。
1本でも失点を少なくする。これは当然ではあるが、失点を恐れて安全なプレーに片寄ってはいけない。相手が弱い時は、ツッツキやショートを多くして凡ミスしないようにしたほうが失点が少なくなるのだが、これでは肝心の調子があがらない。つまらぬ体力消耗をさけ、大会で徐々に調子を上げていくためには、普段の練習どおりの自分のプレーに徹し、積極的なプレーをすることである。試合になったからといって、打ちすぎることも、守りすぎることも、どちらも感心しない。普段の練習の時に、自分がどのくらいの攻守のバランスでプレーしたらよいかを考えておき、実戦では、自分の調子、相手の戦型により若干の調整をする。
油断せずに厳しく攻めることが大切なのであって、攻守のバランスは原則として崩さないことである。
自分の最高のプレーで最少失点を狙う
しかし、もし相手よりも自分のほうがはっきり強いと自覚できるならば、攻めを多くしたほうがよりよい。これは大会で絶好調のプレーに持っていくためである。
台上のサービスに対しては鋭く払うレシーブを多くする。ストップや逆モーションレシーブから積極的に攻めていく。3球目攻撃はフォアハンド(バックハンドが得意な選手はバックハンド)で積極的に攻めていく。また、サービスはショートサービスばかりに片寄らず、ロングサービスを多く使っていく。
このように、攻め主体のプレーにもっていくと ①.足が動くようになる ②.自分の得意な技術をチェックできるようになる ③.体力の消耗を最小限で抑えられる ④.勝ち進むごとに調子が上がる...といった効果が期待できる。
勝つ時は失点を1本でも少なくする。油断なく、厳しく積極的に攻めるよう心がけよう。
大逆転はあきらめない試合態度から
「勝つ時は1本でも少なく」の対(つい)となる言葉が「負ける時は1本でも多くとる」である。
選手の中には、大会で「これは勝てない」と判断すると、試合の中盤で、試合をさっさと投げてしまう選手がいる。これは論外である。精神的によほど弱いか、練習にまじめに取り組んでいないかのどちらかであろう。プレーヤーとして責任ある態度ではない。
まあ試合を丸ごと投げるのは論外としても、1ゲームだけならと、大量リードされるとあきらめてしまう選手がいる。しかし、これも感心したことではない。ヨーロッパのプロ選手の中にも1ゲーム目大きくリードされると「もうダメだ。体力温存のため次にかけたほうが得策」とばかりあきらめる選手もいるが、トップのアペルグレンらはまずこんなことはしない。本当に体力面等に何か問題があり作戦的に捨てる場合以外は、強いプロほど試合を捨てない。どのゲームであっても、1本でも多くとるよう心がけるべきである。
11-19と離されてもなぜあきらめてはいけないか。
その理由のひとつはリードされている時はプレーの流れが悪い時だからである。この流れのまま2ゲーム目に入れば、出足でまた悪い展開になる可能性が強い。1ゲーム目の11-19から、こちらが1本でも多くとろうとがんばれば、リードしている相手は早く試合を終わらせようとあせり、ムリな失点がでることもある。その流れにのって15本ぐらいまでとればリズムはこちらに流れてくる。2ゲーム目の出足でいいスタートが切れる。
もし11-19からがんばって相手の油断につけこみ、5本連取して16-19に持ち込めば、流れはこちらにきた上に相手は大きく動揺する。絵にかいたような大逆転劇が生まれるのはこういった時なのである。
苦しくなっても試合を捨てない
どんなに負けていても絶対に試合をあきらめず、ジワリ、ジワリと追い上げてくるプレーヤーは、リードしている方としては本当にイヤなプレーヤーである。作戦的にはつい変わったことをやりたく(崩れやすく)なるし、精神的にも気が抜けない。肉体的にもスタミナを消耗させられる。1ゲーム目をとったとしても、次のゲームに対しプレッシャーを与えられてしまう。そういったプレーヤーを目指すべきである。
また、リードされている時、「このゲームは落としてもいいから1本でも多くとろう」と考えると、勝敗にこだわらなくなり、無心で思いきったプレーができるようになる。冷静かつ客観的に試合が見えてくる。
その逆に「これ以上やっても負けゲームは精神的に苦しいばかりだから、早く負けて次のゲームで勝負しよう」と考えるとプレーが急に雑になる。負けゲームで流れが悪い上に雑なプレーでフォームを崩したのでは、次のゲームで立ち直ることは容易ではない。
練習試合でも全力でプレーする
「勝つ時は1本でも少なく、負ける時は1本でも多く」の必勝訓は、本当に強い選手であれば誰でもが実行していることである。
かつての中国選手は「勝つ時は1本でも少なく」を忠実に実行し、勝つ時は5~6本で相手をたたいてしまった。そのため、周りの国は対戦する前からあきらめの気持ちが先に立ち、実力差以上にカウント差がついてしまう状態が長く続いた。
勝負事の理想は、戦わずして勝つことである。やる前から勝負がついている。やる前から心理的なハンデがあるのであればこんなに勝ちやすいことはない。
卓球はメンタルな部分の多いスポーツである。練習試合の時から1本でも失点を少なくして勝つことを心がけよう。そうすれば「あいつは強い」と周りが自然に思ってくれるものなのである。
その逆に練習試合だからといってちょっとリードすると気を抜く選手はそれがクセになる。実戦でもそれがでる。せっかく強くなるためにゲーム練習しているのならば、気を抜いたプレーで練習時間をつぶすことはない。最高のプレーが連続してできるようにどんな状況でも集中してプレーする。そうすれば自然と集中力が長続きするようになる。プレーに緊迫感がでてくる。練習が身につきやすい。
チャンピオンスポーツとしての卓球に取り組んでいる選手なら、ゲーム練習の時であっても「勝つ時は1本でも少なく、負ける時は1本でも多く」と自分に厳しくプレーすべきである。
もし、チーム内で、実力に差があり、ゲーム練習の時にどうも気が抜けてしまうようならハンデ制を採用する方法もある。1回勝てばその相手と次にやる時は1本ハンデをあげる。そして負ければ1本ハンデを返してもらう。ゲーム練習の時に集中して練習できるように工夫することである。
スポーツとして感動を呼ぶプレーを
どんなに大きな大会でも、いくら強い選手であっても「勝てばいいだろ」式の気を抜いた試合をしたのでは観客の気持ちをゆさぶらない。
「勝つ時は1本でも少なく、負ける時は1本でも多く」を両者が実行したプレーは、プレーに緊張感がある。好ラリーになりやすい。たとえ得点差がついたとしても両者の必死さが伝わればダラダラした試合にはならない。
マラソンなどで、たとえ1位にはなれなくても、すべてを燃やしつくしてがんばる姿は美しい。スポーツとしての感動を呼ぶ。競技として人気のあるスポーツは、必ず全力を出しつくし、本気でぶつかり合うものである。リードしたからといって油断したり、リードされたからといってあきらめたりは絶対にしない。それがスポーツの美しさである。
卓球の試合も、死力を尽して戦う試合は美しい。技術レベルうんぬんより、お互いが全力を出し合う姿にスポーツの良さ美しさがある。
「勝つ時は1本でも少なく、負ける時は1本でも多くとる」
卓球を盛りあげるためにも、常に必死でがんばるプレーヤーであってほしい。
当然勝つべき試合を落とす。勝てるチャンスのある試合をものにできない。プレーヤーとして、悔しいことである。
1ゲーム目、14-6とリード。もう勝った、と思い無理なボールをスマッシュする。甘いサービスを出してしまう。相手に攻めさせて台から下がってしまう...。
こういうプレーは、たとえ21-15で楽に勝ったとしても、全く感心できない。勝負の厳しさを知らないプレーである。
ポイントを多くとった相手は「これはやれるんじゃないか」と自信を回復する。油断したこちらは、プレーが雑になり、2ゲーム目も甘いプレーになりやすい。調子が出てきた相手。甘いプレーが尾を引く自分。こうなると、たとえ実力差があっても試合の行方は分からない。負けてしまえば、どうしようもない試合ということになるし、たとえ勝っても体力を消耗し、大会を勝ち進むためには全くのマイナスである。
安全なプレーに片寄ってはいけない
長谷川語録に筆者が書いた必勝訓の中に「勝つ時は1本でも少なく、負ける時は1本でも多くとる」がある。
「勝つ時は(失点を)1本でも少なく」というのは、冒頭の例でも分かるように、おおむね自分よりレベルが下と思われる選手との対戦でのことである。自分より強い選手に対しては、大量リードすることも、油断することもまずありえない。
では、大会の1~2回戦で、自分と同レベル、もしくは少しレベルが下の選手と対戦した時のことを考えてみよう。
1本でも失点を少なくする。これは当然ではあるが、失点を恐れて安全なプレーに片寄ってはいけない。相手が弱い時は、ツッツキやショートを多くして凡ミスしないようにしたほうが失点が少なくなるのだが、これでは肝心の調子があがらない。つまらぬ体力消耗をさけ、大会で徐々に調子を上げていくためには、普段の練習どおりの自分のプレーに徹し、積極的なプレーをすることである。試合になったからといって、打ちすぎることも、守りすぎることも、どちらも感心しない。普段の練習の時に、自分がどのくらいの攻守のバランスでプレーしたらよいかを考えておき、実戦では、自分の調子、相手の戦型により若干の調整をする。
油断せずに厳しく攻めることが大切なのであって、攻守のバランスは原則として崩さないことである。
自分の最高のプレーで最少失点を狙う
しかし、もし相手よりも自分のほうがはっきり強いと自覚できるならば、攻めを多くしたほうがよりよい。これは大会で絶好調のプレーに持っていくためである。
台上のサービスに対しては鋭く払うレシーブを多くする。ストップや逆モーションレシーブから積極的に攻めていく。3球目攻撃はフォアハンド(バックハンドが得意な選手はバックハンド)で積極的に攻めていく。また、サービスはショートサービスばかりに片寄らず、ロングサービスを多く使っていく。
このように、攻め主体のプレーにもっていくと ①.足が動くようになる ②.自分の得意な技術をチェックできるようになる ③.体力の消耗を最小限で抑えられる ④.勝ち進むごとに調子が上がる...といった効果が期待できる。
勝つ時は失点を1本でも少なくする。油断なく、厳しく積極的に攻めるよう心がけよう。
大逆転はあきらめない試合態度から
「勝つ時は1本でも少なく」の対(つい)となる言葉が「負ける時は1本でも多くとる」である。
選手の中には、大会で「これは勝てない」と判断すると、試合の中盤で、試合をさっさと投げてしまう選手がいる。これは論外である。精神的によほど弱いか、練習にまじめに取り組んでいないかのどちらかであろう。プレーヤーとして責任ある態度ではない。
まあ試合を丸ごと投げるのは論外としても、1ゲームだけならと、大量リードされるとあきらめてしまう選手がいる。しかし、これも感心したことではない。ヨーロッパのプロ選手の中にも1ゲーム目大きくリードされると「もうダメだ。体力温存のため次にかけたほうが得策」とばかりあきらめる選手もいるが、トップのアペルグレンらはまずこんなことはしない。本当に体力面等に何か問題があり作戦的に捨てる場合以外は、強いプロほど試合を捨てない。どのゲームであっても、1本でも多くとるよう心がけるべきである。
11-19と離されてもなぜあきらめてはいけないか。
その理由のひとつはリードされている時はプレーの流れが悪い時だからである。この流れのまま2ゲーム目に入れば、出足でまた悪い展開になる可能性が強い。1ゲーム目の11-19から、こちらが1本でも多くとろうとがんばれば、リードしている相手は早く試合を終わらせようとあせり、ムリな失点がでることもある。その流れにのって15本ぐらいまでとればリズムはこちらに流れてくる。2ゲーム目の出足でいいスタートが切れる。
もし11-19からがんばって相手の油断につけこみ、5本連取して16-19に持ち込めば、流れはこちらにきた上に相手は大きく動揺する。絵にかいたような大逆転劇が生まれるのはこういった時なのである。
苦しくなっても試合を捨てない
どんなに負けていても絶対に試合をあきらめず、ジワリ、ジワリと追い上げてくるプレーヤーは、リードしている方としては本当にイヤなプレーヤーである。作戦的にはつい変わったことをやりたく(崩れやすく)なるし、精神的にも気が抜けない。肉体的にもスタミナを消耗させられる。1ゲーム目をとったとしても、次のゲームに対しプレッシャーを与えられてしまう。そういったプレーヤーを目指すべきである。
また、リードされている時、「このゲームは落としてもいいから1本でも多くとろう」と考えると、勝敗にこだわらなくなり、無心で思いきったプレーができるようになる。冷静かつ客観的に試合が見えてくる。
その逆に「これ以上やっても負けゲームは精神的に苦しいばかりだから、早く負けて次のゲームで勝負しよう」と考えるとプレーが急に雑になる。負けゲームで流れが悪い上に雑なプレーでフォームを崩したのでは、次のゲームで立ち直ることは容易ではない。
練習試合でも全力でプレーする
「勝つ時は1本でも少なく、負ける時は1本でも多く」の必勝訓は、本当に強い選手であれば誰でもが実行していることである。
かつての中国選手は「勝つ時は1本でも少なく」を忠実に実行し、勝つ時は5~6本で相手をたたいてしまった。そのため、周りの国は対戦する前からあきらめの気持ちが先に立ち、実力差以上にカウント差がついてしまう状態が長く続いた。
勝負事の理想は、戦わずして勝つことである。やる前から勝負がついている。やる前から心理的なハンデがあるのであればこんなに勝ちやすいことはない。
卓球はメンタルな部分の多いスポーツである。練習試合の時から1本でも失点を少なくして勝つことを心がけよう。そうすれば「あいつは強い」と周りが自然に思ってくれるものなのである。
その逆に練習試合だからといってちょっとリードすると気を抜く選手はそれがクセになる。実戦でもそれがでる。せっかく強くなるためにゲーム練習しているのならば、気を抜いたプレーで練習時間をつぶすことはない。最高のプレーが連続してできるようにどんな状況でも集中してプレーする。そうすれば自然と集中力が長続きするようになる。プレーに緊迫感がでてくる。練習が身につきやすい。
チャンピオンスポーツとしての卓球に取り組んでいる選手なら、ゲーム練習の時であっても「勝つ時は1本でも少なく、負ける時は1本でも多く」と自分に厳しくプレーすべきである。
もし、チーム内で、実力に差があり、ゲーム練習の時にどうも気が抜けてしまうようならハンデ制を採用する方法もある。1回勝てばその相手と次にやる時は1本ハンデをあげる。そして負ければ1本ハンデを返してもらう。ゲーム練習の時に集中して練習できるように工夫することである。
スポーツとして感動を呼ぶプレーを
どんなに大きな大会でも、いくら強い選手であっても「勝てばいいだろ」式の気を抜いた試合をしたのでは観客の気持ちをゆさぶらない。
「勝つ時は1本でも少なく、負ける時は1本でも多く」を両者が実行したプレーは、プレーに緊張感がある。好ラリーになりやすい。たとえ得点差がついたとしても両者の必死さが伝わればダラダラした試合にはならない。
マラソンなどで、たとえ1位にはなれなくても、すべてを燃やしつくしてがんばる姿は美しい。スポーツとしての感動を呼ぶ。競技として人気のあるスポーツは、必ず全力を出しつくし、本気でぶつかり合うものである。リードしたからといって油断したり、リードされたからといってあきらめたりは絶対にしない。それがスポーツの美しさである。
卓球の試合も、死力を尽して戦う試合は美しい。技術レベルうんぬんより、お互いが全力を出し合う姿にスポーツの良さ美しさがある。
「勝つ時は1本でも少なく、負ける時は1本でも多くとる」
卓球を盛りあげるためにも、常に必死でがんばるプレーヤーであってほしい。
筆者紹介 長谷川信彦
 1947年3月5日-2005年11月7日
1947年3月5日-2005年11月7日
1965年に史上最年少の18歳9カ月で全日本選手権大会男子シングルス優勝。1967年世界選手権ストックホルム大会では初出場で3冠(男子団体・男子 シングルス・混合ダブルス)に輝いた。男子団体に3回連続優勝。伊藤繁雄、河野満とともに1960~70年代の日本の黄金時代を支えた。
運動能力が決して優れていたわけではなかった長谷川は、そのコンプレックスをバネに想像を絶する猛練習を行って世界一になった「努力の天才」である。
人差し指がバック面の中央付近にくる「1本差し」と呼ばれる独特のグリップから放つ"ジェットドライブ"や、ロビングからのカウンターバックハンドスマッシュなど、絵に描いたようなスーパープレーで観衆を魅了した。
 1947年3月5日-2005年11月7日
1947年3月5日-2005年11月7日1965年に史上最年少の18歳9カ月で全日本選手権大会男子シングルス優勝。1967年世界選手権ストックホルム大会では初出場で3冠(男子団体・男子 シングルス・混合ダブルス)に輝いた。男子団体に3回連続優勝。伊藤繁雄、河野満とともに1960~70年代の日本の黄金時代を支えた。
運動能力が決して優れていたわけではなかった長谷川は、そのコンプレックスをバネに想像を絶する猛練習を行って世界一になった「努力の天才」である。
人差し指がバック面の中央付近にくる「1本差し」と呼ばれる独特のグリップから放つ"ジェットドライブ"や、ロビングからのカウンターバックハンドスマッシュなど、絵に描いたようなスーパープレーで観衆を魅了した。
本稿は卓球レポート1991年3月号に掲載されたものです。