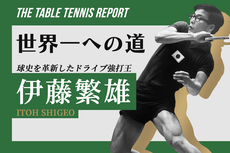死闘の跡
「う、うーん」
伊藤は、ベッドの中で大きな伸びをした。でも、起き上がれない。伸びをした後、ねじが外れたように体中がだらりとしてしまい、力が入らないのだ。
ここは西ドイツ(当時)のミュンヘンである。日はとうに高く昇り、窓から柔らかな光を投げかけている。小鳥のさえずりも聞こえてくる。きっと、マリエン広場の辺りを飛び回っているのだろう。何とものどかな朝だ。つい昨日まで、緊張の最中にあった伊藤には信じられないくらいの、穏やかな空気が漂っている。
伊藤は、けだるそうに傍らのショルダーバッグに手を伸ばした。上半身を起こしてバッグのジッパーを開け、中からラケットを押し頂くように取り出す。伊藤はラバーに、はぁっと息を吹きかけながらなで、ごく自然に話しかけた。
「お前もよくがんばってくれたなあ...」
ラケットを握るとあのときの光景がまざまざとよみがえってくるから、不思議なものだ。
「ん?」
伊藤は、ラバーをさする左手を止めた。スイートスポット部分のシートとスポンジの間がはがれて、ラバーが浮き上がっている。ツブがちぎれたのか、接着剤がはがれてしまったのか、いずれにしても、昨日の試合のすさまじさを物語るものだ。
「俺は本当に世界一になったんだ。とうとう頂点に上り詰めたんだ」
伊藤の心の中に、もう一度熱いものがこみ上げて来た。
............
西ドイツ入り
1969年4月。世界選手権大会の1週間前、伊藤たちの日本選手団は西ドイツで集合した。会場のあるミュンヘンに入る前に、郊外の村で5日間の合宿を行った。気候が日本とよく似ており、最後の調整をするのには適していた。
合宿では、課題点を絞り込んで練習した。イメージ通りに体を動かせるように、「伊藤流」のリズムを分習法で整えた。ゆっくりしたバックスイングから素早い動きに切り替えて相手を惑わすサービス、ボールに向かって襲いかかっていくようなフォームの威力あるドライブ、バックのコーナーぎりぎりまで回り込んで攻め続けるフットワーク。伊藤の卓球に欠かせない重要ポイント、逆に言えば、これさえしっかりとしていれば必ず勝てるという、戦術・技術の根幹の部分である。
サービス、レシーブ、5球目、6球目までの展開を想定したシャドープレーはもちろんのこと、コートの上に万年筆のキャップを置いて自在に狙い打つなどの工夫もした。
世界選手権大会に臨んでの伊藤の目標は、まず団体戦を制することだった。というのも、彼の頭には、母校の専修大学に受け継がれていたある言葉が、強烈に刻み込まれていたのである。それは、かつて世界選手権大会の女子団体戦で日本を優勝に導いた、渡辺妃生子先輩の一言だった。
「海外に出て戦うなら、団体戦で優勝しないと意味がないのよ。団体戦のメンバーになれず、個人戦にだけ出場するくらいなら辞退しなさい。どうせ負けてしまうんだから」
こうハッパをかけられた伊藤は、奮い立っていた。
そうして団体戦で勢いを付けて、個人戦でもベスト4以上を目指す。このときの世界選手権大会は、男女シングルス、男女ダルブス、混合ダブルスの準決勝以上を、最終日にまとめて行う日程で開催されていた。つまり伊藤は、個人戦の全種目で最終日に残って、そこから本当の勝負をすることに懸けていたのだ。
この目標を達成するためには、調子のピークを前半の団体戦と最終日に持っていかなければならない。いざというときに最高の力が出せなくては、元も子もないからだ。10日間の日程のこなし方については、全日本選手権大会での経験をそのまま生かせば、狂いがないと思われた。
自己管理には細心の注意を払って体調を整えており、闘志も十分である。しかし、少しでも気を緩めると、不安が心をよぎる。なにしろ、初めての世界選手権大会である。日本の卓球人のためにも、友人や先輩、家族のためにも、日本チャンピオンの名に恥じない、立派な成績を残さなければならない。そう思うと、自然と体が硬くなる。
これまでの傾向から、日本選手は世界選手権大会初出場での優勝の可能性が高いと言われていた。男子では佐藤、荻村、田中、長谷川、女子では大川、松崎、深津、森沢の各選手が、この偉業を成し遂げた先人として挙げられる。伊藤はこれを自分に当てはめて、弱気になりそうな自分を鼓舞した。
ゴモスコフ戦
団体戦で日本男子は、ハンガリー、デンマーク、イングランド、ユーゴ、ソ連(当時)に勝って、準決勝リーグを突破した。決勝戦の相手は、西ドイツだった。
開催国としての勢いも手伝った西ドイツは難敵だったが、日本代表の伊藤、長谷川、河野は5-3でこれを下した。2大会連続7回目の優勝だった。
男子シングルスでも伊藤は、当初の思惑通り順調に勝ち進んだ。その伊藤が準々決勝で対戦したのは、ソ連のゴモスコフだった。直前の交歓試合で2連敗している、あのゴモスコフである。
しかし、今度の伊藤には勝算があった。交歓試合を通して練り上げた、対ヨーロッパ選手の戦術を使うときが来たのだ。すなわち、「相手のフォアハンドは日本選手のバックハンド、相手のバックハンドは日本選手のフォアハンド。相手のフォア半面と自分のコート全面を使って、フォアハンドで攻める展開にする」という作戦である。
立ち上がり、ゴモスコフは下回転サービスを、伊藤のバックに出してきた。
タタタタ、ガバーッ。
伊藤はすかさず回り込んでバウンドの頂点をとらえ、得意のバックストレートへドライブで攻めた。しかしゴモスコフも伊藤のこのレシーブを読んでいて、スナップを利かせた打球点の早い合わせ打ちで、フォアクロスに返して来た。コーナーを切る鋭いボールで、ノータッチで抜けていく、と観客の誰もが思った。
ところが、こっちはのんきに構えているような伊藤ではない。ゴモスコフの動きを読んでコースを見極め、しゃにむにボールに飛びついた。
すると、奇妙なことが起こった。ボールが伊藤の腰に命中したのである。ノータッチで抜かれると思われたボールに、伊藤は追い付いたばかりではなかった。勢い余って、ストライク位置から半歩分も行き過ぎてしまったのである。
伊藤の「珍」プレーに、観客席からは失笑が漏れた。しかし当の伊藤は、このときすでに勝利の手応えを感じていたという。
「俺の足は、自分が思っている以上に速く動いている。今の失敗は、絶好調だということの証明なんだ。うん、自信を持ってやっていい」
その後の展開は作戦通りだった。コートの周りをひたすら動き回り、強ドライブでゴモスコフのフォアを攻め続けた。そして、それまでの2敗が嘘のような会心の内容で、この試合を制したのである。
伊藤 18、16、15 ゴモスコフ。
伊藤の強ドライブには、ますます磨きがかかってきた。しかしこのとき、鋭い観察眼で興味深いことを見抜いた人がいた。元世界チャンピオンの荻村伊智朗氏である。彼は伊藤にこう話したという。
「伊藤、今日のバックハンドはよかった。ゴモスコフが鋭くバックに送って来てもまったく後退せず、体の前でボールをとらえて、上から打ち下ろすようにストレートに持っていっていた。つなぎのバックハンドとは言っても、打球点が高くて勢いがあったから、ゴモスコフにすきを与えなかったな」
強ドライブとスマッシュで次々に得点を決める、豪快な面が強調されがちな伊藤のプレースタイルだが、その裏には、チャンスを引き出すためのしっかりとしたつなぎ技術があったのである。確実で、しかも相手の弱点を突くバックハンドが下支えになっていたからこそ、伊藤のフォアハンド技術は光ったのだ。ここでももちろん、鍛錬に鍛錬を重ねて身に付けた下半身の力、特にひざの柔軟性が発揮されていた。
決勝前夜
伊藤と同じく男子シングルス準々決勝を勝ち抜いたのは、日本の笠井と田阪、それに西ドイツのシェラーだった。伊藤の次の相手は、愛工大のカットマン・笠井だった。
河野と組んだ男子ダブルス、小和田と組んだ混合ダブルスでも、伊藤はベスト4入りを果たしていた。
その晩、伊藤は宿舎の部屋に戻って落ち着いたものの、なかなか寝付けなかった。緊張しているというより、もっと高次の異常興奮状態にあったと言った方がよさそうである。
いよいよ、自分の力のすべてを発揮するときが来たのだ。
「世界選手権大会で優勝したい」
2年前の4月29日、ストックホルム大会で優勝した長谷川たち一行を羽田空港で迎えたあの『第2の誕生日』以来抱き続けて来た最高の目標に、明日挑むことができるのである。ついに、燦然(さんぜん)と輝く星のすぐそばまでたどり着いたのだ。
「さあ、今こそ力の限り手を伸ばして、しっかりとこの手のひらにつかもう」
伊藤は、大きく広がる可能性を前に、幸福な気持ちに溢れていた。
ところが、困ったことに気づいた。眠れないのだ。
本番で身体的、精神的なプレッシャーに打ち勝つためには、できるだけ睡眠を取って心身を休めておかなければならない。それなのに、何としてもチャンピオンの栄冠を勝ち取りたいと思うと体中が熱くなり、どうしても目がさえてしまう。
二重の思いに苦しみながら寝返りを繰り返すうち、伊藤の脳裏に、ある言葉が浮かんだ。専大の先輩でかつて世界を2度制した、松崎キミ代さんのアドバイスである。
「大事な大会の前夜というのは、眠れなくて当たり前です。でもね、1晩くらい寝られなかったくらいで試合ができないなんてことは、絶対にありません。横になって目をつぶるだけでいいんですよ。そういうときの方が、かえっていい試合ができるものです」
この言葉を何度も反芻(はんすう)しながら、伊藤は、プレッシャーをプラス方向の自己暗示へと変えていった。
「そうだ、眠れないのは勝利の前兆なんだ。明日はきっと、万全の体勢で向かっていけるぞ」
高ぶっていた気持ちはすうっと落ち着き、伊藤は泥のように眠りこけた。
その日
翌朝は、すっきりと目覚めることができた。伊藤は一人でそっと部屋を抜け出して、ランニングに出かけた。全身に精気がみなぎっているのが分かった。
男子シングルス、男子ダブルス、混合ダブルスの3種目の準決勝と決勝を、すべてゲームオールで戦ったとしたら30ゲームである。
「もう体がどうなってもいい。今日1日に懸けよう」
伊藤はこう自分に言い聞かせた。
ダブルス2種目は、準決勝で敗れたが、男子シングルスの準決勝では、笠井に3-0で勝った。決勝の相手は、田阪を3-2で倒したカットマンのシェラーである。伊藤は彼と団体戦で対戦し、ゲームオールで負けていた。
このシェラーのカットは、日本選手の持っていたカットのイメージとかけ離れていた。フォロースルーが極端に短く、手首でラケット角度を合わせるだけでカットしているように見えるのに、飛んで来るカットがズシンッと腕に響くくらい重いのだ。腕の筋力と下半身のバネが、よほど強いのだろう。
その上シェラーは、100メートルを11秒台前半で走ると言われており、守備範囲の広さも群を抜いていた。
そうかと思うと、カットのバックスイングで腰の辺りまで切り下ろすように見せかけながら、いきなり手首を返してフォアハンド攻撃を仕掛けて来たりもする。てっきりカットが来ると予想しているところに、突然ライナー性のスマッシュが襲って来るために、逆を突かれると簡単に抜かれてしまうおそれがある。伊藤は普段、対カットマン戦を得意としていながら、団体戦の決勝ではシェラーに煮え湯を飲まされていた。このときの反省から、大津監督は伊藤に、「粘っていけ。浮いた甘いボールだけを強ドライブやスマッシュで狙うんだ」とアドバイスした。伊藤は控室に入った。
命しらずにゃ敵がない
とうとう決勝の時が来た。このようなときは、一人静かに座り、絶対に勝てると自己暗示をかけて気持ちを高めていくのが、伊藤の常である。しかし、この日は違った。ぴりぴりとした緊張状態にあるはずの伊藤の口から漏れて来たのは、何と演歌だったのである。
君は誰だと聞かれたときに
おれは男と答えたい
いつもにっこり
笑って死ねる
命知らずにゃ敵がない
命知らずにゃ敵がない
(中略)
下に優しく上には強く
腹は立てるな気は長く
おれの出番は一生一度
そうだその意気その我慢
そうだその意気その我慢
水前寺清子の「命知らずにゃ敵がない」だった。伊藤は目を閉じ、下腹に気を入れて歌い続けた。なぜこのような重要なときに歌が出て来たのか、伊藤自身にも分からなかった。しかし、日本選手の最後の砦(とりで)となった孤独感は、相当なものだったはずである。これを払拭するためには、歌で丹田に意識を集中させるしかなかったのかもしれない。事実、「そうだ、その意気、その我慢」と口に出しているうちに、わずかに心の隅に残っていた不安は完全に消え去り、不思議なほどリラックスすることができたという。
試合に勝つためには、勝利への執念を持ち続け、闘志を高めることが不可欠である。しかし、勝利欲だけを先行させてしまっては、かえって体をこわばらせ、不満足な結果を招くことにもなりかねない。野望を抱きながらも、心の奥底は冷静な状態に保ち、体はリラックスさせるという、相反する2つの要素が同時に大切なのだ。精神を緊張させつつ弛緩(しかん)させる、この微妙なバランスをうまく保ってこそ、大舞台で実力を発揮することができるのである。
「命知らず」「出番は一生一度」「我慢」といった歌詞の一つひとつは、伊藤の心をそのまま代弁していたのであろう。
伊藤はすっと立ち上がり、フロアに向かった。
2階席には、横断幕が何枚も張られていた。満員の大観衆が大声を上げ、ドンドンと足を踏み鳴らすために、会場全体が揺れ動くような感覚に襲われる。
第1ゲームが始まった。伊藤は作戦通り、少し威力を落とした確実なドライブで粘った。そして、チャンスボールだけを得意の強ドライブやスマッシュで狙い打ちしようとしたのである。ところがシェラーの守備は、予想以上に堅かった。1発や2発のスマッシュではびくともしない。
自信を持って攻めても返って来るシェラーのカットの変化に惑わされ、凡ミスを重ねてしまった。左右に大きく揺さぶられるほとんどのボールにフォアハンドで対応していたため、体力を過剰に消耗して自分のペースを崩すことにもなった。
その上、フォアに大きく動かされて苦し紛れにクロスに返したボールを強打されての失点が続いた。
ゲームは一貫してシェラー優位で進み、伊藤は第1、第2ゲームを落とした。
伊藤 -19、-14 シェラー
第2ゲームの最後は、それまでのすべてを忘れようと、目をつぶったまま3球目を引っぱたいた。
日本選手団のベンチには、早くも落胆した雰囲気が漂っていた。伊藤を勇気づけようと励ます仲間たちも、目に浮かぶ悲痛な色は隠せないでいた。
しかし、伊藤の頭の中にはすでに、第3ゲームからの新しい作戦ができあがっていた。
そのポイントは3つあった。
①攻めるコースをバックからミドルまでの範囲に限定する。カットの変化を付けられやすいフォア側は極力避けなければならない
②チャンスボールをただ待っていたのではらちが明かない。カットに対して最初から威力あるループドライブで攻め、甘く浮かせてからバックを目掛けてスマッシュを打ち込む
③バックに大きく動かされたときに、無理にフォアで回り込まずにツッツキでつなぎ、シェラーを前に寄せてから、またドライブでチャンスを作り出す
大津監督や田舛総務も、同じ意見だった。
とにかく相手に呑まれず、戦略と戦術を徹底させて伊藤流のペースをつくっていくことである。シェラーには、総勢6000人の地元の大観衆がついていた。ヨーロッパからは、1953年以来男子シングルスの世界チャンピオンが出ていない。シェラーの応援に観客の熱が入るのも、無理からぬことだった。
一方、日本選手団は男女合わせても40名程度に過ぎない。普通なら、気後れして当然だろう。
伊藤は、ゆっくりとした足取りでコートに戻った。床を踏みしめて一歩進むごとに、伊藤優位のイメージの世界に入っていくかのような、しっかりした歩き方だった。
逆転劇
第3ゲームが始まった。驚いたことに、戦術を転換しただけで、あれほど苦しかったフットワークに見違えるような余裕が出てきた。それだけにスマッシュチャンスも逃すことなく、シェラーの堅陣を的確に打ち抜くことができ、このゲームで初めて伊藤リードのうちに終盤を迎えた。
20-17。
ところが、心のどこかに緩みが生じたのだろう。伊藤はここでスマッシュミスを重ねた。
20-19。
「20オールに持ち込まれたら、俺の負けだ」
伊藤の目の前が白くなった。マラソンレースのゴール前で併走者に追い付かれ、振り切り損なったランナーと同じで、ばん回された側がもう一度引き離して勝つのは、追い抜いて勝つより困難である。
「次の1本が勝負だ。これを取れば絶対に第4、第5ゲームも取れる。腹をくくって、この1本に俺のこれまでの卓球人生を賭けるしかない」
伊藤が出したのは、バックミドルへの下回転サービスだった。シェラーは低い軌道のカットでクロスに返してくる。伊藤は素早く回り込み、強ドライブを仕掛けた。
1球、2球...。
チャンスはなかなかやって来ない。それならばと伊藤は、次のボールをツッツき、シェラーをいったん前陣に引き寄せてから再びドライブで攻めた。
この揺さぶりが効いて、カットがようやく浮いて返ってきた。伊藤は、全身の力を込めて強打した。彼が放ったのは、フォアクロスへの重いスマッシュボールだった。一発で抜けはしなかったが、次のボールはやや短く、浮いてミドルに返って来た。しかも、シェラーは剛球をしのいだ後で、体勢を崩している。
「しめた!」
伊藤は、シェラーのフォアにとどめのスマッシュを打った。
「うっ」
伊藤は自分の目を疑った。またもやシェラーのラケットが、ボールの軌道を断ったのだ。
ボールは伊藤を嘲(あざ)笑うかのように、ゆっくりと深くに飛んで来た。
「入るな。絶対に入らないでくれ!」
伊藤は、スマッシュを打ち終えたフォロースルーの体勢のままだった。絶対に打ち抜けると確信していたために、次球に備えてニュートラルの位置に戻るという初歩的なことを忘れてしまったのだろうか。いや、渾身(こんしん)の力を込めて強打したために、基本姿勢に戻りたくても手足が思うように動かなかったのかもしれない。
「あのボールが入っても、もう取れない。頼む、入ってくれるな」
伊藤は祈るような気持ちだった。
ボールは、テーブルからほんの数センチほどのところでアウトした。伊藤はパシッと左手で受け止めて胸をなで下ろし、走ってベンチに戻った。
何よりも、心の緩みを戒めなければならなかった。試合では、豪快なスマッシュを決めてやろうと格好を付けたり、必要以上に勝ちを意識したりといった雑念を抱いてはならない。本当の敵はシェラーではなく、自分自身だったのだ。2度と第3ゲームの轍(てつ)を踏んではいけない。無欲無心になるのだ。体を鍛え込んだ伊藤にとって、疲労は必ずしもマイナス要素にはならない。むしろ、体から無駄な力みを取り除いてくれるはずである。
第4ゲームに入った伊藤の耳には、会場全体にとどろく喚声も聞こえなくなった。意識の中に存在しているのは、シェラーと伊藤自身だけだった。試合は終始伊藤のリードで進み、21点目も1本でものにした。
21-16。
伊藤にとって精神的に苦しかったのは、リードしてスコアに大きく差を付けた、最終ゲームだった。第3、第4ゲームを伊藤に取られて焦ったシェラーが、無理な反撃に転じて自らペースを崩し、前半で一気に10点近くもの差がついてしまったのである。
4-1、8-2、11-4。
「これだけリードしているんだ。もう追い付かれることはないだろう。少しくらい楽をしたって...」
疲労も手伝って、こんな雑念が心のすき間に入り込んで来る。
14-6、18-7。
「いや、駄目だ。第3ゲームであれだけ苦しんだじゃないか。最後の1点を取るまで、絶対に気を抜いてはいけない」
もう一人の自分が、弱い心と疲れた体をむち打つ。ゲームの後半には、シェラーの存在さえも意識から消え去ってしまい、ただただ自分との戦いになった。伊藤が1本取るたびにシェラーが取り返す攻防が繰り返された。しかし、シェラーもすでに疲労の極限にあって、伊藤の葛藤と動揺に付け入ることができない。ゲームは10点の差を保ったまま、20-9でマッチポイントとなった。
伊藤は、斜め上回転サービスをミドル前に出し、フォアに返って来たボールを全力でスマッシュした。次の瞬間、伊藤はもうガッツポーズをしながら相手コートに走り寄り、シェラーに握手を求めていた。最後はすべて、思い描いたシナリオ通りだった。長い苦闘の末、ついに世界チャンピオンの栄冠を手にしたのである。
チームメートや記者、カメラマンがどっと押し寄せ、伊藤はあっという間にもみくちゃにされた。誰かに抱き上げられて優しい言葉を投げかけられたとき、初めてほおを熱いものが伝った。
恍惚(こうこつ)として勝利に酔いしれる伊藤には、もう、何が何だか分からなかった。女子選手の泣き顔が見える。長谷川や河野をはじめとする男子選手の顔も、今にも崩れそうだ。監督やコーチがうんうんと何度もうなずいているのも、目の奥で感じられた。
そんな中で伊藤は、脳裏にちらつくある面影を追っていた。故郷で待つ、母の小さな姿だった。
キャプテンとしての、そして日本チャンピオンとしての責任を果たせたのだ。これで胸を張って日本に帰れる。卓球の道に進むことを許してくれたおふくろに、やっと恩返しができたんだ。
初めてラケットを握ったときのこと、思うように卓球ができなかった就職時代、無名選手として屈辱を味わった専修大入学当初、長谷川の世界選手権大会優勝を機に生まれ変わってからの選手生活。その陰にいつも母の姿があった。母親が支えてくれていなければ、今の伊藤はなかった。
各国の旗が打ち振られ、伊藤の大健闘をたたえる観客の拍手は、いつまでも鳴りやまなかった。
球史を革新したドライブ強打王、伊藤繁雄。その名は、これから先も世界の卓球人に長く語り継がれていくに違いない。
(2001年12月号掲載)