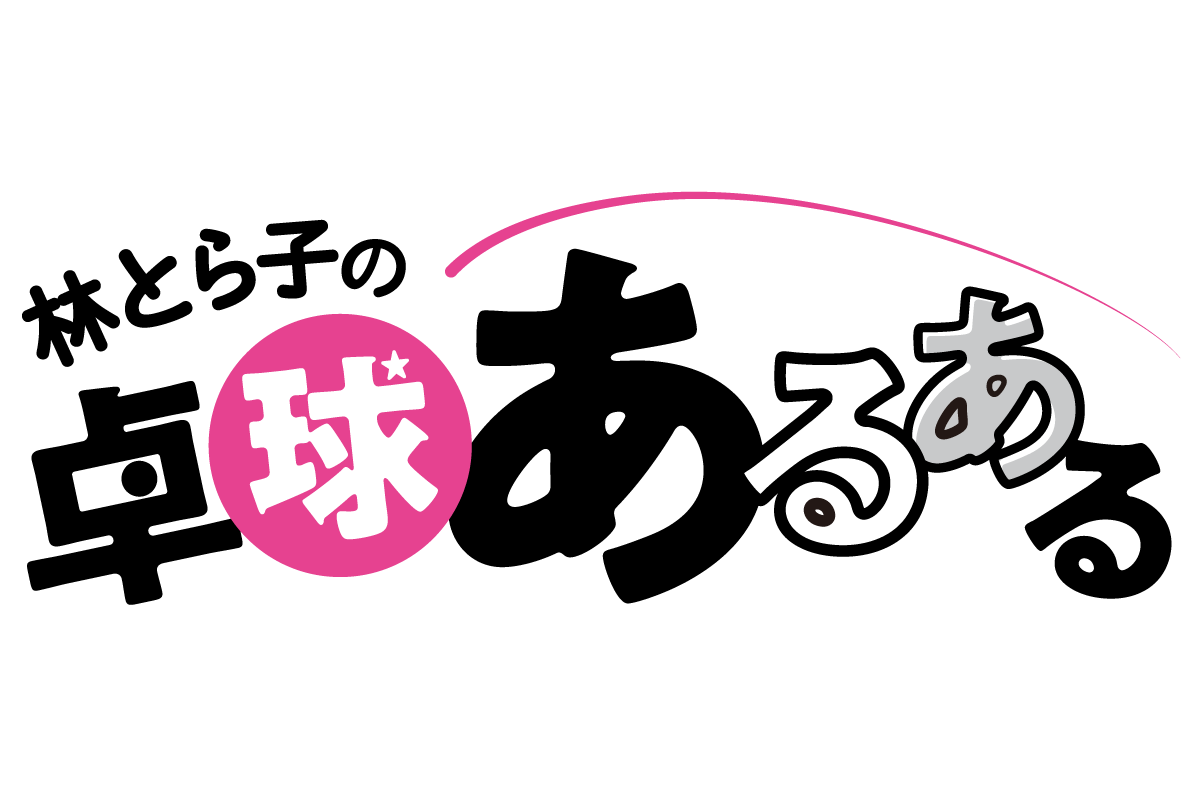冨士枝の日課
「おつかれー」
「明日ねー」
夕方5時になると、みんなはいっせいに校門を出る。学校の規則で、練習場を使えるのは夕方5時まで。それまで一生懸命卓球で汗を流した部員たちは、それぞれの家路につき始めた。しかし、冨士枝の1日はまだ終わりではなかった。
「冨士枝は今日も上六(うえろく)?」
「うん。行ってくるー」
学校の練習が終わったら、上六にある卓球場に移動してまた練習する。それが冨士枝の日課だった。
上六の卓球場にはいろいろな人が来る。仕事帰りの人、小さな子ども、男も女もいろいろな人が来る。いろいろな世代、いろいろな個性が集まるこの場所は、冨士枝にとって大切な勉強の場だった。学校には熱心な男子部員はいなかったが、ここでは男の人のボールを受けることもできた。
「冨士枝ちゃんのフォアはいいなあ」
「ほんまに?」
「フォアだけはな」
「あうー」
そんな軽口をたたきながらも、いざラリーが始まると冨士枝はすぐに真剣になった。練習ができる時間は限られている。1球だっておろそかにせず、常に集中して臨むというのが冨士枝の信条だった。
そうして結局夜9時くらいまで上六で練習。しかし、冨士枝の1日はそれでもまだ終わりではなかった。
「ありがとうございました」
卓球場を後にした冨士枝は、荷物を持ったまま走り出した。足腰を鍛えなくちゃ。そう考えていた冨士枝は、移動はすべてランニングと決意していた。家から学校、学校から上六、上六から家。合計すれば、1日10キロ以上の道のりを走っていたことになる。
涼しい顔で人知れず努力する。冨士枝はそんな女の子だった。練習後の体を引きずって走るのはつらかったが、自分で決めたことを途中で投げだすのはもっと嫌だった。
反対
「冨士枝、何度言えばわかるんだ?」
家に着くなり、父親の厳しい視線が冨士枝に突き刺さった。
冨士枝が卓球を始めたころから、父親は冨士枝が卓球をすることに反対だった。卓球をしたところで何の得があるのか。娘には、もっと生きていくのに役立つことを学ばせたかった。父にしてみれば、卓球は単なる道楽に思えた。貧しさを経験してきた父は、生活の糧を得るための職能をこそ娘に学んでほしかった。
そんな父親は卓球のラケットを『めししゃもじ』と罵倒(ばとう)し、娘を一刻も早くまっとうな道に戻したいと考えていた。
「冨士枝、あんな『めししゃもじ』みたいなものを振り回して、一体何が儲(もう)かる?」
しかも、こんなに遅くまで。夜道は危ないんだぞ。それに、運動しすぎで体を壊したりしないか心配だ。
だが、不器用な父はそんな思いを伝える術(すべ)を知らず、いつも声を荒げて冨士枝を叱りつけるのだった。
「うちは美容院だぞ、卓球なんかやるな!そんなひまがあったらお前も少しは美容の勉強をしろ!
しかし、冨士枝には父親の怒鳴り声もまったくこたえなかった。
冨士枝はすっかり卓球の魅力に取りつかれていた。卓球で味わう楽しさも苦しさも、すべてが冨士枝にとって、なくてはならないものになっていた。卓球が大好き。その気持ちは、父親の激しい反対にもめげない冨士枝のパワーの源だった。
「美容を勉強しないならうちを出ていけ!」
そんな言葉にさえ冨士枝はひるまなかった。卓球をがんばり続けたら、きっと父もわかってくれるだろう。冨士枝の発想はどこまでも前向きで一途(いちず)だった。
試合で勝てない
「みんな、がんばろうね」
「もちろん!」
今日は試合の日だ。日ごろの練習の成果を見せてやろう。毎日ランニングをしてトレーニングも積んだ。フットワーク練習も必ずやった。フォアのスマッシュには自信があるし、体調だってばっちりだ。今日はいける。冨士枝はそんな気持ちで大会に臨んだ。
大阪府予選を勝ち抜き、大阪代表として出場する全国高校大会である。冨士枝は闘志満々でコートに立った。
しかし、冨士枝には大きな弱点があった。
「あれ?なんか感じが違う...」
試合会場で初めて対戦する選手に、冨士枝は違和感を感じていた。当たり前である。人によって、放つボールには微妙な違いがある。しかし、冨士枝はその違いに戸惑っていた。
コーチのいない冨士枝たちのチームでは、練習方法をよく知っている者は1人もいない。すると、練習は自然と基礎練習が多くなる。一つひとつの技術は高いレベルになっていったが、冨士枝はそれを戦術的に結びつける術を知らなかった。また、いろいろな場面に対応する応用力も身に付いていなかった。
大阪府内ではそれでも通用した。しかし、全国大会ともなると冨士枝はまったく勝てなかった。
「どう打てばいいかわからない。どうしよう、どうしよう...」
なれない相手の球に戸惑いながら、焦りだけが大きくなっていく。冨士枝は完全にあがってしまっていた。ガチガチに緊張した冨士枝は、試合に臨む上で欠いてはいけない闘志や自信まで失っていた。
あがり性で、本番で力を発揮できない。それは冨士枝の大きな弱点だった。
試合をしながらも、まったくゲームに集中できない。体が思うように動かない。それほど実力の差があるとは思えない相手なのに、まるで勝てる気がしない...。
「ありがとうございました」
また負けた...。基礎的ではあるが自分なりに工夫した練習を積んできた。特にフォアハンドには少々自信があった。そんな冨士枝だが、全国大会ではさっぱり勝てなかった。
後に江口冨士枝はこう語る。
「本当は、負けたときの方がより勉強になるんです。『こういうふうに負けたから、ああしなきゃいけない』っていう部分を勉強する上で、敗戦はとてもいい機会だと思うんです。勝った場合は『やったー、勝った!』で済ましてしまいがちですものね。ですから、本当は勝ったときよりも負けたときの方が、卓球そのものは深くなっていくんじゃないかと思うんです」
しかし、高校生の冨士枝は、まだその発想には至っていなかった。
「あーあ。また負けちゃった」
そして、何度も何度も負け試合を重ねていくうちに、冨士枝の勝ちへの執着は次第に薄れていった。
もともと、両親と4人の姉の他に150人を超える従業員、そんな家庭に育った冨士枝である。人に譲る態度、人に配慮する性格が自然と冨士枝に備わっていた。しかし、そんな個性がここでは裏目に出た。ここ一番というときに人を押しのけて勝利することができず、敗戦を続けていく。冨士枝には、いわゆる「負け癖」がついてしまっていた。そして、そんな状態では、冨士枝は卓球を以前ほど楽しいとは思えなくなっていた。
挫折
「冨士枝、また負けたのか。それでもまだ続ける気か。美容をやれ、美容を」
試合に負けて帰宅すると父が言う。父が卓球に反対するのはいつものことだ。しかし、度重なる敗戦に落ち込み気味の冨士枝に、父の言葉は重く響いた。
父の言う通りかもしれない。卓球なんかに夢中になっていないで、もっと現実的なことを考えなくちゃ。高校を卒業したら、手にきちんと職を持った方がいいだろう。4人の姉たちは全員美容師の資格を持っている。私も家業の美容院を継ぐべきかもしれない。冨士枝は次第にそんな考えを持つようになっていった。そして、高校の授業と卓球の練習の傍ら、美容師の資格も取ったのだった。
やがて、高校卒業が近づくにつれ、冨士枝はますます自分の進路を悩むことが多くなった。卓球をやるのか、家業を継ぐのか。2つの選択肢に揺れながら、冨士枝の思考は徐々に卓球から離れる方に傾いていった。
本当はもっと強くなりたかった。全国レベルで活躍したいと思っていた。特別に才能がないのはわかっていたけど、そのぶん人の何倍も努力しようと思ってがんばってきた。でも...。全国大会では全然勝てなかった。やっぱり才能がなかったらダメなのかな。あきらめた方がいいのかな。卓球は大好きだけど、全然勝てない。卓球は私の進むべき道じゃないのかもしれない。
―もう、やめよう。
冨士枝はとうとう決心した。卓球を捨てる覚悟だった。挫折感。切ない思いがないわけではなかった。しかし、これがベターな選択だと思った。
高校を卒業と同時に、冨士枝は美容師の見習いとして父の経営する丸善美容院に入った。丸善美容院は高島屋百貨店の中にある大美容院だ。大勢の店員たちに立ち交じって働きながら、冨士枝は人を和ませるそのキャラクターで周囲にすぐに溶け込んだ。新しい生活がスタートしたのだ。
毎日忙しく働きながら、冨士枝は腕のいい美容師になることだけを考えた。これで本当に卓球とは縁を切った。二度とラケットに触れることもない。未練もない。そんなことを思っていた。
再スタート
卓球とは縁を切った。そう考えていた冨士枝だが、これまであれほど夢中に打ち込んできた卓球である。そんな状態が長続きするわけはなかった。
「さあ、江口さんもやろう」
「はーい」
気づけば冨士枝は高島屋卓球部の一員になっていた。
しかし、卓球部と言っても中学校や高校時代の環境とは大きく違う。練習場は社員食堂だ。自分たちの昼休みや就業後で、なおかつ食堂が空いている時間帯を見計らっては卓球に興じる。部員たちは楽しく練習し、冨士枝も仲間と一緒に楽しんではいた。しかし、どちらかと言えばレクリエーション的傾向の強いクラブであり、技術レベルは低かった。
冨士枝はもの足りなさを感じながらも、足しげくクラブに顔を出した。一度は縁を切ったと思った卓球に再び興じていることが、なんだかとてもうれしかった。私はやっぱり卓球が好きなんだ。やめられないんだ。
苦い絶望感とともに一度は背を向けた卓球だったが、冨士枝はいつの間にか再び向き合うようになっていた。卓球が好き。単純なだけに、それは抑えようのない思いだった。
さて、高島屋の卓球部に所属した冨士枝は、大会にも出るようになった。しかし、当時は実業団の大会が少なく、百貨店対抗大会などというのが高島屋卓球部にとってのメインイベントだった。
もっと試合をしたい。もっと自分の卓球を磨きたい。もっと卓球がやりたい。父の美容院で修行を初めて1年が過ぎ、冨士枝の卓球への衝動は爆発寸前だった。このままあきらめたくない。卓球をやりたい。そのためには、もっと卓球のできる環境へ移りたい。
―父に相談しよう。
わかってもらえるかは自信がない。でも相談してみよう。冨士枝は覚悟を決めた。
医者になれ?
「なあ、お父さん。聞いてくれる」
冨士枝は父に話を切り出した。何の儲けにもならない卓球をやりたいなど認めてもらえるはずもないと思いながらの、恐る恐るの相談だった。
「じゃあ大学に行ったらええ」
しかし、意外にも父はこんな提案をしてきた。冨士枝は耳を疑った。だが、話には続きがあった。
「でも、医科以外はあかん」
冨士枝はきょとんとした。医科コース?私に医者になれと言うのだろうか。
「これからの美容には医者の資格が必要だ。髪や化粧をいじるだけじゃ限界だ。これからの美容は普通の美容師の上を行くトータルな美容師じゃなければいけない。医者の資格を持った美容師がお客さんの体全体を美しくする、それしかない」
美容整形も何もかもひっくるめたトータル的な美容。それが父の理想だった。ときは1950年代である。その早くからこの発想を持っていた冨士枝の父の慧眼(けいがん)は驚きだ。
しかし、冨士枝は父の話に面食らってしまった。
「え、私が医者に?そんなの無理だよう」
「だったら大学はあきらめろ」
「そんなあ」
「とにかく、医科以外の学校は学校とは認めんからな。絶対医科だけだ」
後になってこの父の偉大さがわかったという冨士枝だが、そのときはただただ悔しく、悲しい気持ちだった。
「なんで?こんなに卓球が好きなのに許してくれないなんて...」
うつむいたら目から涙が落ちた。
しかし、冨士枝に選択肢はなかった。何としてでも大学の医科に合格しなくてはいけない。合格しなければ、卓球への道は閉ざされたも同然だ。
コツコツと、冨士枝の受験勉強が始まった。もともと人一倍がんばり屋の冨士枝である。昼は美容院で働き、夜の時間を受験勉強に充てた。美容師と受験生の二重生活は楽ではなかった。朝から夕方まで懸命になって働いた体は、夜になるとすぐに激しく睡眠を求めた。しかし、卓球ができる環境を夢見て、冨士枝は毎晩机に向かった。
そして、1952(昭和27)年4月、冨士枝は晴れて大阪薬科大学の医科コースに入学した。このとき冨士枝は19歳だった。
「運」を引き寄せろ
「冨士枝」
見事大学合格を果たした冨士枝に、父は言葉をかけた。このときの言葉を冨士枝は今でも大切に記憶している。
「冨士枝、お前がどうしても卓球をやるんだったら、もう反対はせん。反対はせんけども一つ言っておく。
人は『運がいい』とか『運が悪い』とか言うだろう。だけど、運のいい悪いを決めるのは、やっぱりその人次第だ。『運』っていう字をよく見ると『いくさ(軍)』っていう字を書くだろう。『いくさ』っていうのは命がけでやるものだ。でも、命がけで『いくさ』をしてもまだ足りなくて、それに『しんにょう』を足して初めて『運』になるんだ。
だから、命がけのいくさでさえも、それだけじゃまだ足りない。何かそれ以上のことをやらなけりゃ運を引き寄せることはできないんだ。人と同じようないくさ、人並みの努力をしてたってそれでは運は向いてこない。命がけのいくさをして、さらに何かを足さなければ人には勝てないんだぞ」
父の語る人生訓は、冨士枝の胸を打った。いつも反対ばかりで頑固な父だと思っていたが、ずっと自分を応援していてくれたことがわかった気がした。
人並み以上に努力して、さらに自分を超えるような努力をすること。冨士枝は父の言葉を胸に刻んだ。この父のためにもがんばろうと思った。
「よーし、卓球がんばるぞ!」
冨士枝の胸は期待でいっぱいだった。そして実際に、冨士枝はこの大学時代に選手としての才能を開花させ始める。
しかし、大学生活は思ったほど甘くはなかった。もっと卓球をしたいという思いで入った大学だが、冨士枝はそこでこれまで以上に卓球への渇望を抱くことになるのである。
(2002年2月号掲載)