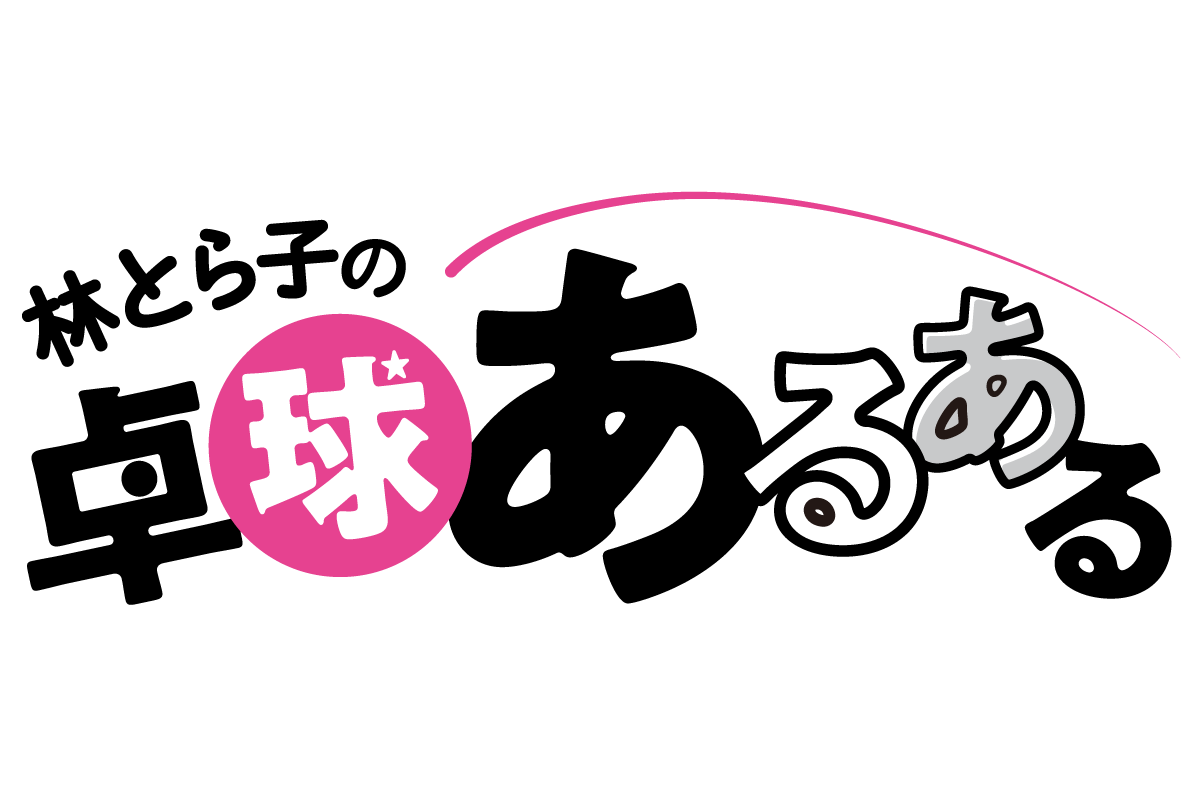逆風をはねのけ
1954(昭和29)年の世界選手権ウェンブレー大会で、日本は男子団体・女子団体・男子シングルス(荻村伊智朗)と3種目に優勝した。日本選手団は意気揚々と凱旋(がいせん)し、団体戦メンバーとして戦った冨士枝にも多くの称賛が寄せられるかと思われた。しかし、日本に帰った冨士枝を待っていたのは思いがけない批判だった。
「卓球の江口冨士枝はアマチュア規定に違反した活動を行っている。けしからんことだ」
新聞にこのような記事が掲載された。
当時、日本のスポーツ界はかたくなにアマチュアリズムを守っていた。収入を目的とせず愛好するためにのみスポーツを行うアマチュアが尊重され、スポーツで収入を得るプロフェッショナルは蔑(さげす)まれる傾向があった。
「卓球の江口はアマチュア選手でありながら広告出演をしており、これは大問題である」
問題とされたのは、冨士枝の実家の美容院に飾られた1枚の写真だった。
女性がスポーツをするときのヘアスタイル。美容師として働いていた冨士枝の姉が熱心に研究していた課題がこれだった。当時、髪を短くカットしている女性は少なかった。しかし、スポーツに適したヘアスタイルを考案中の姉は、思い切って短くカットしたヘアスタイルを提案した。このときカットモデルとなったのが冨士枝だったのである。美容院には冨士枝の写真が飾られた。そして、これが物議をかもした。
アマチュア選手がスポーツで商売をしていると新聞に叩かれ、冨士枝は仰天した。まったくそんなつもりはなく、報酬だって得ていないのに...。記事を見た冨士枝はすぐに、いろいろと世話になっている日本選手団の後藤鉀二団長に電話した。
「後藤先生、私が新聞に出てます。アマチュア規定違反と書いてあります。どうしたらいいでしょう、卓球は続けられるでしょうか」
思いがけない出来事に不安でいっぱいの冨士枝だったが、しかし、後藤団長はあっけらかんとこう言った。
「気にするな、新聞で宣伝してくれたと思えばいいじゃないか。江口もみんなが注目する選手になったということだ」
そうか、悪いことをしたわけではないのだし、ビクビクすることはないんだ。後藤団長の言葉に冨士枝は気持ちがふっと軽くなった。
さらに、時の卓球協会会長の鈴木万平も冨士枝にこう告げた。
「江口選手のことは私たちが守りますから、安心して卓球に集中してください」
新聞に叩かれ、逆風の中に置かれた冨士枝だが、後藤団長や鈴木会長の言葉はそんな冨士枝を救うものだった。
―そうだ、みなさんの言う通りだ。私は卓球をがんばるだけ。
世界で活躍し注目を浴びたぶん、冨士枝はスキャンダルの餌食(えじき)として狙われることにもなった。だが、周囲の人の支えに感謝しながら、冨士枝はますます卓球に励むようになるのである。冨士枝は大学や上六の卓球場だけでなく、近くの高校にも練習場を求めるようになった。
さて、冨士枝が練習に来るということで高校生たちは興奮した。日本代表の江口冨士枝と言えば、高校生には雲の上の人。そんな冨士枝から「練習に行かせてもらってよろしいですか」と電話を受けたのは三国ケ丘高校卓球部だった。部員たちは授業が終わって午後4時ごろからぼちぼちと練習場に向かった。ところが、卓球場にはすでに人影がある。どうやら雑巾がけをしているようだ。その人影が冨士枝だった。
世界の江口が高校で掃除をしている。驚いて「やめてください」と頼む高校生たちに、冨士枝はにっこり笑ってこう言った。
「私はここに練習させてもらいに来たんだから、掃除するくらいは当り前」
高校生たちはものを言うこともできず、感激して立ち尽くした。それからである、三国ケ丘高卓球部は授業が終わると部員全員が走っていって掃除をするようになった。
当時、三国ケ丘高校で練習をしていた星野展弥(1959年世界選手権大会男子団体優勝、1961年世界選手権大会男子ダブルス優勝・混合ダブルス優勝)は言う。
「あのときはびっくりしました。江口さんはそういうことを普通にやる。江口さんにはそんなエピソードがいっぱいある。高校生とやってもあの人は絶対に『練習に行った』ではなく『練習をさせていただいた』と言う。自分で進んで動くから、自然と周りがついていってしまう。江口さんはそんな人です」
星野は後に日本代表メンバーとなり、冨士枝とともに代表合宿に参加することになる。そして冨士枝は、この年(昭和29年)の全日本選手権大会で、昨年の2位からさらにステップアップし優勝を遂げるのである。
大学中退
全日本で優勝した冨士枝は、1955(昭和30)年の世界選手権ユトレヒト大会の代表にも選ばれた。しかし、このとき冨士枝にとって苦しい事態が持ち上がった。
冨士枝の大学の出席日数は、大会などの都合で不足していた。そして、出席日数が足りないと試験が受けられないのだった。日本代表選手という事情はあっても「江口だけ特別扱いするわけにいかない」というのが学長の方針だった。冨士枝はなんとか卓球と学業の両立を図ろうとしたが、出席日数不足は努力で解消できるものではない。冨士枝の進級は絶望となった。そして、世界選手権ユトレヒト大会を前に、冨士枝は大学を去った。
そうした悔しい思い、情けない思いをしながらも、冨士枝は前向きさを失わなかった。
―勉学にはこういう厳しさが必要なんだ。私だけ特別扱いされるのはおかしい。私はこれでよかったんだ。
こうして臨んだ1955年世界ユトレヒト大会の結果は女子団体2位。冨士枝は翌1956(昭和31)年の世界選手権東京大会にも日本代表として出場し、結果は女子団体3位だった。世界戦デビューのウェンブレー大会で手に入れた「優勝」の2文字は手に入らず、冨士枝はシングルスでも思うような成績は残せなかった。
そんなとき、冨士枝に「今度うちに卓球部をつくるから来ないか」と誘いがかかった。東京にある東洋レーヨンだった。冨士枝はこの誘いに乗り、1956(昭和31)年10月に単身上京した。冨士枝は持ち前の人を和ませる性格で、東洋レーヨンでもすぐに楽しい人間関係を築いた。
不本意ながら大学を去ることになり、世界大会でも思うような成績を挙げられずにいたが、冨士枝はこの上京を機に心機一転がんばろうと思った。初めて親元を離れての生活は寂しく、不安な面もあった。しかし、新しい環境で卓球をすることは新鮮で、冨士枝の不屈の精神がむくむくと頭をもたげた。
そしてその年の12月、冨士枝は全日本選手権大会の決勝の舞台にいた。対戦相手は渡辺妃生子。世界大会やアジア大会に何度も一緒に出場する僚友であり、また冨士枝のライバルでもあった。結果は3-1で冨士枝が勝利。全日本2度目の優勝となった。
世界一
翌1957(昭和32)年、冨士枝は世界選手権ストックホルム大会へと出発した。そして、この大会に向けて冨士枝は万全の準備を整えていた。
当時、世界選手権大会で上位に上がってくるヨーロッパ選手は、ルーマニアのロゼアヌのようにカットが主流だった。世界で勝つためにはカット打ちができないと話にならない。だが、日本選手にはまだ練習相手になるカットマンが少なく、冨士枝はカット打ちが苦手だった。この苦手を克服すべく、冨士枝は東洋レーヨンの門屋豊徳コーチを相手に猛特訓をした。カットマンの門屋コーチを相手に、初めはまったくラリーが続かなかった。そこで冨士枝は自分にノルマを課した。ミスをしたら体育館をうさぎ跳びで1周。絶対にミスをしないと集中して練習した結果、冨士枝のカット打ちは見違えるようになっていた。
「江口はタイトルを取る気がする。合宿練習を見た人は誰でもそう感じるに違いない」
これは、日本選手団の南駿一団長が出発前に出したコメントだ。
さて、準備のかいあって、ストックホルムでの冨士枝は絶好調だった。江口冨士枝・渡辺妃生子・大川とみ・難波多慧子のメンバーで臨んだ女子団体、冨士枝は宿敵ロゼアヌを倒して日本に優勝を呼び込んだ。また、荻村伊智朗と組んだ混合ダブルスでも優勝を果たした。そして、女子シングルスでも冨士枝は念願の決勝に進出していた。
女子シングルス決勝の相手はイギリスのヘイドン。左利きのシェークハンド攻撃型のヘイドンは体格に恵まれ、卓球だけでなくテニスにおいても世界のトップに立つ、スポーツ万能選手だった。
冨士枝とヘイドンの試合がスタートした。1ゲーム目は21-14で冨士枝が取り、2ゲーム目も24-22で冨士枝が取った。
―いいぞ、3-0のペースだ。
冨士枝は勝利が見えたと思った。しかし、0-2と追い込まれた3ゲーム目にヘイドンは勝負に出た。攻撃に転じたヘイドンの前に、冨士枝は3ゲーム目を19-21で落とし、4ゲーム目も21-23のジュースで取られてしまった。冨士枝の心に動揺が走った。
ヘイドンは軟らかいスポンジラバーを操り、ボールの音を全然させないという特徴を持っていた。焦りを感じている冨士枝は、ヘイドンが振った瞬間にボールが自分のコートに刺さるような錯覚を覚えた。
2-2となった休憩時間、冨士枝は必死に考えた。これまでの4ゲームを振り返り、最終ゲームをどうするかを考える。世界選手権大会の女子シングルス決勝、もう二度とないチャンスかもしれない。仲間のためにも、胸につけた日の丸のためにも、絶対に勝ちたい。冨士枝は必死に考えた。
落とした2ゲームは消極的過ぎたかもしれない。この消極性を積極性に切り替えなくちゃいけない。世界戦決勝というプレッシャーをはねのけなくちゃ!
最終ゲームはそれまでの勢いを保ったヘイドンのペースで試合が進んだ。冨士枝は13-17とリードされ、イギリスの応援団が大歓声を上げた。
しかし、この土壇場で冨士枝の武器が爆発した。全力を込めたフォアハンドと、それを支えるフットワーク。冨士枝は一気に攻撃に打って出た。度胸を決めて必死にぶつかっていく冨士枝の攻撃の勢いは、ヘイドンにあった流れを奪い返した。
19-19。
会場中が息をのんだ。
環境の不足、指導者の不足、冨士枝はすべて自分で考え、工夫して切り抜けてきた。自分には才能などないと思い、人の倍の努力をすることを自らに課してきた。
20-19。
冨士枝の強烈なフォアハンドスマッシュが決まった。そのフォアハンド、そしてフットワークは、冨士枝が黙々と練習を重ねてきたものだった。
21-19。
またもやフォアハンドスマッシュが決まる。ヘイドンは冨士枝の前に倒れた。
「ゲームアンドマッチトゥー、エグチ」
1957年3月15日、世界チャンピオン・江口冨士枝が誕生した。
卓球が大好きで、親に反対されてもけろっとして練習していた元気な冨士枝。優しい気性で周囲の人間を和ませてしまう冨士枝。そして、誰よりもがんばり屋の冨士枝。たくさんの拍手と歓声を浴びながら、24歳になった冨士枝は世界の頂点に立っていた。
「江口選手、国際電話です。ご家族とお話ししてください」
「えっ!?」
冨士枝の前に、新聞社の容易した受話器が差し出される。
「冨士枝、お前本当に優勝したのか。すごいぞ。よくやった」
「あんなに甘ったれ子だったのにねえ」
期せずして受話器の向こうから伝わってくる父たちの喜ぶ声を聞きながら、冨士枝は感激の涙が止まらなかった。
いつも冨士枝を陰で支えてくれた家族のみんな。娘の卓球に反対しながらも激励してくれた父には海外遠征の資金も援助してもらい、苦労をかけた。
―でも、これで少しは恩返しができたのかな。
冨士枝の心は、感激と感謝でいっぱいだった。両親だけではない、いろいろな人のおかげでここまで来られた。見えるところで、見えないところで、本当に多くの人に...。
感激屋の冨士枝はいつしか号泣していた。
1957年世界選手権ストックホルム大会。このとき日本は男子団体(荻村伊智朗・田中利明・角田啓輔・宮田俊彦)、女子団体、男子シングルス(田中利明)、女子シングルス、混合ダブルスと、なんと5種目に優勝したのである。
さて、世界チャンピオンにはなったものの、冨士枝はまだやり残したと感じていることがあった。世界を極めた冨士枝は、ひそかに次の使命を自らに課していたのである。
(2002年4月号掲載)