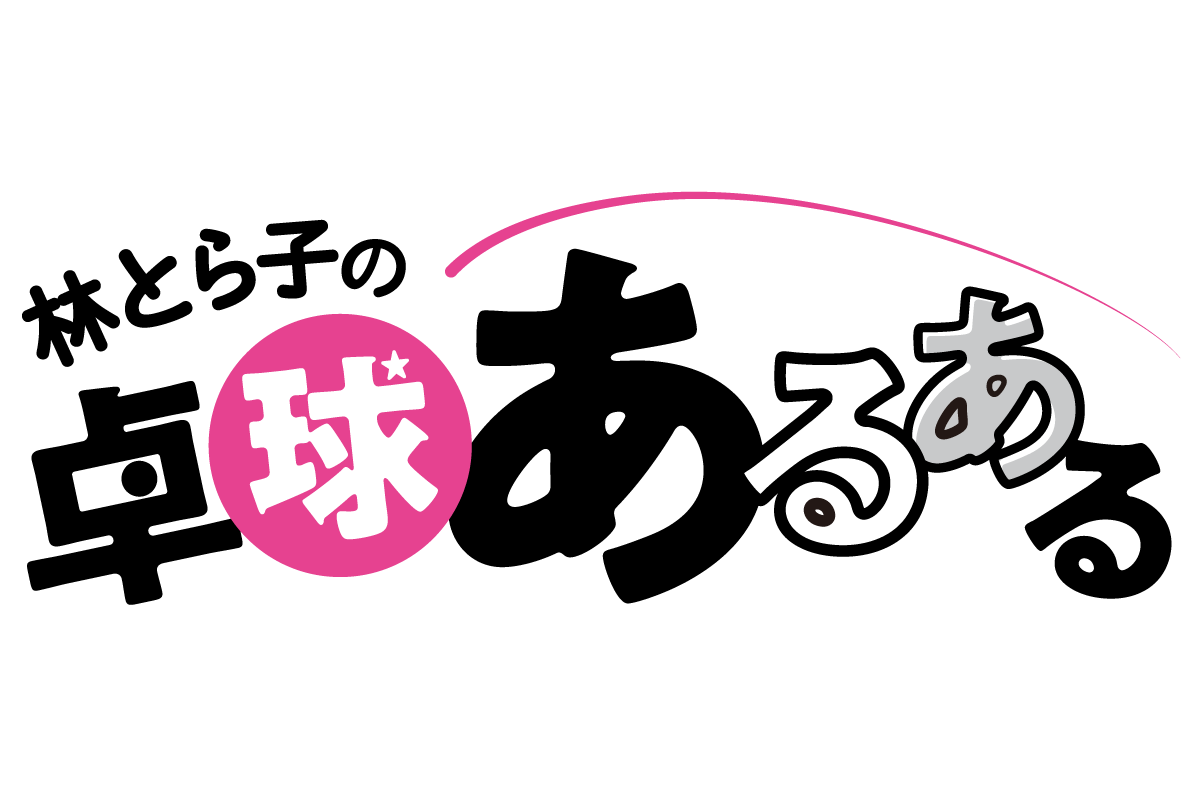ドライブ
「上」を目指すためには、大嫌いなカット打ちを克服しなければならない。それも、世界に通用するほどに。
まずは、つないでいるだけでもミスを連発してしまう現状を打破することから始めなければならない。深津は、男子のまねをしてみることにした。
ループドライブでつなぐ男子の卓球は参考になった。それまでの深津は、フォアハンドの攻撃はドライブではなく、すべて角度打ち。ツッツキと角度打ちでつなぎ、チャンスボールをスマッシュした。この戦い方が間違っているというわけではないのだが、角度打ちではどうしてもミスが重なる上、深津のスマッシュには威力がなかった。
当時、女子でドライブを使う選手はいなかったが、飲み込みの早い深津は男子のプレーを参考に見よう見まねで習得していった。高校時代は「カット打ちができない、練習してもうまくいかない、カット打ちはしたくない、カット打ちができない」という悪循環に陥っていた。しかし、ドライブという新しい技術を学ぶことで、この悪循環は解消された。また、深津はもともとスナップを利かせて打つことが得意で、打法に相応した強い手首も持っていた。
「これはいけそうだ」
深津は、インパクトの瞬間に手首の動きでボールに回転をかける技術を身につけていった。それまでは、ラケット面を上下させることでボールに角度を合わせていたが、これからは自分で微調整することができる。深津のプレーは変わり始めた。
「ペンドライブ型」の女子選手は、世界でも深津だけだった。深津にとって、ドライブを覚えたことは、世界を制することに直結していく出来事だった。
飛躍への第1歩
昭和38(1963)年、深津は大学1年生でありながら、全日本学生選手権大会で準優勝を飾った。
まさかの決勝進出だった。深津は、関東学生でベスト16にも入っていない。全国大会で決勝まで勝ち進むとは、夢にも思っていなかった。
このときの優勝は中央大学の関正子。全日本選手権大会も制している女子ナンバーワン選手だ。ペン表ソフトで、ピッチの速い速攻型だった。
深津は、カット打ちのために始めたドライブを、攻撃型に対しても使おうと試みていた。しかし、まだドライブを主戦にする段階には達してはいない。そこで、関との試合では従来通りの角度打ちを駆使した前陣攻撃で挑んだ。
慶應大学のベンチは大騒ぎだった。慶應の卓球部はここ数年、全日本学生チャンピオンの座から遠のいていた。深津が関を追い詰めると、校歌を歌う準備を始めたり、集合写真のために身だしなみを整えたりと、応援どころではなかった。
深津も勝ちを意識した。高校時代は優勝して当り前だったが、大学ではこれまですっきりした勝ちがない。
関は、深津の心のすきを見逃さなかった。ゲームカウント2-1で深津リードの4ゲーム目、16対19と追い詰められながらも、5本連続で3球目攻撃を決めて一気に逆転(当時、サービスは5本交替)。試合を2-2の振り出しに戻し、最終ゲームもきっちり取って逆転優勝をさらった。
慶應ベンチは落胆したが、深津は悔しさよりも「よくやった」と感じていた。相手は大先輩であり、日本の第一人者だ。忘れられない1戦になった。
昭和38年11月に行われた全日本学生選手権大会女子シングルス決勝、これがドライブを使わずに戦った最後の試合になる。ドライブを武器に世界を制するのは昭和40年4月。たった1年と半年後のことである。
海外遠征
全日本学生選手権大会の結果が認められ、ドライブを操るという特殊な戦型も注目され、深津は大学2年生で日本代表入りを果たした。初の海外遠征は、昭和39(1964)年9月25日から10月4日にかけて韓国のソウルで行われたアジア選手権大会だった。
日本は強かった。国の政策で中国が出場しなかったとはいえ、アジア7チームが参加。その中で日本はダントツの実力を見せつけた。11種目(男女団体、男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルス、ジュニア男女団体、ジュニア男女シングルス)すべてを制し、ボンベイ大会、マニラ大会から続く3大会連続完全優勝を飾ったのだ。
日本選手は優勝するか、同士打ちで負けるかのどちらかであった。だが、深津だけが女子シングルスで初戦敗退。
「情けない」
初めての日本代表、初めての海外遠征だったのに...。悔やんでも悔やみきれない結果だった。相手は1枚ラバーを使う韓国選手だった。前陣で戦っていた高校時代は、1枚ラバーを使う選手は得意だった。しかし、ドライブを使うようになり、攻めが遅くなった。スピード、ピッチという深津の持ち味は、以前よりも鈍っていた。カット打ちを克服するための代償だった。
深津は、高校時代と逆になっていた。ピッチの速い卓球をする相手に弱く、カット型に強い傾向になったのだ。
昭和39年、大学2年生のときの全日本学生選手権大会では、国内のカット主戦型の第一人者ともいえる磯村淳(専修大学)に勝った。それ以来、国内のカット主戦型には全勝する。
その一方、ピッチが速い相手が苦手になった。例えば、後に全日本選手権大会女子シングルス100勝の大記録を打ち立てる伊藤和子(1枚ラバーを使ったピッチの速いプレーが特徴)には、「痛い1敗」を喫している。
「痛い1敗」というのには訳がある。伊藤和子に負けたのは昭和41(1966)年の全日本選手権大会女子シングルス準々決勝。全日本選手権大会は例年東京で開催されるが、この年は深津の地元・愛知県で行われた。
深津は大学4年生。世界選手権大会で優勝した後だった。地元の英雄の凱旋(がいせん)に会場中が注目する。もちろん、深津への声援は大きい。ところが、駆けつけた恩師、チームメートたちが見守る中、深津は1-3で敗れた。
「伊藤さんの100勝には、私の『痛い1敗』が含まれているんですよ」
ダークホース
深津にとって2度目の海外遠征は、アジア選手権大会の直後に行われた第1回北京国際招待大会だった。昭和39年10月、まさに東京オリンピックと時を同じくして開催された大会である。中国をはじめアジア8チームが参加し、アジア選手権大会よりも勝つことが難しいといわれていた。
アジア選手権大会で初戦敗退している深津は、再び代表に選ばれる可能性は低いと感じていた。アジア選手権大会のときは、「深津を試してみるか」という意味合いの強い選考であった。女子には珍しくドライブを主戦にしている、若い...それらが選考の理由であり、実績が買われたわけではなかった。
しかし、若さゆえの経験不足と、本番でのドライブの不発。深津は選考漏れを覚悟した。
この時点での深津は、プレーの軸をドライブへと移行させる過渡期であった。そのため、試合では攻撃が中途半端に終わっていた。無理にドライブを使おうとして、攻撃が遅れてしまう。ちぐはぐな拙攻が続いた時期であった。
「ソウルで結果が残せなかったのだし、北京遠征の代表に選ばれなくても仕方がない...」
だが、そうした本人の評価とは別に、深津に対する周囲の期待は大きかったのである。「ここが人生のターニングポイントだった」と深津は言う。
深津は北京国際招待大会の代表に選ばれた。そして、日本の期待をはるかに超え、世界までをも驚かす結果を残すことになる。
対中国14連勝。
ドライブがおもしろいように決まった。中国選手の多くは前陣速攻型で、カット主戦型も少しはいたが、深津のループドライブを抑えきることのできる選手はいなかった。深津は見事、国際大会で優勝を飾ったのである。中国の総理・周恩来の手によって渡された優勝カップは、誰もが思わず目を見張るほど美しい七宝焼き。卓球を国技とする国の心意気が感じられた。
「ダークホース深津」
『卓球レポート』の報道からも、予想外の結果に驚く様子がうかがえた。
中国にとって、深津は研究対象外だった。関などはよく研究されており、実力差があっても肉薄され、よもやの敗戦を喫すこともあった。それほど日本に対するマークは厳しかったのである。荘則棟を中心に、国家を挙げての卓球強化が本格化していた時期だった。
そのような中で、深津は14戦全勝という結果を出したのだ。マークされていないとはいっても、相手は中国。それほど深津のドライブは精度が高く、世界に類を見ない技術の1つだった。
「世界で通用する」
誰もが確信した。
14勝のうちの1勝は、カット主戦型に対するものだった。林慧卿という両面裏ソフトのカット主戦型だ。簡単に勝つことができたため、深津にとっては印象の薄い相手であった。
しかし、この後深津が急成長を遂げる一方で、林慧卿は中国の秘密兵器として育てられてゆく。
「まさか決勝で争うことになるとは」
半年後の世界選手権リュブリャナ大会、女子団体と女子シングルスの両方の決勝で、深津と林慧卿は再び相まみえることになる。
反省
遠征での成績が評価され、深津は世界選手権リュブリャナ大会の代表の座を射止めた。
男子代表は木村興治・高橋浩・小中健・野平孝雄、おっして荻村伊智朗の5選手で、女子代表は深津尚子・関正子・山中教子・磯村淳の4選手。4月で大学3年生になる深津は最年少であった。
1番年下で経験がない深津は、先輩たちに比べれば代表としての自覚が足りない部分もあった。たいていは大目に見てもらえたが、1度だけ当時の日本卓球協会会長・後藤鉀二に強くしかられたことがある。
ある遠征中、深津は熱を出して寝込んでしまった。原因は、疲労と慣れない食事。何も口にできないでいた。
「冷たいものが食べたいなあ」
まともな栄養も取れていないのに、つい冷蔵庫のアイスクリームに手を伸ばしていた。そこを後藤に見つかった。
「君は自分の体調も維持できずに、恥かしいと思わないのか。まして君のために代表を外された人のことを考えたことがあるのか。よく反省しろ!」
今でもアイスクリームを食べると、このときの反省を思い出すという。
自分は運よく中国遠征の代表に選ばれたおかげで、今があるのだ。運悪く落とされてしまった、逆の立場になって考えたことがなかった...。
「のんびり屋さん」などといわれていた最年少の深津だが、このような経験を積み、日本代表であるという責任感、使命感が芽生えていったのである。
空前のハードトレーニング
「私は比較的恵まれた選手生活を送ってきましたが、このときの感激はまた格別でした」
世界選手権リュブリャナ大会の代表に選ばれたと知らされたとき、深津は喜びのあまり何度も「本当ですか」と聞き返した。一方で、「リュブリャナかあ。こんなことでもなければ、ユーゴスラビア(現在はスロベニア)なんて一生行けないわ!」と無邪気にはしゃいだりもした。
しかし、喜びはつかの間だった。
世界選手権リュブリャナ大会に向けて、後に「空前のハードトレーニング」と称されるほどの厳しい代表合宿が始まったのである。
監督は、選手と兼任で荻村伊智朗だった。そして、荻村にとって世界選手権リュブリャナ大会は、現役選手としては最後になるものだった。気合が入るのは当然である。
その荻村は、深津にとって4人目の指導者といえる。
「中学時代の城殿先生、高校時代の松井先生、高橋先生。1番元気なときに1番熱意ある指導を受けることができて幸運だった」
深津はこう語るが、荻村もそれに当てはまる。中学時代、高校時代、そして大学在籍中に代表入りしてからと、深津は指導者に恵まれ続けた。
だが、荻村の課す訓練は壮絶だった。
当時の『卓球レポート』から荻村の話を抜粋しておく。
「毎日5~6時間、4カ月にわたる強化訓練は続いた。3等分して、最初の3分の1は、決勝まで不安なく戦える体力づくり、2番目の3分の1は技術練習。カット打ちを基礎からやった。ピッチの速さにしても中国の速さについていけるだけの練習をした。あとの3分の1は実戦的、作戦的な練習を多くやった。たとえば、対張燮林、対荘則棟、対ヨーロッパなどの個々のプログラム練習をやった」
ハードな練習は、とりわけ男子にとっては当然だった。世界選手権リュブリャナ大会は、女子にとっては前回優勝の松崎キミ代に続いて連覇を狙う、いわば防衛戦。だが、男子にとっては、中国に奪われた地位を取り戻すための、死に物狂いの決戦だったのだ。
相手は両ハンド速攻で一時代を築く荘則棟、「魔球」を繰り出すペンカットの張燮林、実力世界一といわれる李富栄。まさに最強の布陣だった。荻村は「練習は1日5~6時間」というが、実際には夜中の3時まで続くことも珍しくなかった。
1000本ラリー
合宿では、カット対策として「1000本ラリー」が取り入れられた。1000本ノーミスでカット打ちをせよ、というものだ。
「何日かかってでも達成せよ!」
荻村の檄(げき)が飛んだ。
無変化球に対する1000本ラリーの次は、変化カットに対して500本ラリー。そして、スマッシュを打ってノータッチで100本抜く。選手には次々とカット対策が課された。それも、1センチでも深く、低くドライブを打つことを意識しなければならない。
結局、深津は1000本ラリー達成に3日かかった。
深津は疑問に感じた。
「私は国内のカット主戦型には負けないし、中国遠征だって簡単に勝った。今さらなぜカット打ちなのだろう。私だって以前よりうまくなっているから、大丈夫なはずなのに」
深津の考えは浅かった。荻村の考えは、はるか先にあったのだ。荻村の頭の中には常に中国の存在があった。
「日本に負けた中国は、どのような対策を立ててくるのだろう」
中国は世界の、日本の裏をかいてカット主戦型を育てていた。しかも、秘密兵器として育てていたのは、深津に大敗した林慧卿だった。そして、荻村はそれを読み切っていたのだ。
荻村の「先見の明」には驚かされる。荻村の一言で、日本は何度救われたことだろう。
「何でこんなことを」
深津たち選手は疑問に思いつつ、荻村に従っていた。世界選手権大会女子シングルス決勝で、深津がカットに対して170本も粘ることになるとは、誰も予想していなかった。
深津はこの練習から学んだことがある。
「攻撃は最大の防御でないときもある」
高校時代は、カットに対して無理に強打してはミスを繰り返していた。それは、カットとのラリーが続くことが怖かったからだ。だが、今は違う。深津はひたすらドライブを打ち続けた。
深津はトレーナーにも恵まれた。藤井基男がそうであった。1000本のノルマを達成できない深津に付き合い、最後まで相手をしてくれた。
合宿の最終日、深津と藤井は試合をした。深津が男子選手の藤井に勝つことなど無理なはずだったのだが、結果は、深津の勝利。
「出かける前だから勝たせてくれたんでしょう」
「いや、本当に一生懸命だったよ」
深津は、藤井に感謝し、達成感に満ちて合宿を終えることができた。
相手を務めた藤井は、深津の確かな成長を感じていた。
「荻村さん、今回は深津が優勝するんじゃないですか」
「まさか...」
深津は荻村の予想を超える結果を出すことになる。
(2005年8月号掲載)