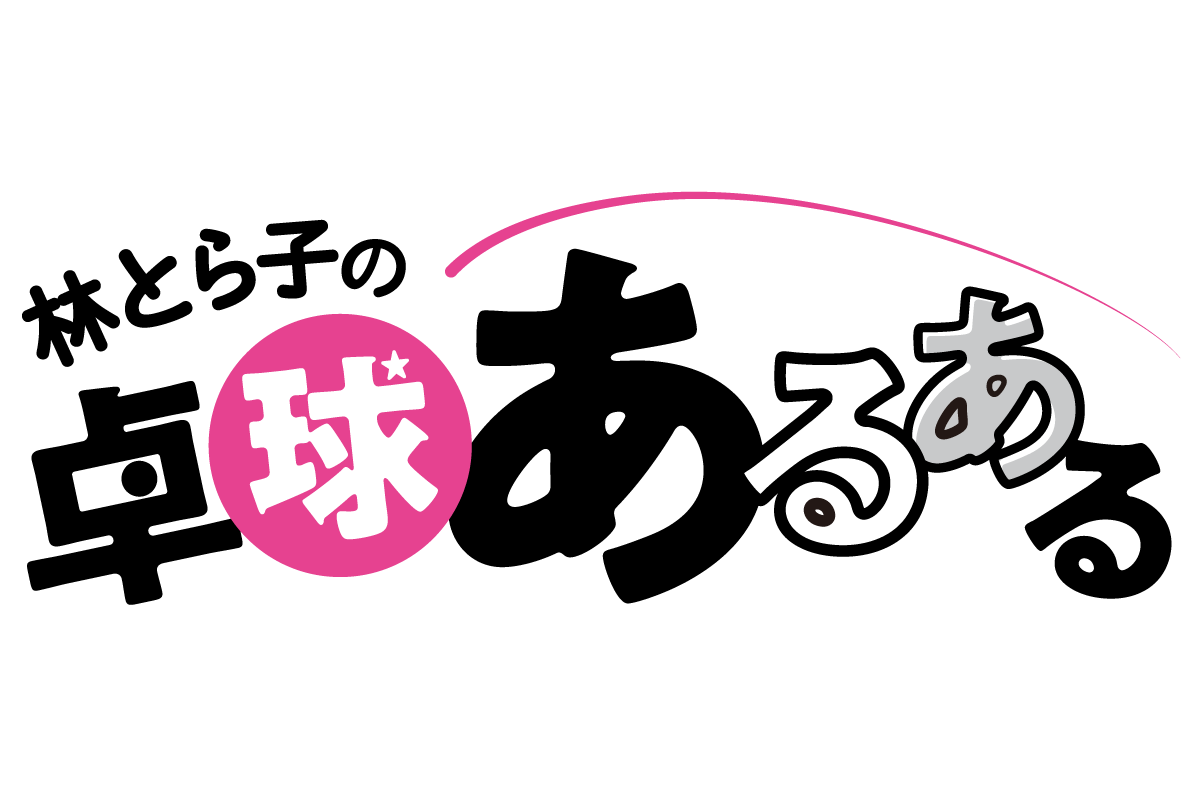世界の舞台で
全日本選手権大会で初優勝した松崎は、その翌年開かれる世界選手権の代表に選ばれた。ドルトムントで松崎の世界への挑戦が始まったのである。その大会で松崎は初出場で団体優勝、シングルス優勝と華々しいデビューを飾るが、そこに至るまでには周囲の支えと、特に先輩江口の存在がなければ栄冠をつかむことは難しかっただろう。
やがて日本の大黒柱に成長した松崎は、反日感情の渦にあった世界選手権北京大会に挑んでいく。
世界選手権大会出場が決定
1959年1月、松崎は第25回世界選手権大会(ドルトムント)の代表に決まった。男子は荻村、成田、村上、星野。女子は江口、難波、山泉の先輩たちと松崎。外国へ行ってみたい、外国の選手と試合をしたいという夢がかなった。最年少の20歳。代表決定後、間もなくロゼアヌとツェラー不出場のニュースが舞い込んだ。松崎は「シングルスに6連勝したロゼアヌの試合が見られる、ひょっとしたら対戦できるかもしれない、どんなカットなのだろう、と楽しみにしていただけにガッカリしました」と、振り返る。
当時の世界卓球界は強豪といわれた選手はみな守備型で、カットを打ち崩すことができなければ世界の頂点は見えてこないのであった。そのため、ドルトムントへ出発するまでの4回の合宿では、大半がカット選手相手の練習だった。大学で活躍していた男子選手がそのトレーナー役だった。高校時代にカット選手と練習する機会のなかった松崎は、全国大会でカットが打てず惨めな自信喪失を味わっていた。このため、大学に入ってからは世界に目を向けて練習の中にカット打ちを課していた。しかし、これが難しく、変化するカットに対し、正確さと作戦の面で自信を持つまでにはなかなか近づけなかった。
「回転を見極めるためなら何でも取り入れようと、駅のホームで通過していく電車をよく見ていました。私は右利きですから、左から右へ走る電車に合わせて首を動かして中を見る。それを繰り返すんです。すると、かなり速く走っている電車でも中の乗客の様子がはっきりと見える瞬間があるのです。この要領で、飛んでくるボールを見ると、バウンドして頂点に達するあたりで回転を確認することができるんですね。また、先輩選手の中には、自分が電車に乗っているときに通り過ぎていく電柱に貼ってある記号や文字を見る訓練をしたといいます。今でいう動態視力を高めるためです。回転が見えたとしても、ラケット操作を間違えないでカットのボールを打つのは大変難しいことでしたが...」
大会直前に発熱。江口を呼ぶ
3月下旬のドイツ(当時は西ドイツ)・ドルトムントは日本より1カ月も遅い気候で、寒く乾燥していた。何もかも初めて経験することばかりの松崎は、出発前のオーバーワークがたたったのか、環境の変化に順応できなかったのか、大会の始まる2日目に突然体調を崩した。「全員個室のベッドに入って間もなく、体中の節ぶしが痛いようなだるいような、なんともいえない不快感がありました。そのうち、氷水を全身にかけられるような悪寒が襲ってきたのです。ガチガチと歯が鳴り、体がベッドから浮き上がりそうになるほどで、小さく縮こもって震えるばかりでした。心細さと、申し訳なさで...、迷いましたが、意を決してキャプテンの江口さんに電話しました。時刻は深夜12時頃で、江口さんは寝入ったばかりだったはずなのにすぐ来てくれ、『大丈夫、心配せんときや』といい、自分のベッドの毛布を持ってきてかけてくれたり、私のコートをかけてくれたのです。しばらくして震えがおさまったのですが、今度は体中が熱くなり、脈拍がどんどん早くなり、そして鼻から口から熱風が出てくるような感じになったのです。江口さんはすぐさま水道水でタオルを濡らしては、私の額に当ててくれました。ところがそのタオルはすぐに温かくなるので、頻繁に取り替えなければならない...。そこに監督の長谷川さん、宮本さんの声とともに、医師がやって来ました。江口さんは、途中から自分のベッドのマットレスを運んできましたが、ほとんど看病で寝ていなかったのではないかと思います。全く、自分の身をいとわず介抱してくれました。朝になると、江口さんは他の選手たちと食事に行き、午前の練習へと出かけていったのです」と、松崎。江口に対する感謝の気持ちは、今もって変わらないという。続けて、松崎は自らの試合と江口の試合について次のように語っている。
団体戦2敗喫す
「そんなわけで、私は団体戦の途中から出場し、大事な場面で2敗してしまいました。1敗はハンガリーのコチアンに1-2。コチアンは凡ミスの少ない正確なカットであるのに対し、私の方は淡白な攻め方しかできず、カットを打ち切れなかったんです。早々と世界の壁の厚さを思い知らされました。トップの私が落とし、ダブルスも負けたために、1対2と追い詰められ、4番で江口対コチアン戦となりました。
手に汗握りながらもこの試合の江口さんは本当に素晴らしかった。右に左にとコントロールされたカットを、完璧なフットワークと強弱をつけたフォアハンドで、粘るコチアンからチャンスをうかがうというものでした。特に3ゲーム目は出足から大接戦でした。チャンスを強打、もう1本...、ところが低いカットがしっかり返ってくると深追いせず、チャンスのつくり直しです。こんな緊張した状態で、ラリーが60本を超えることもありました。すごいフットワーク、体力...。そういえば、日本での合宿で、1日7時間の練習の中で、午後3時から30分だけは休憩があり、この間は誰もが体を休めるのに、江口さんは『マツさん、まわして!』と、一番きついフットワーク練習をしたものでした。私だけでなく、まわりの人たちも江口さんの体力と意気込みの厳しさにびっくりしたものです。あの厳しい練習が、今この修羅場でしっかり生きているんだ―私は驚きと尊敬の念で、すごい勝利に感謝しました。
もう1敗は、日本対韓国の決勝戦で、エース曹に4番で敗れました。これを勝っていれば日本が優勝という場面だったのですが...。曹はペンホルダーの攻撃型でしたからやりにくくはなかったのですが、私のサービスとレシーブが甘かったと思います。この敗戦のためにラストの難波さんに余計なプレッシャーがかかってしまいましたが、怖いような試合を、最後切り抜けてくれました。この団体優勝は生やさしいことで手に入れたものではありませんでした。それも私の敗戦のために...。私はもっと確実なポイントゲッター、大黒柱にならなければ!と心から反省しましたね」。そして、次はシングルスに挑むことになる。
決勝は、江口対松崎の同士討ち
―勝負と恩義のはざまで―
「私は初出場で世界選手権大会についてよく分かっておらず、ましてや団体戦でも負けているので、自分が個人戦で上位にいけるとは考えていませんでした。それが、どんどん勝ち進んで、とうとう決勝に出たのです。一方、反対のブロックからは江口さんが上がってきました。皮肉にも、徹夜で親身になって看病した人と、その看病のおかげで元気になったものとが世界の決勝を戦わなくてはならなくなったのです。同士打ちというのは、本当に嫌なものですよね。この場合、単なる同士打ちとは異なりますし...。あの夜、苦しくて心細くて助けを求めた江口さんの姿は、意識のもうろうとする中でどんなに癒(いや)されたかしれません。そんな恩人と、翌日に戦わなければならなくなったのですから、私は悩みました。江口さんはもう家庭に入っていて、この大会の後引退が決まっていました。もし私が負ければ、江口さんはシングルス2連勝となり、素晴らしい花道となるでしょう。私も一生懸命戦って負けるのならいいのです。しかし、もしかすると私が勝つこともあり得るわけで、それは情け知らずではないだろうか...と考えてしまいました。
私が江口さんに対し負い目を感じながら試合をして敗れたとしたら、当座はこれでよかったんだと自分自身で納得するかもしれませんが、しかし、時が5年、10年と経(た)つにしたがって後悔するのではないだろうか...とも。
ルールにのっとり、互いが勝負を競うのがスポーツである。ルールを無視してやみくもに勝ちにいくことは、もちろんスポーツの本質を汚すことになる。また、たとえどんな理由があるにしても、全力を出し切らなかったり、相手に勝ちを譲るような行為をしたならば、その瞬間にスポーツの精神からはずれたことをしていることになる。
こうして理屈では分かっていながら、人情との板挟みになって、決勝前夜の私の頭の中は堂々巡りするばかりでした。しかし、大いに悩んで、その上で決断するのがよいという考えに達し、それを自分に言い聞かせていました。明日は個人戦5種目の決勝戦です。『今夜のうちに決心を固めよう、試合に入ってから迷いながらプレーをするようなことはみっともないから』
私自身、後に後悔するような選択はやはりすべきでない!逆に、戦い終わった後、江口さんに対して申し訳なさで苦しんだとしても、時が経って『あのときの選択は正しかったんだ』と言える方を実行すべきだ、という考えにだんだん絞られてきました。
何しろ、世界の舞台の、その中でも最高の舞台に立つわけです。そう思うと、自分の考え悩んでいることがちっぽけなことのように思えてきたのです。これが明け方まで居ずまいを正して出した結論でした」
決勝戦は3-1で松崎が勝った。二人の特長がよく出た激しい攻撃卓球を世界の人々に披露したのだった。しかし、試合を終え、表彰台の上で松崎は笑うことはできなかったと、当時を振り返る。松崎は、江口と一緒に日本代表になったことで、実に多くのことを学んだという。広い心、卓球への厳しい取り組み、コチアン戦で見せたカット攻略法などいろいろある。松崎との決勝戦でついに力尽きたが、そのときもひたむきな態度は変わることはなかった。そして江口は、心技体の質の高さを5歳若い松崎に託すように退いていった。
このドルトムント大会では、日本は7種目中6種目に優勝した。新聞は連日大きな活字で、スポーツ面の大半を割いて日本選手の活躍を伝えた。『日本チーム○○国を撃破』『日本、○○国に完勝』という具合で、戦後の虚脱や喪失感のまだ残る日本社会で、卓球愛好者ばかりではなく一般の人たちをも勇気づけたのであった。
松崎の郷里高瀬では、日本男女団体がそろって優勝した日に、ちょうちん行列で祝ったそうである。また、松崎が帰国して高瀬に帰ったとき、2トン車をオープンカーにして香川県の西半分一帯をパレードしたそうである。
「チャンピオンの座を保持するのは、チャンピオンを目指すよりも難しい」。だから、チャンピオンになったのはその一瞬だけで、また次に改めてチャンピオンに向かって挑戦するのだ―そんな言葉を糧にする松崎は、限界を超える練習、トレーニングを重ねていった。
国内の大会では、2年連続で東日本学生、全日本学生、全日本、この3大タイトルの単複を獲得するなど順調だった。
戦い方の転機はけがからだった
それは4年生の夏であった。フォアへ大きく飛びついて打つという練習を繰り返していて、左股関節をけがしてしまった。左足を着地したとたん、股関節がグジッという音がして、左足に全く体重がかからなくなってしまったのだ。一瞬、選手生活が続けられないのでは...、と不安になるほどの痛みだった。いろいろな治療をしたが、自分の最も得意なバックへの回り込み強打という動作がとても苦痛になったのである。このけが、故障のために、前陣でバックハンドをマスターして足の負担を少なくする卓球に変えていかなければならないと真剣に考えた。自分ではやむを得ずではあったが、本当はその卓球スタイルに変えるべきだったのである。
次の第26回世界選手権大会は北京で開かれることになっていた。中国は速攻型が主であり、地元なので大挙出場してくるに違いない。相当な強化をしてくるだろう。
どんなにフットワークがよくても、中国の右打ち左押しの速さに対して、フォアハンド主体の卓球では到底無理なのである。
松崎の股関節故障は結果的には『中国選手に対してバックハンドもどんどん使えるような卓球に切り替えよ!』という信号だったのかもしれない。随分と痛みを伴う信号ではあったが...。
松崎は中陣でのバックハンドは振れなくはなかったが、前陣での鋭い振りはできなかった。フォアハンドに比べ振りの力強さが全く違うのがじれったかった。そこで、松崎は大学の卓球練習場の続きにあったボクシング練習場のサンドバックをめがけてバックハンドの素振りをすることを思い付いた。
自分がやりたいのは
●ショート対ショートから先にバックハンドで攻める
●レシーブあるいはツッツキからバックハンドスマッシュ
●ラリー戦の中では、バックにチャンスボールがきたらバックハンドスマッシュ
これらをどうしてもマスターしたいのだ。
北京大会まであと半年余り。「間に合うだろうか」「試合の中でも勇気を出して使っていかなければ」と必死になって取り組んだ。また、カット打ちもおろそかにはできなかった。
国威発揚の北京大会
第26回世界選手権大会(北京)は、1961年3月下旬に開かれた。代表は荻村・星野・渋谷・木村・三木、女性は岡田(旧姓大川。1957年世界チャンピオン)・伊藤・関・松崎というメンバーだった。2回目の世界選手権出場で、初めてのときのような感慨はないが、選手としての自覚と責任をより強く感じた。
「中国は社会主義の中華人民共和国になって12年目、日本とは国交がありませんでした。『軍国主義の時代に日本が侵略戦争をし、日本の軍隊が侮辱、残虐の限りを行った国で、私たちは試合をするんだ』ということを、出発前に諭(さと)されました。
中国は大きなスポーツの国際試合を開催するのは初めてとあって、国をあげて組織し運営しているのがよく分かりました。この大会のために1万5000人収容の円形体育館が完成したばかりでした。手厚いもてなしも受けました。しかし、大会会場では、日本選手団は全く孤独でした。見れば、アメリカ選手に対する観客の反応も私たちと同じでしたね。日本の対戦相手が中国選手のときはもちろんのこと、他の国の選手であっても、満員の観衆は相手選手を応援するのです。日本選手にスマッシュをあびせたときなどは、まるで鬼の首を取ったように大歓声と拍手がかぶさってきました。そして相手が日本選手を追い込んで、あと1本、というときのミスには、『惜しい!』『ナァーンダ!』という大きなため息が耳を突き刺すようでした。私たちは相手選手と観衆と、そのうえ審判員まで向こうに回して戦わなければならなかったのです。
対日感情の激しさは、その当時の政治的な背景も強く影響していました。政治にうとかった私など、『最初の頃はなぜ観衆がここまで徹底するのか...』と戸惑いました。微妙な判定も、明らかにこちらの得点という場合でも相手選手の得点になりました。ここまでくるとすぐに割り切りました。こちらのエッジはすべてサイドであり、相手のサイドはすべてエッジなんだと思うようにしたのです。
大会前、日本の得た情報では、中国は対日本ならば男子は絶対に中国が強い、女子は五分五分とのことでした。これには驚きました。なぜなら、日本が世界に出たロンドン大会以降5連勝している日本男子が中国に勝てる要素がないというのですから...。どれほど強化したのだろう、どんな強い選手が生まれているのだろうと不安になりました。そして、予想通り男女とも日本対中国の決勝戦になったのです―」
(2000年9月号掲載)